城戸四郎は1894年(明治27年)、東京の築地の生まれ。
一高、当代法学部を出て一度は国際信託銀行(現みずほ銀行)に就職したものの、当時の松竹社長・大谷竹次郎に乞われて松竹キネマに入社。
以降、松竹鎌田撮影所長、松竹副社長、社長、会長を歴任した。
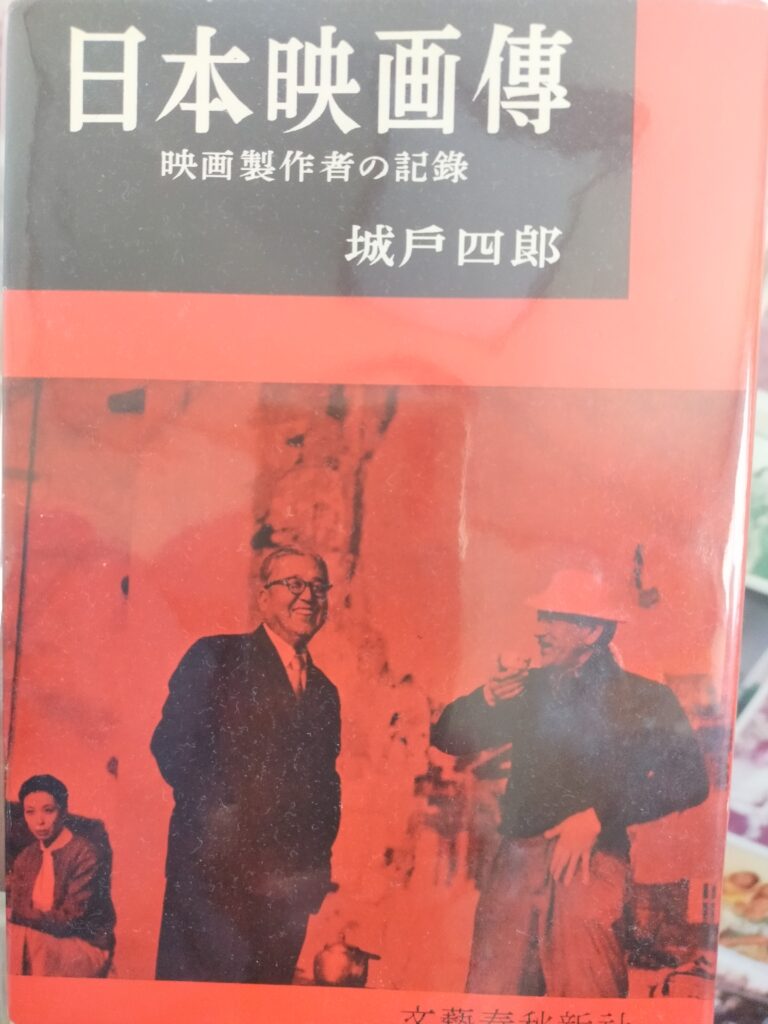
その城戸の1956年文芸春秋社刊「日本映画傳」を読む機会があった。
創立当初から現在に至るまで、日本映画のメジャーの地位にある松竹の戦前戦後を通しての、会社経営者であり映画製作者であり、日本版タイクーン(ハリウッドでいえば、セルズニックやザナックの位置づけか)でもあった城戸の自伝である。
全盛期の日本映画の記録としても貴重なものだった。
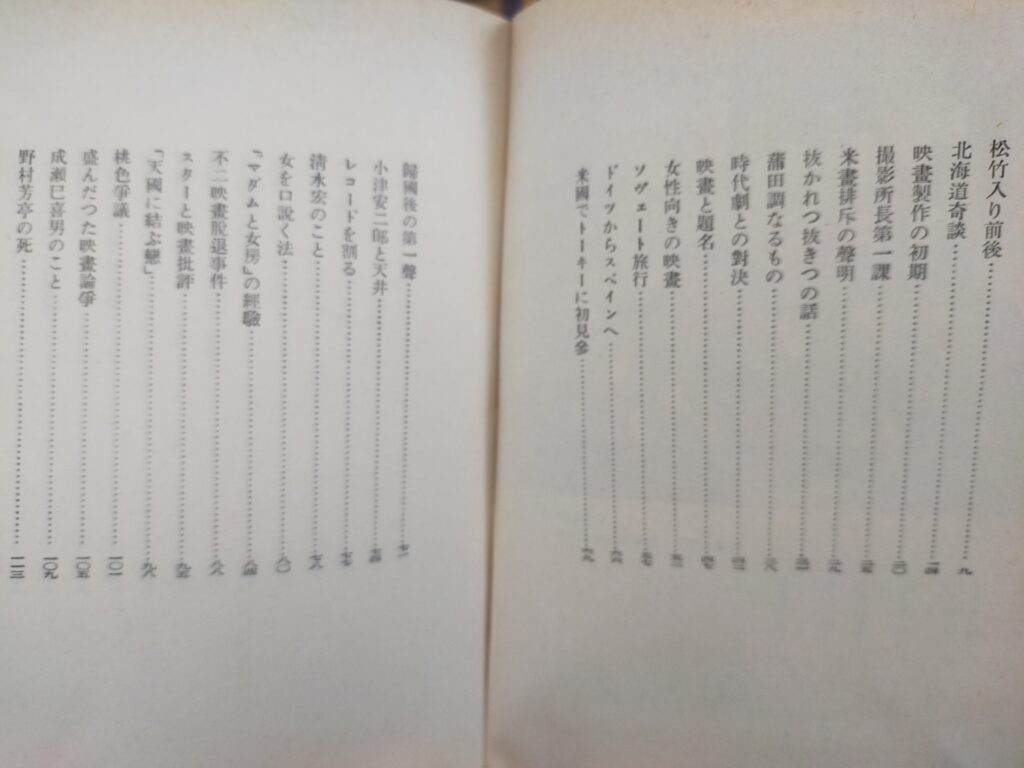
新聞記者志望で弁護士資格を持つ城戸が、戦前の興行会社である松竹に入社した経緯は、本著では「以前からぼくの家とはちょっと知り合いの松竹の大谷社長から、松竹へきて働かぬかという話をうけた」(同著P11)と簡単に表現している。
これは、城戸の生家が築地精養軒という日本における西洋料理の草分けであり、東京の拠点を築地に置いていた松竹の大谷社長との接点があったこと、大谷社長が長男を亡くし後継者を捜していたことが契機になってのことだと思われる。

松竹は関西の芝居小屋の経営を母体にした興行会社であり、当時も今も関西の芝居、映画の興行、東京での歌舞伎、芝居、映画の興行がメインの会社である(映画製作については現在も行ってはいるが、唯一の直営撮影所であった大船撮影所を手放した現在では、メインの事業ではなくなっている)。
当時の興行界は、小屋に出入りするヤクザ、巡業先の地元のヤクザ、役者、小屋主との付き合いが、今よりも重要視される特殊な業界であり、城戸のようなエリートが就職先として選ぶことはまれであった。

本著では城戸が行った松竹キネマを舞台にした経営者としての業績が数々つづられる。
具体的には、
撮影所内で女優を妾とし、少し人気が出れば自分の実力のためと過信する俳優たちと対峙して撮影所内のシステムと風紀を是正した。
契約したフィルム貸出料金を滞納する映画館主たちから回収を行い松竹の財政を改善した。
戦前の対抗勢力であった日活との間で興行戦争を行いスターを引き抜き合った。
新興勢力東宝との間で日比谷の興行街の利権争いでは一敗地にまみれたものの、別件でまき返した、などなど。
一方、製作責任者として、自らの理念に沿った施策も行った。
具体的には、
撮影所内にシナリオ研究所を作って人材を育成し、
撮影所をスターシステムからデイレクターシステムへと変更し、
新人育成用に中編映画を製作する、など。
また、
映画批評家と松竹作品の内容を巡って論争したり、興行に向かない作品は遠慮なくオクラ入りして才能ある監督に更なる奮起を促す、などの出来事には、映画理論家としての城戸の妥協なき理念性が現れてもいる。
城戸が映画製作においてその理念としているのは、「人間社会に起こる身近な出来事を通して、その中に人間の真実というものを直視すること」(本著P39)であり、また「いわゆる社会の常識を考え、社会的の思想なり判断、社会の大衆の分析やその判断に沿い、そうしてそれにマッチしながら、なおかつその人たちに感動を与える」(同P241)である、と述べている。
これがいわゆる蒲田調、大船調の底流ととなった理念である。
同時に松竹映画の、良くも悪くもこれが限界となって今に至るのではあるが、1956年、映画産業全盛期に書かれた本著では、それら理念の成果や反省がご本人によって述べられる時期ではなかったのが残念でもあり、一方で安心もする。

エリートで感受性に優れ、正義感もある城戸は、映画界の悪癖、因習を改革し、また戦中戦後にあっては映画界を代表して国家や権力側と交渉し、松竹のみならず、業界全体の利益と透明性のために尽力していることが本著から窺える。
監督や俳優に対する、愛情のこもった視線も本著の随所に表れている。
これらを見ると、映画製作者(日本版タイクーン)としての城戸の特性は、大映の永田雅一などに見られる、斬った貼ったの興行主としてのそれではなく、また東宝の経営者のように不動産をやりくりしながら財政をキープするスマートなものでもなく、映画青年の感受性を持ちつつ、新聞記者を目指した客観性を維持しながら、映画製作者という極めてヤクザな職務を全う(しようと)した点にあるのではないかと思う。

(余談)
本著には、1929年(昭和3年)、ソビエトからヨーロッパ、アメリカへと9か月にわたる洋行の著述がある(本著P57~71)。
ソビエトでエイゼンシュテインやプドフキンと面談し、モンタージュ論を議論し、城戸の持論を述べたこと。
また持参の「からくり娘」を見せたが、「長い」といわれたことに触れている。
城戸がその際思ったのは、日本人が出ていること自体、彼らの想像と理解から離れ、それをして彼らに「この映画は長い」と言わしめたのだ、彼らに興味を持たせるにはすでに彼らの日本に対する常識となっている、時代劇的なものでなければだめだ、ということだった。
さらに興味深いのはハリウッドで製作者、B・P・シュルバーグに会っていること。
B・Pは大著「ハリウッドメモワール」を書いたバッド・シュルバーグの父親。
城戸は試写室に招かれ、B・Pが監督とデスカッションをしている場面を見て、ハリウッドの生存競争がいかに激しいかと感じる。
晩さん会ではノーマ・シアラー、グレタ・ガルボ、駆け出しのゲーリー・クーパーらと会食をしており、VIP待遇だったことをうかがわせる(ガルボが出てきたということは、B・Pがルイス・B・メイヤーのもとで製作をしていた頃であったのか)。

城戸はトーキーシステムの事前調査も行っており、彼なりにあたりをつけて帰ってきており、帰朝後はさっそく日本でのトーキー映画の研究をスタートさせる。
当時はサイレント時代の末期で映画界が下り坂だったらしく、ホテルに投宿する城戸らに、ハリウッド女優のあっせんがあったそうである。
値段を聞くと一晩10ドルといわれたとのこと。
映画界の実情を表す記録として貴重な記述でもある。
