上田映劇は、大正6年開業の上田劇場をルーツとする映画館。
現在はNPO法人が運営するミニシアターとなっている。
映画好きの山小屋おじさんとしては、上映情報のチェックが欠かせない。
上映作品は、いわゆる内外のミニシアター系の新作が中心だが、時に「フィルム上映大会」として寺山修司の「田園に死す」などを取り上げたり、地元上田出身の映画監督・成沢昌茂の追悼上映として、「花札渡世」など4作品を上映するなどの企画にも取り組む。
今回はロベール・ブレッソンというフランスの映画監督の旧作「たぶん悪魔が」(1977年)が上映されたので駆け付けた。

この日の上映開始は16時20分。
14時半ころまで畑で苗の植付作業などを行い上田を目指す。
上映開始までに近くの商店街で今川焼のあんことクリームを購入、上田映劇に併設しているカフェでコーヒーテイクアウトしてから場内へ。
いつものように広々とした場内。
観客は自分を入れて5人ほど。
まるで大スクリーンを個人で独占しているかのような鑑賞条件に感謝、満足。

ロベール・ブレッソンは映画史上で評価が定まった巨匠だが、山小舎おじさん的には、リアルタイムで見た「白夜」(1971年)という作品が唯一の鑑賞体験。
ここ最近になって、「少女ムシェット」(1967年)、「やさしい女」(1969年)などがデジタル素材で再輸入されてミニシアターなどで上映されており、本作「たぶん悪魔が」と「湖のランスロ」(1974年)も同様にデジタル素材での輸入公開(日本では初公開)となったもの。
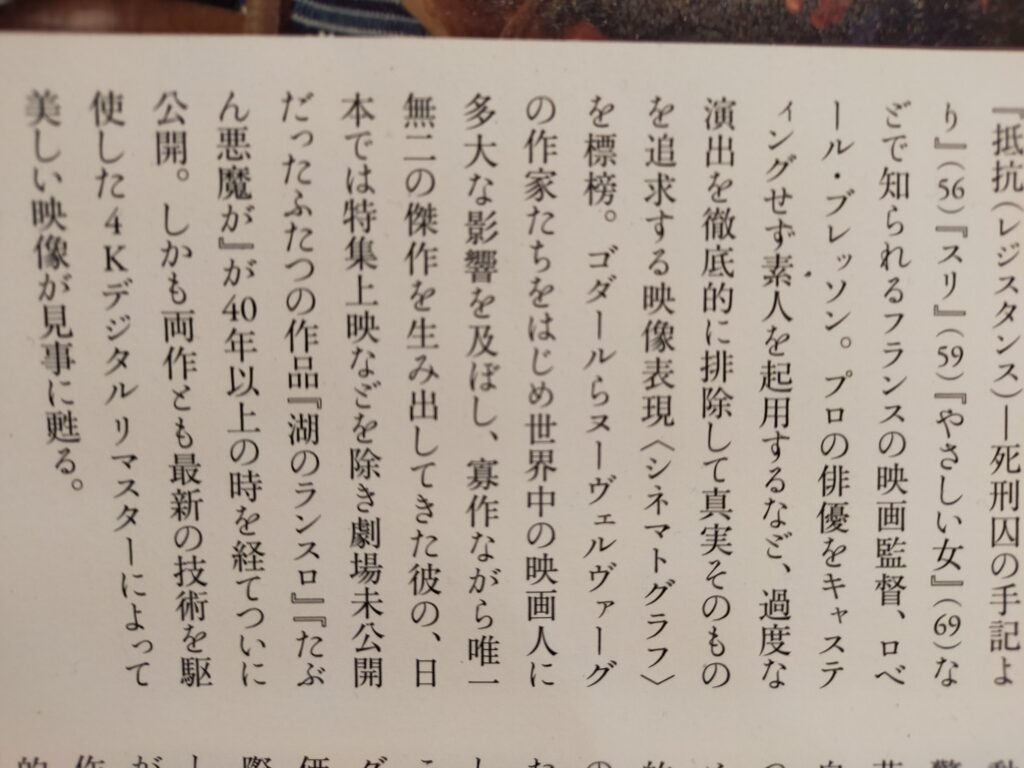
今川焼を食べ、コーヒーを飲みながら(上田映劇は場内での飲食可能)ほぼ初めてのブレッソン作品を見た山小舎おじさん。
芸術作品にありがちな、観念的、象徴的、形而上的な映画なのかと思っていました。
もしそうだったら無理して理解しようとはせず、画面のあるがままを受け入れ、力を抜いて見ていようと思いました。
退屈しないか、だけが心配でした。

心配は当たりませんでした。
登場人物は他のブレッソン作品同様、職業俳優ではないようでしたが、静謐で知的な美男美女でそれだけで画面が締まります。
素人俳優の演技は個性を排した動きで、まるで小津作品における俳優たちのセリフ回しのようですが、それが映画そのものをスポイルするということはありませんでした。

ストーリーは、1970年代のパリの学生である青年が、あらゆる事象に救いを得ることができず、自殺するといいものです。
政治運動、宗教、ヒッピー、麻薬、恋愛、学問などの事象が出てきますがそれらは青年の救いにはなりません。
反対に当時の環境汚染などの映像が青年の絶望の象徴としてカットインされます。
映画を貫くテーマは、ブレッソン監督の感性〈そのもの〉です。
もっというと、ブレッソンの感性〈それだけ〉です。
俳優に自由な演技を許さず、むしろロボット的な動きを求めるなど、ブレッソンの感性を逸脱する動きを排した映像が続く作品です。
そういった作品が緊張感を維持し、退屈ではないのは、ブレッソンの感性の完成度が高く、また普遍性を持っているからだと思います。
映画作家には、〈この作品を撮らなければ前へ進めない〉と思って作った作品があるように思います。
それは大島渚の「日本の夜と霧」(1960年)だったり、ビリー・ワイルダーの「異国の出来事」(1946年)だったりします。
両作品に共通するのは興行的にヒットしなかったこと(「異国の出来事」は日本に輸入すらされなかった)。
作家の個人的感慨を唯一のテーマにしたり、濃厚に反映させた作品の宿命でもありましょう。
おそらくはブレッソンのフィルモグラフイーはほとんど全部が、ほかのだれかが企画したものではなく、ブレッソン自身が〈この作品を撮らなければ前へ進めない〉と思って撮った作品なのではないでしょうか。
その結果が、興行成績はともかく、各作品が映画祭等で受賞し、現在に至るまでファンを獲得しているところがロベール・ブレッソンのすごいところだと思います。

