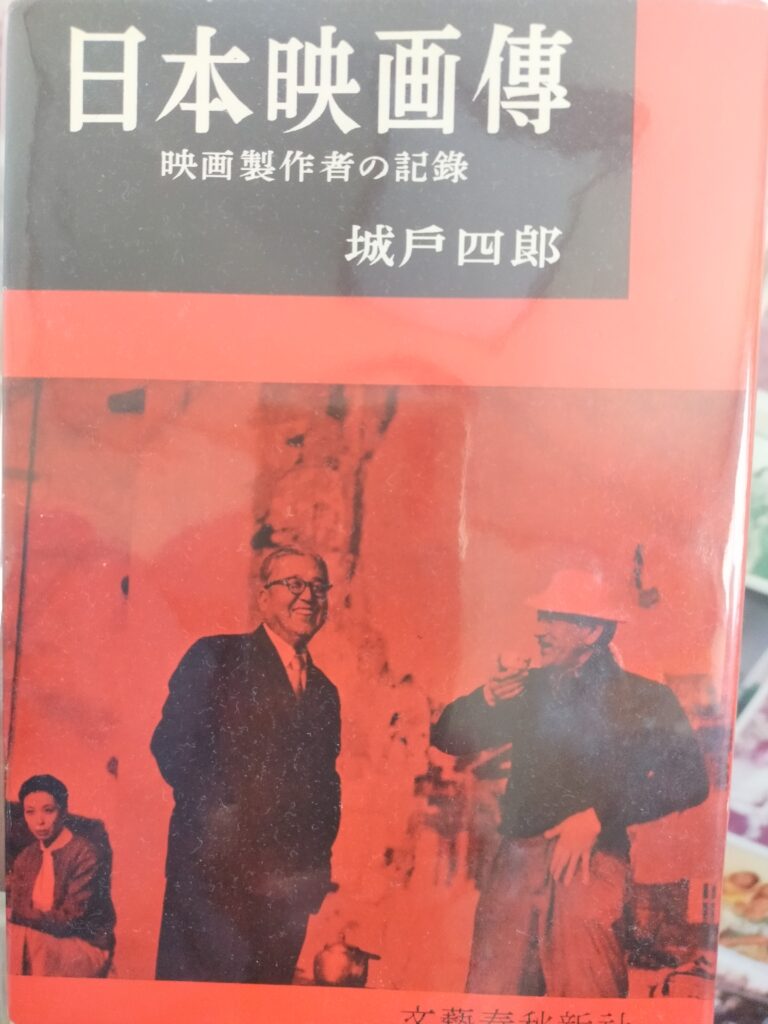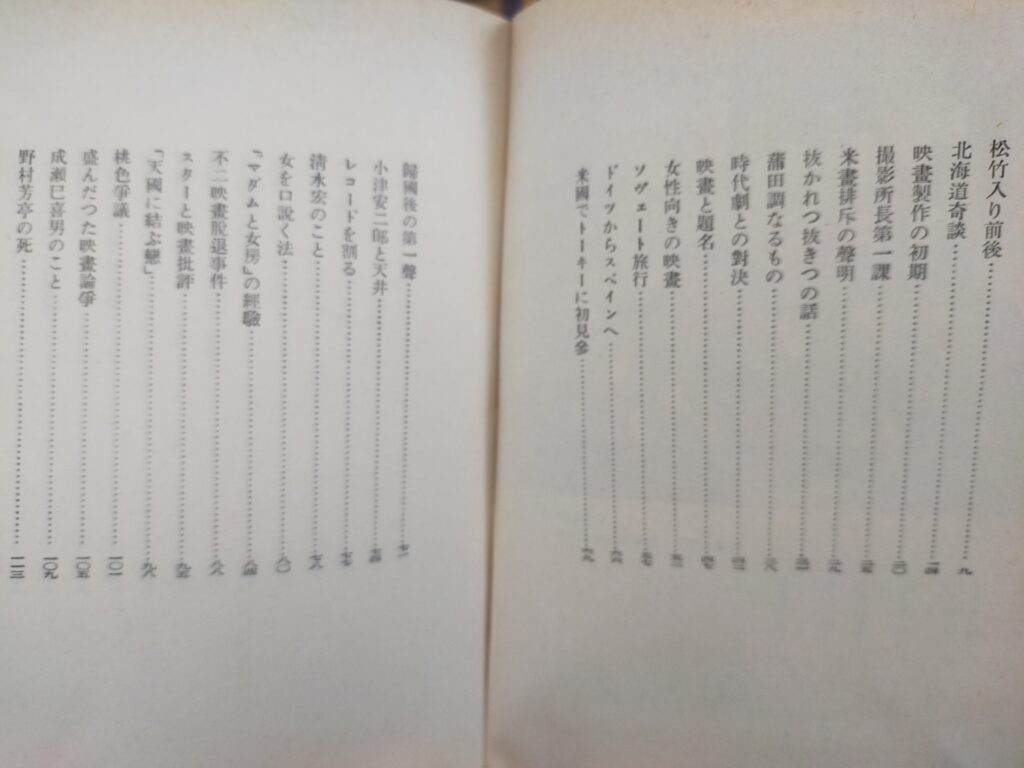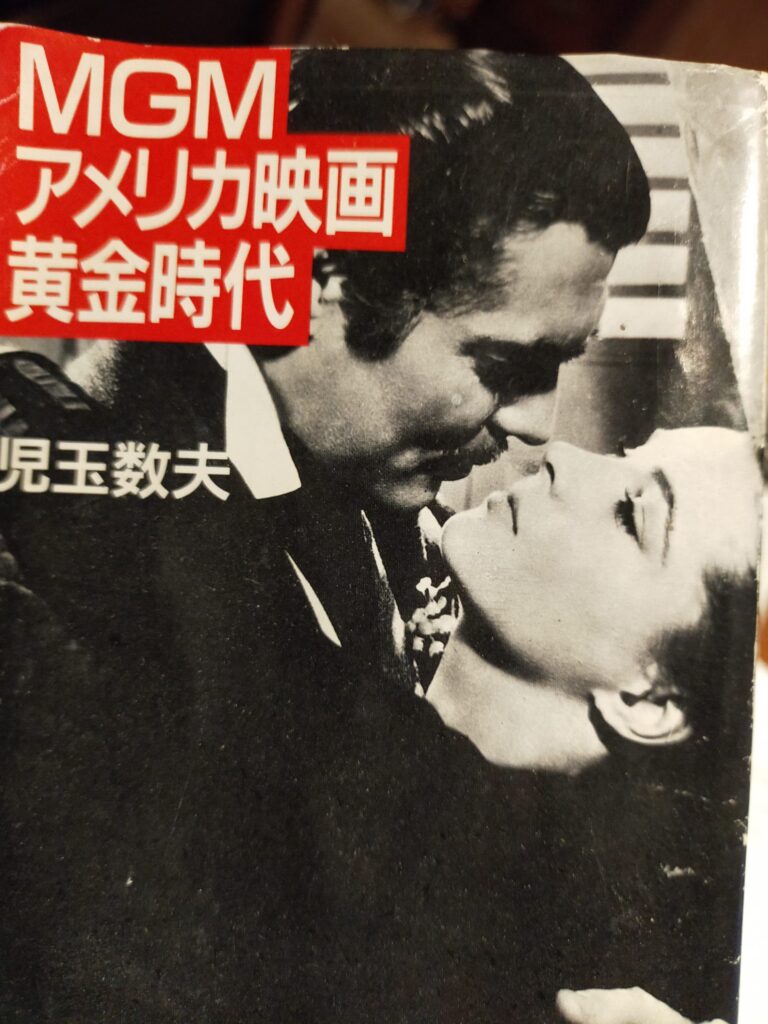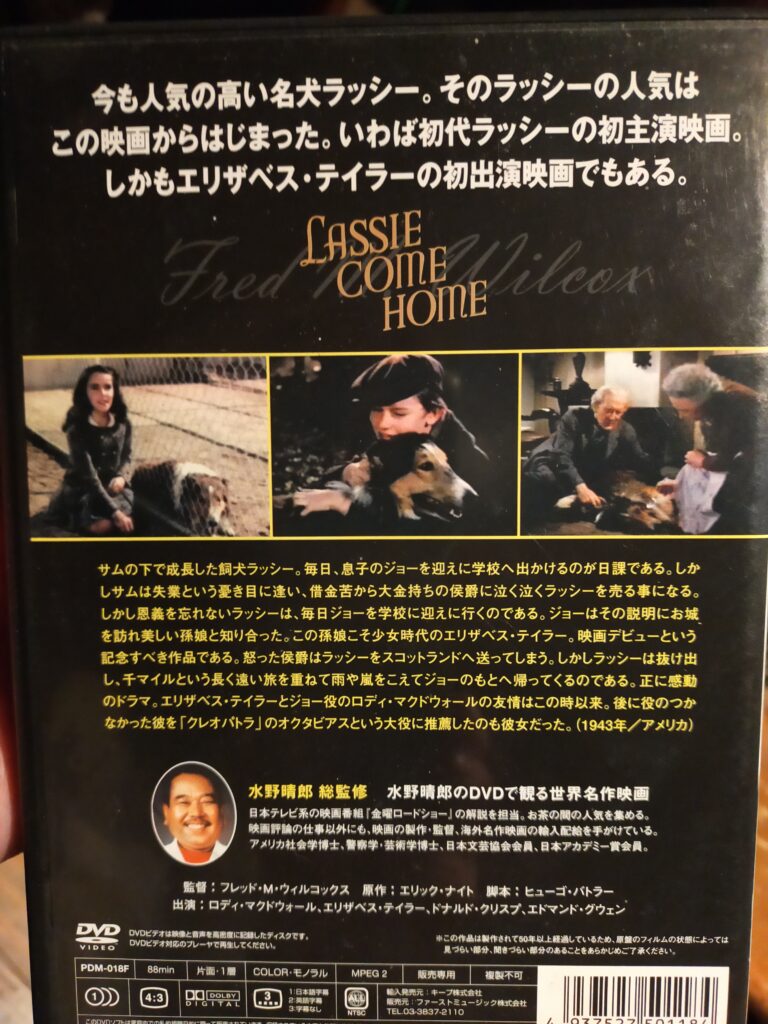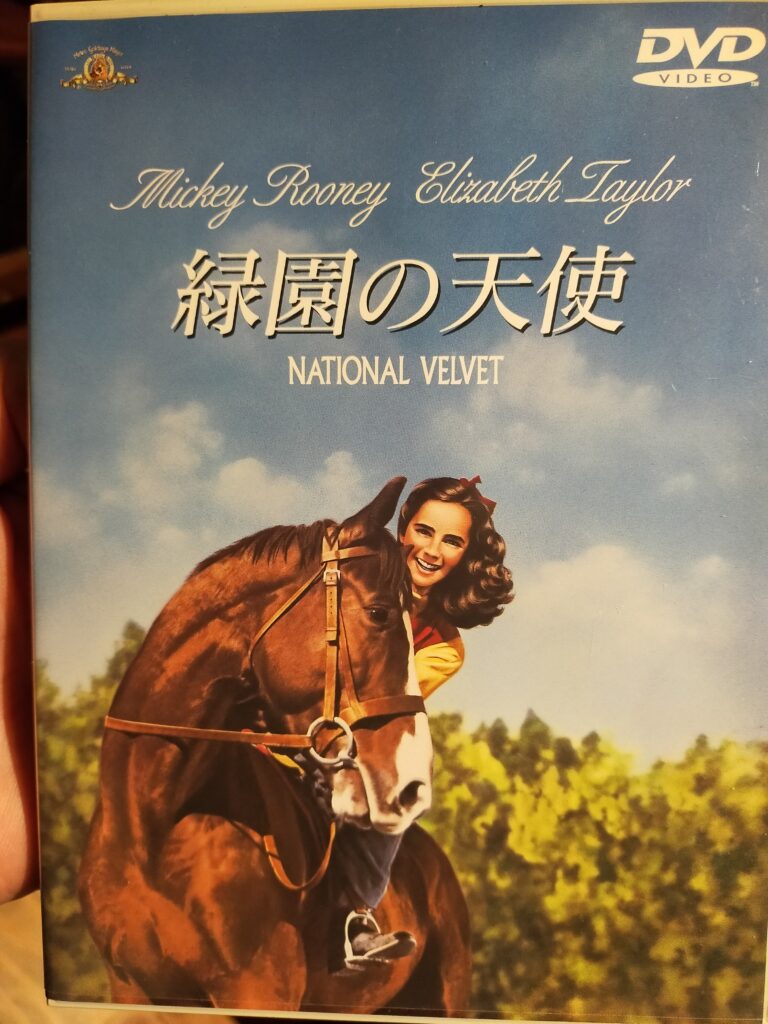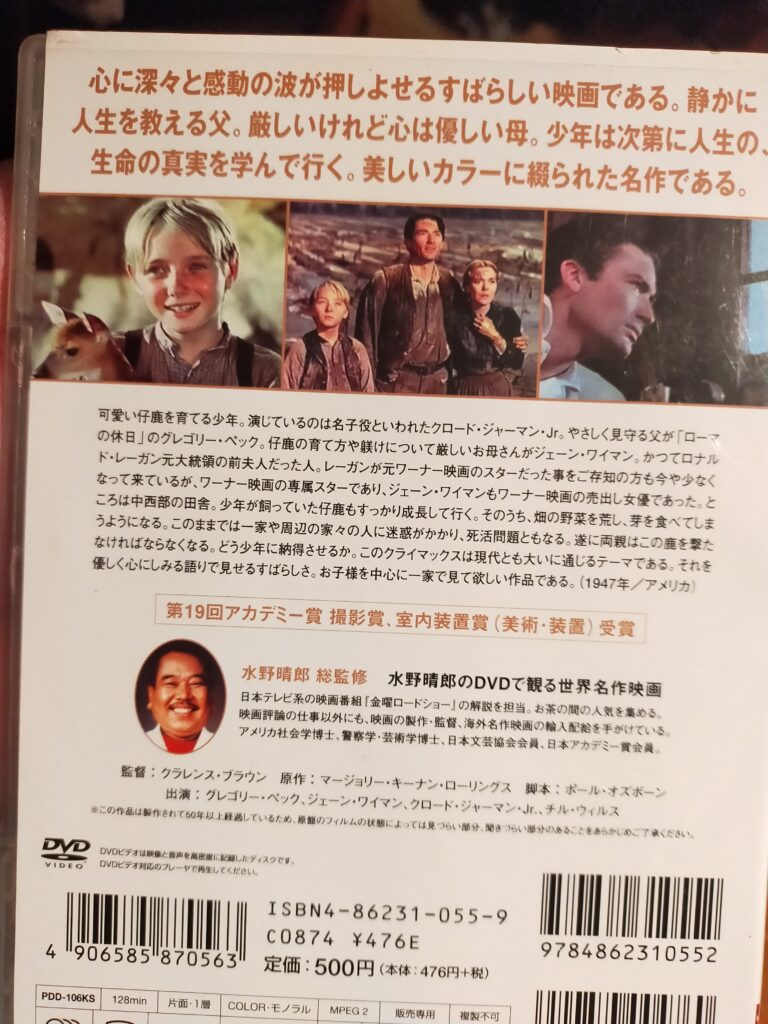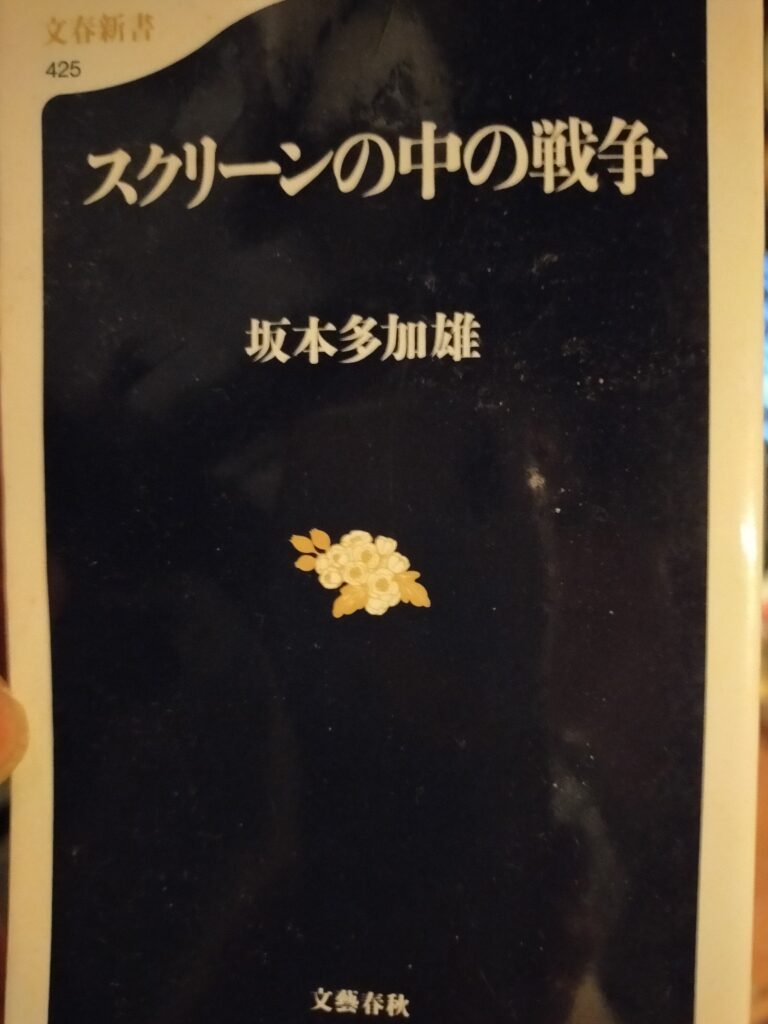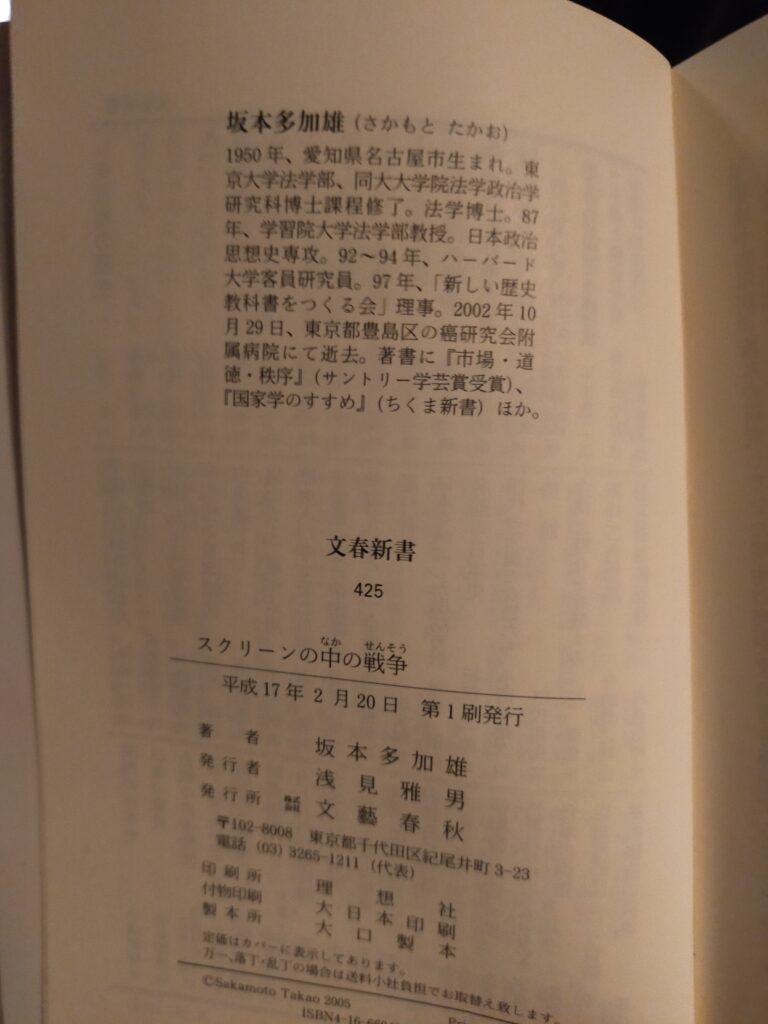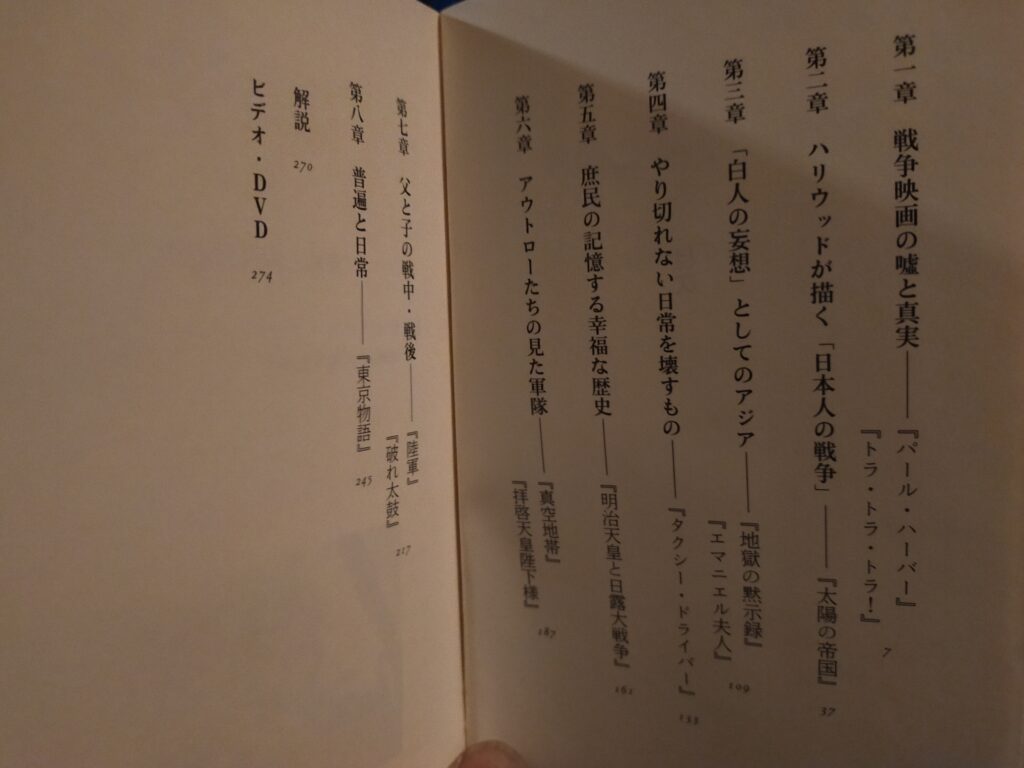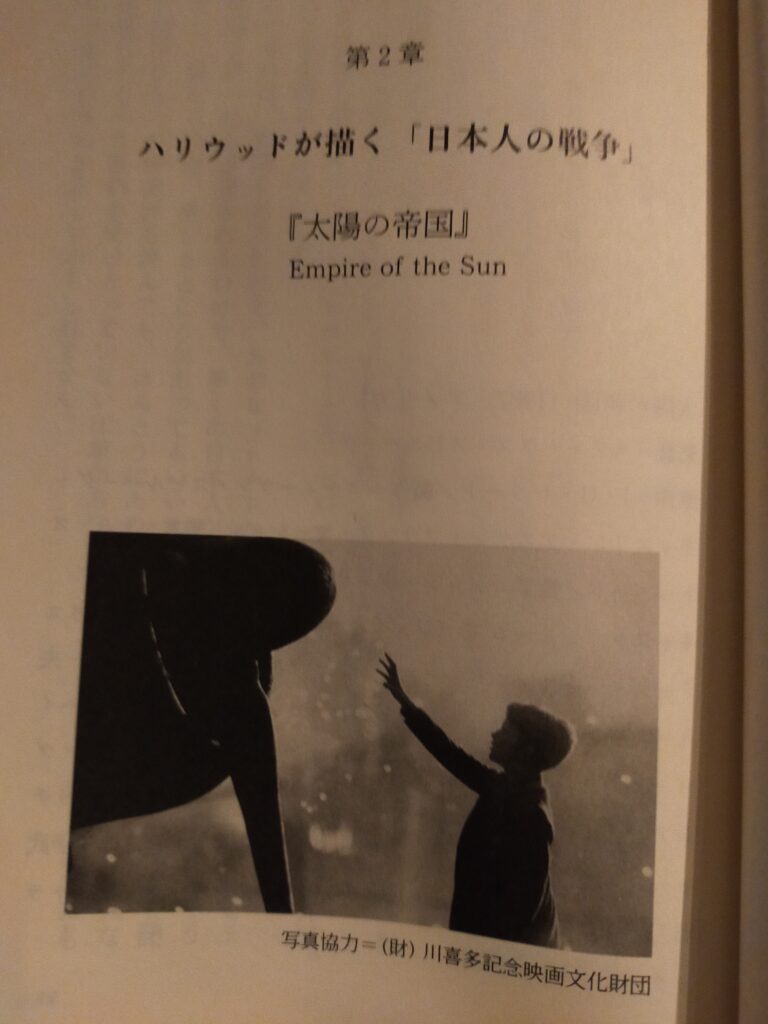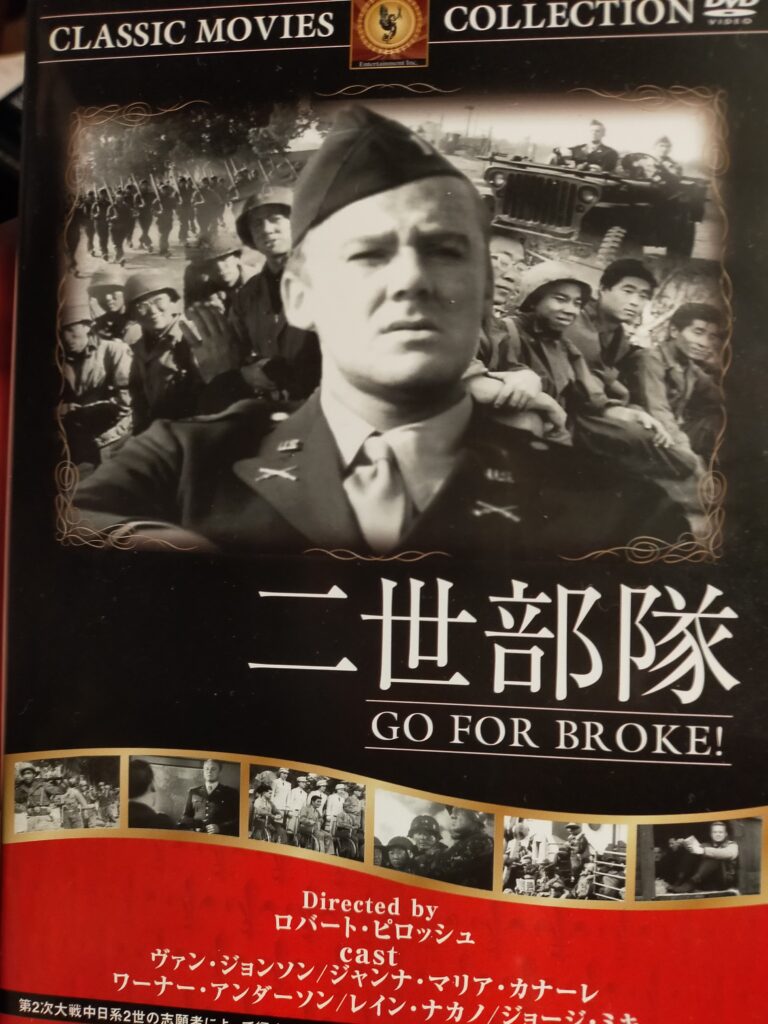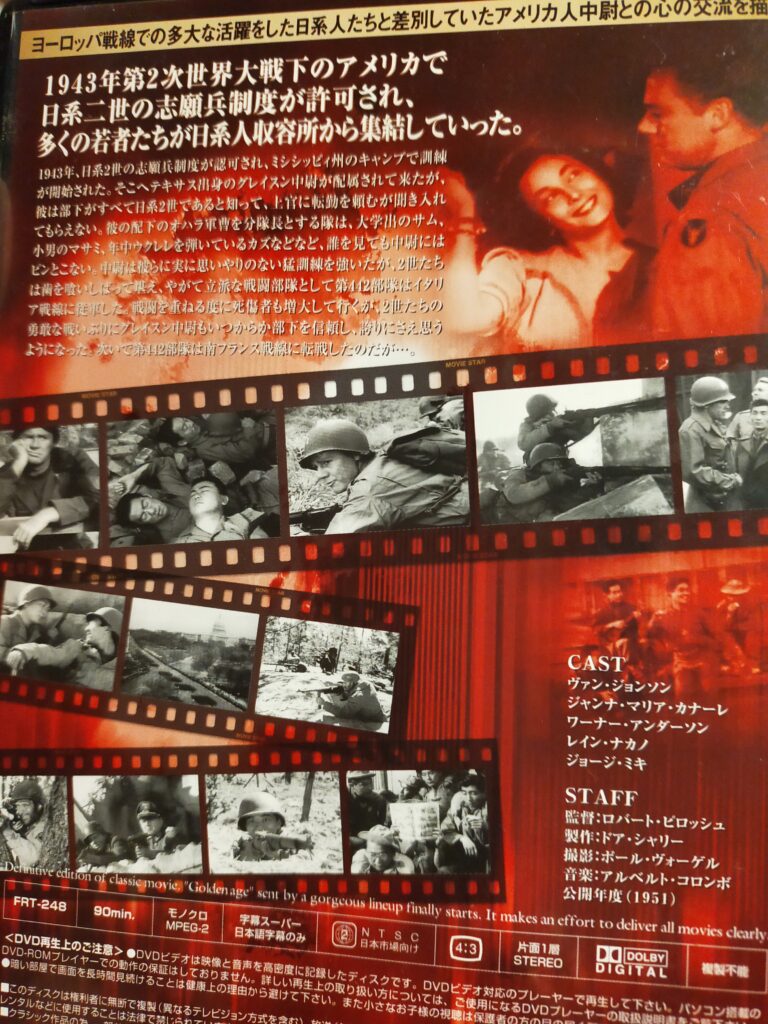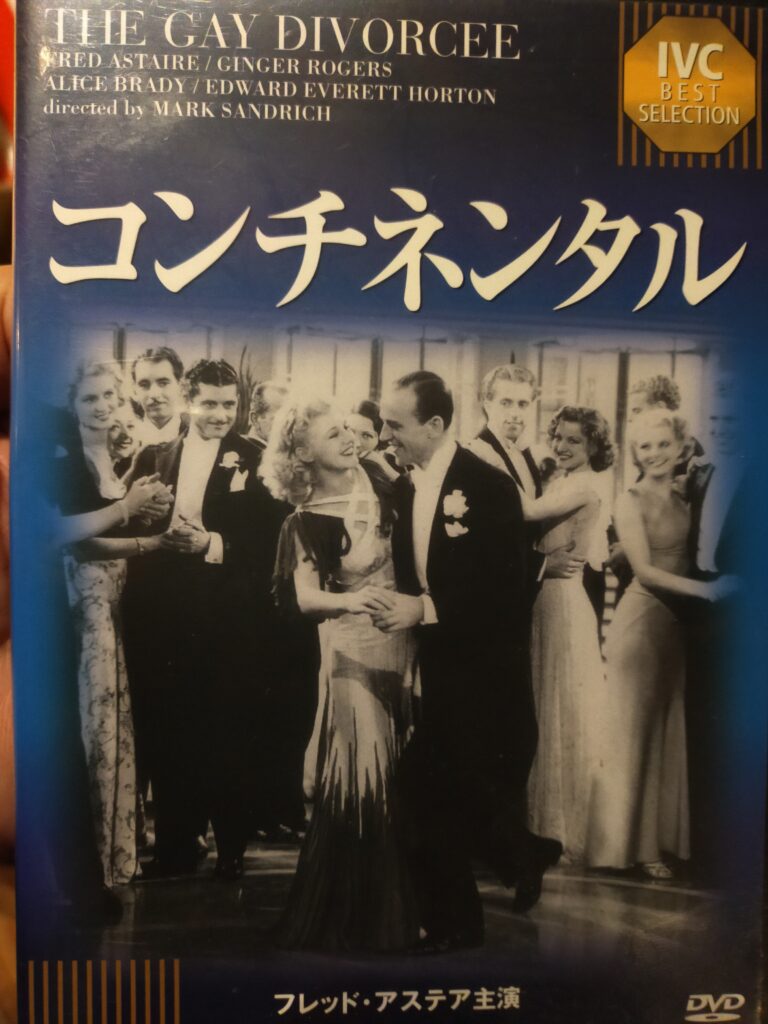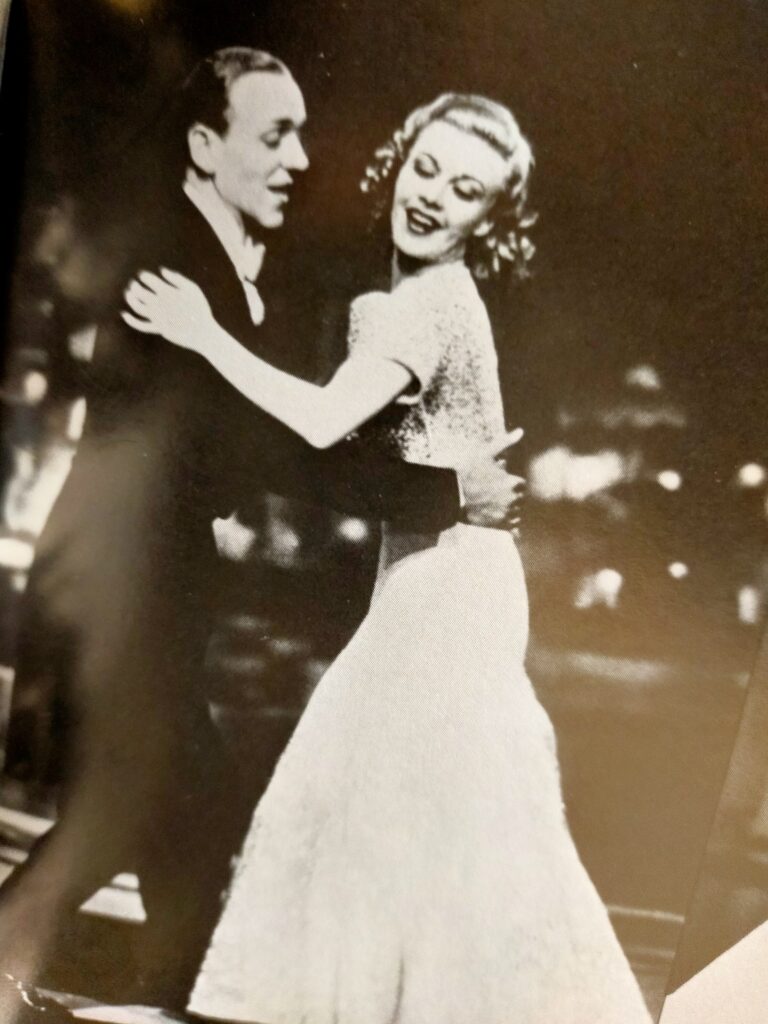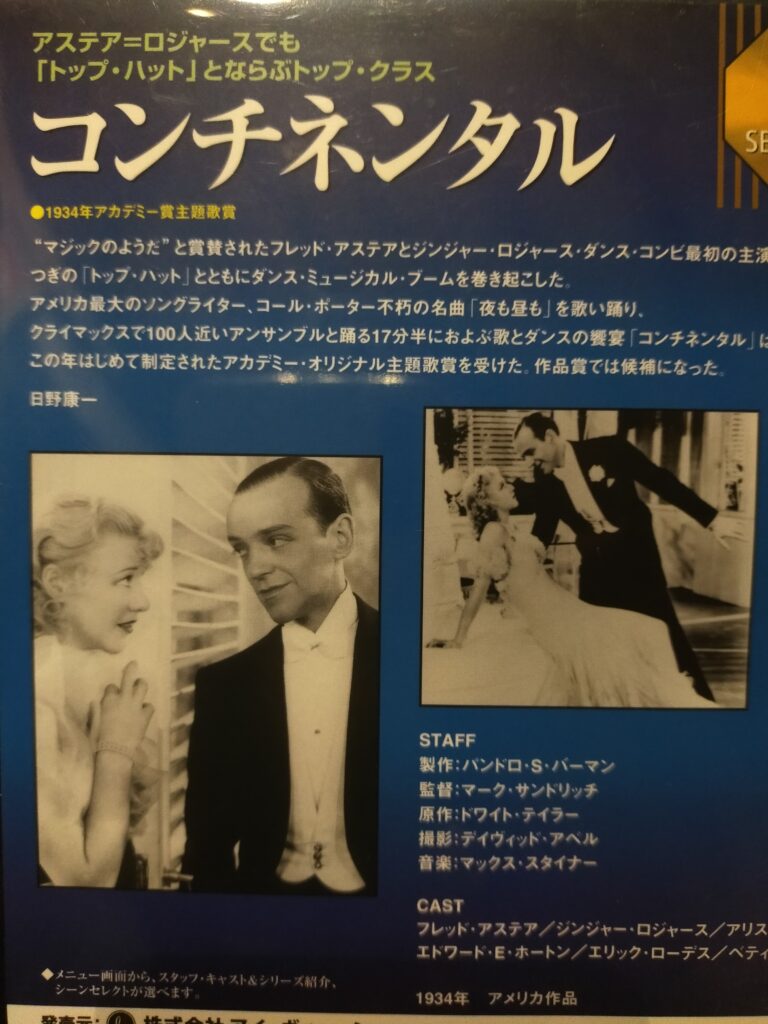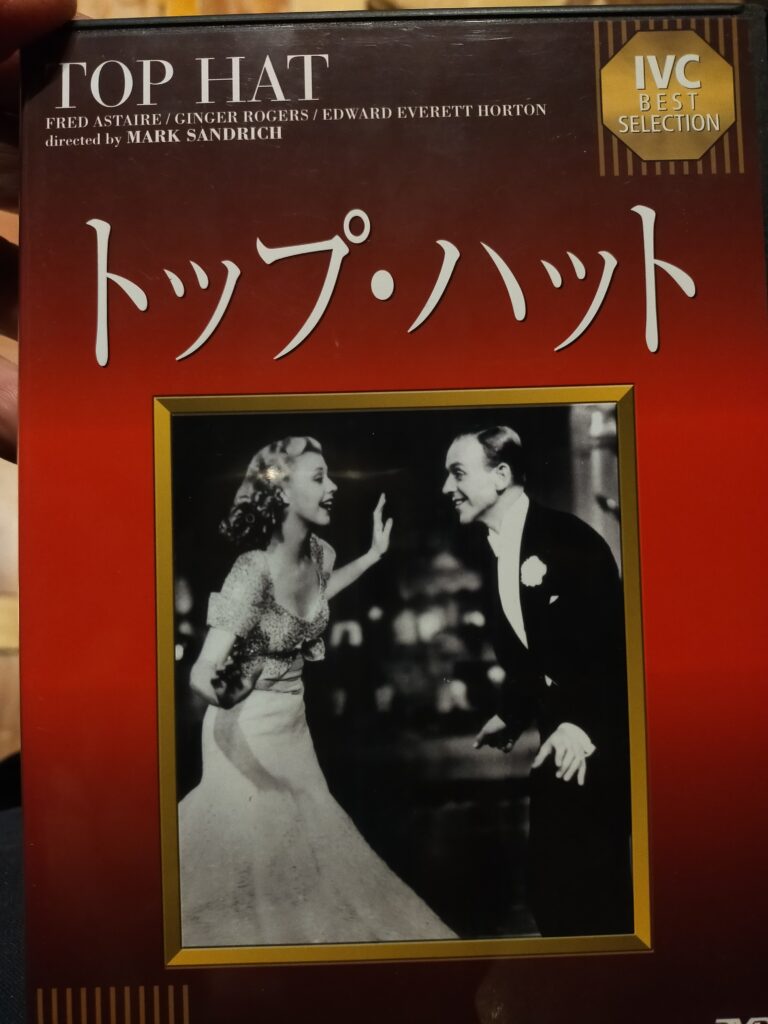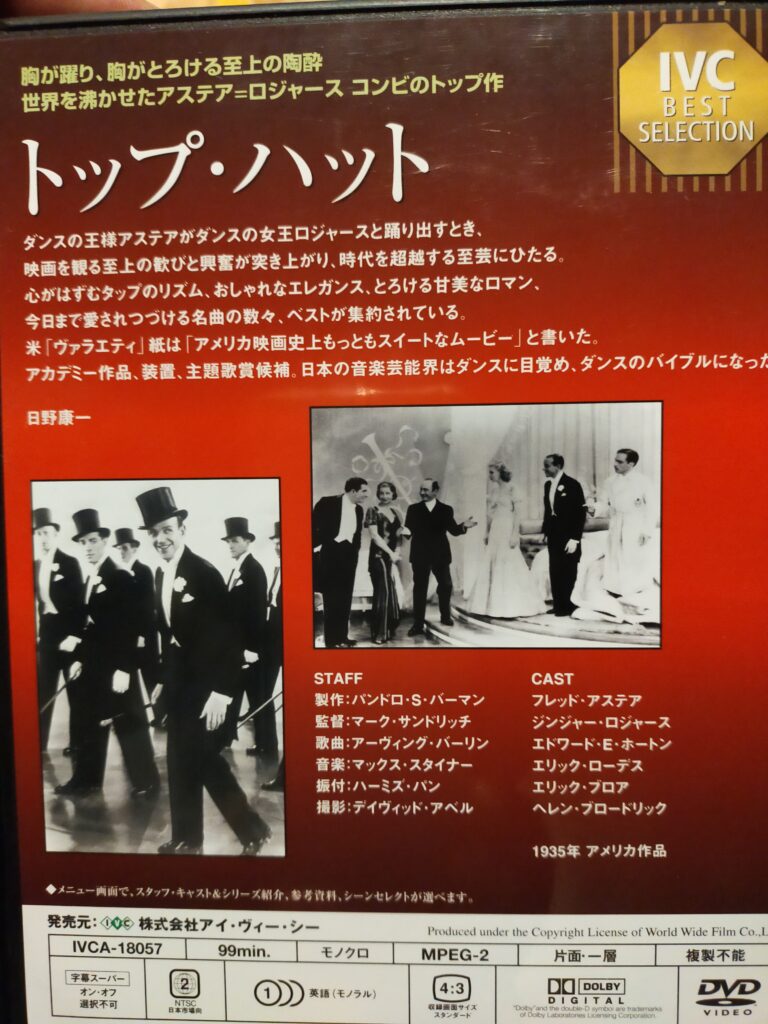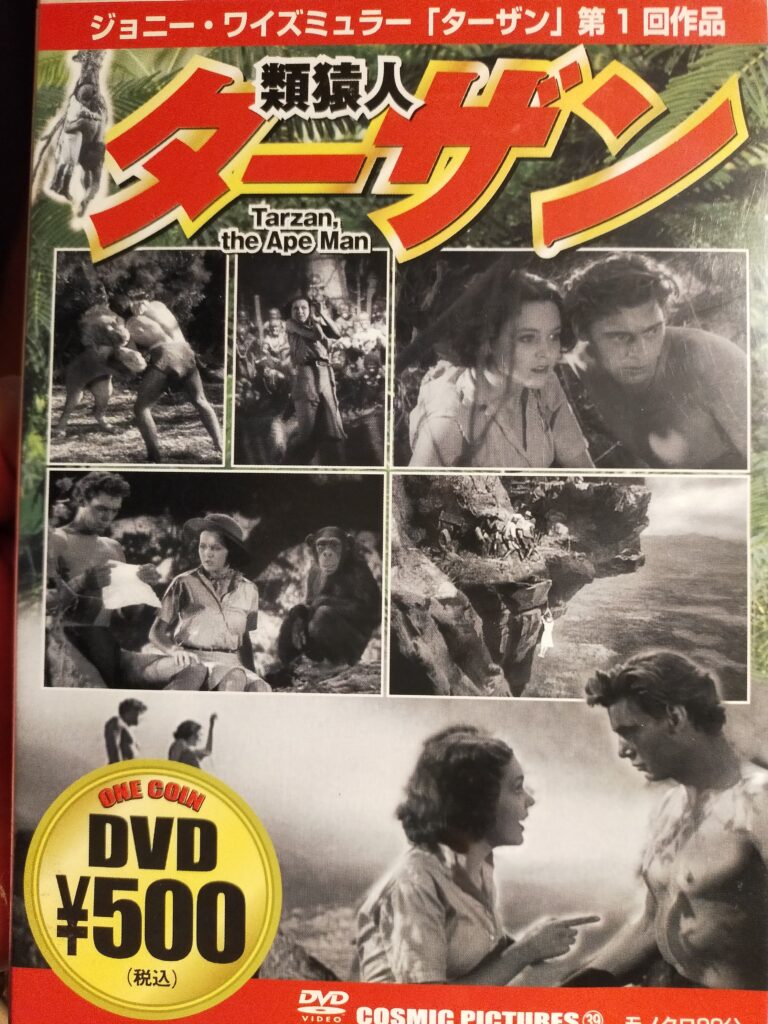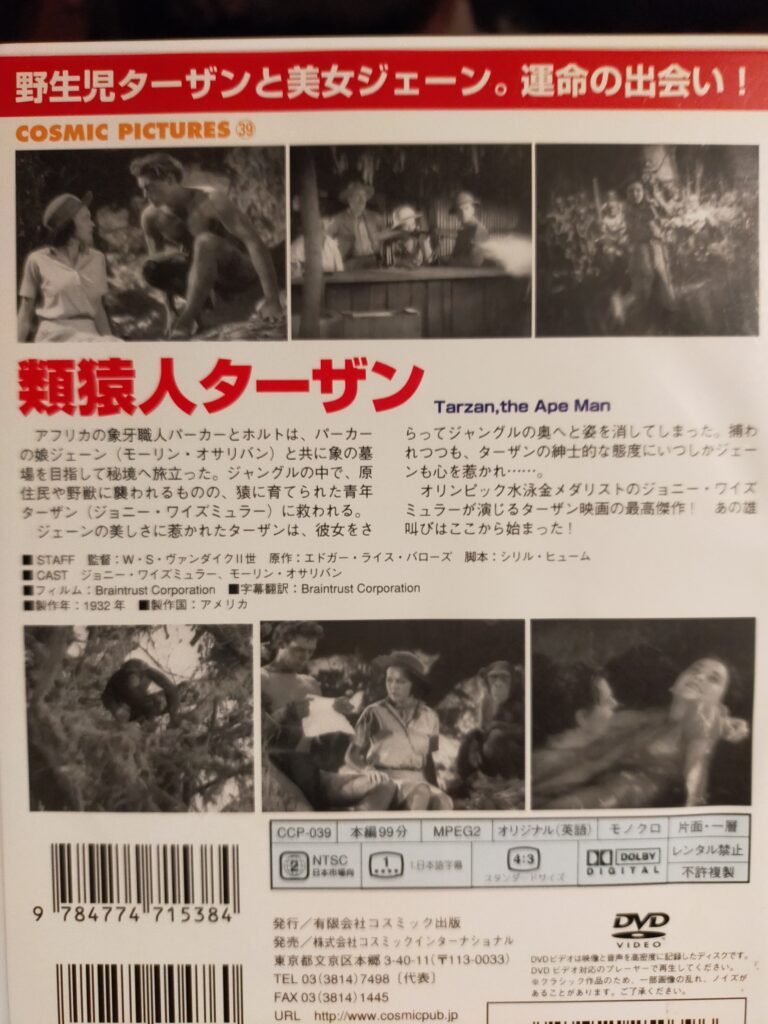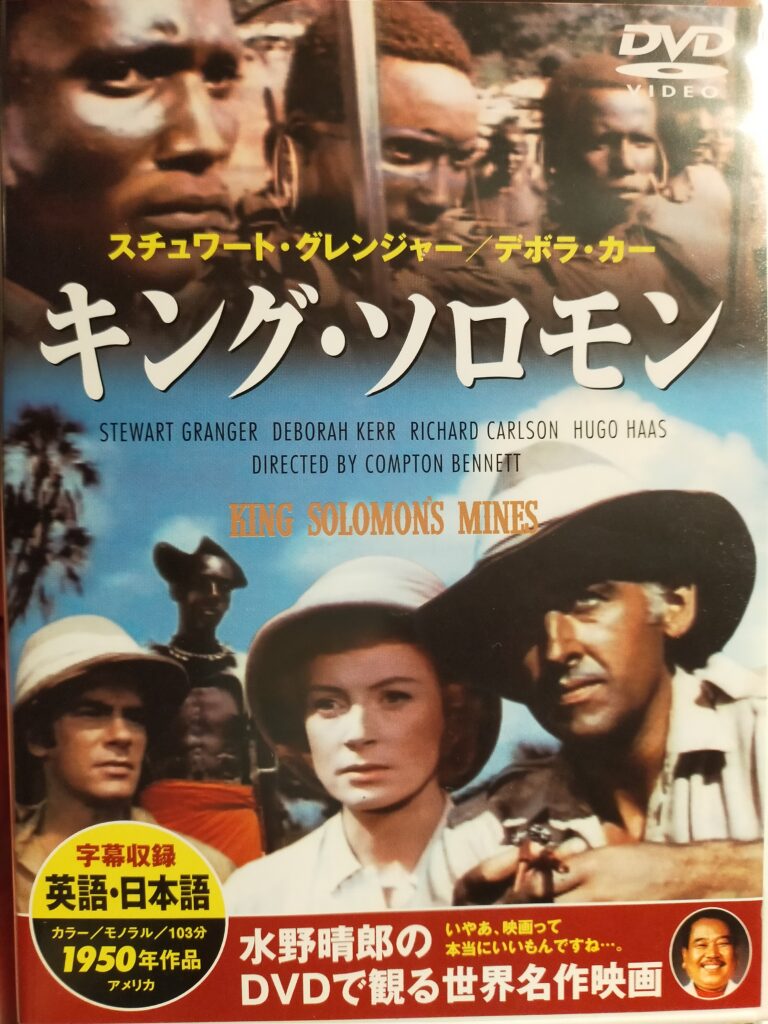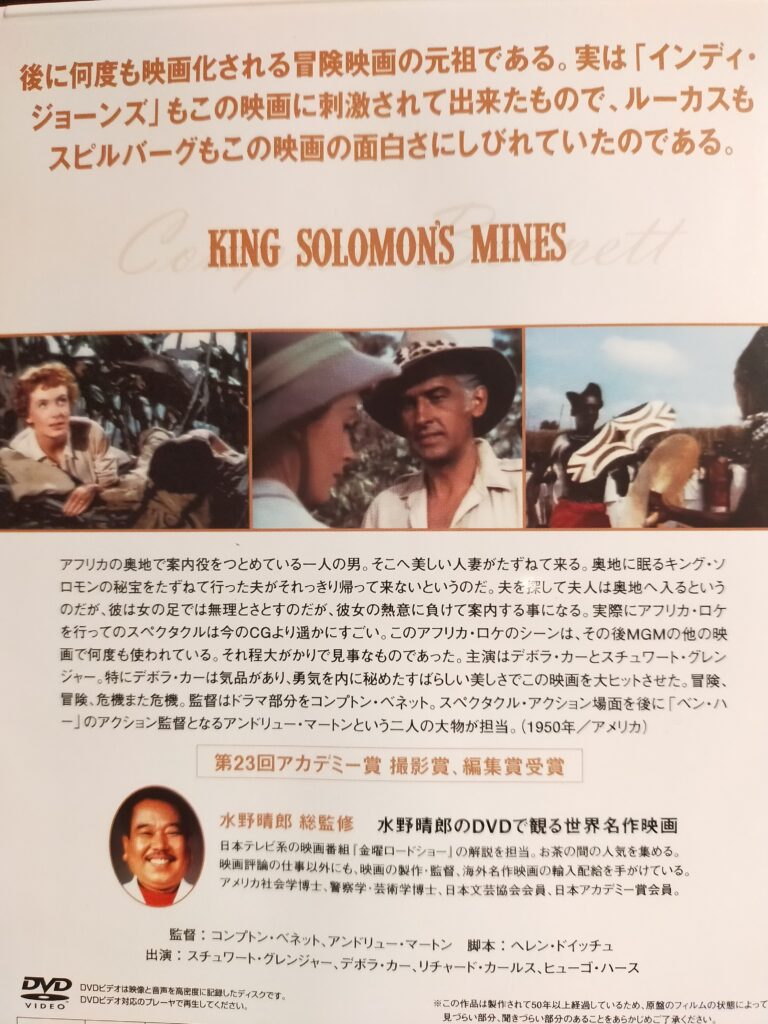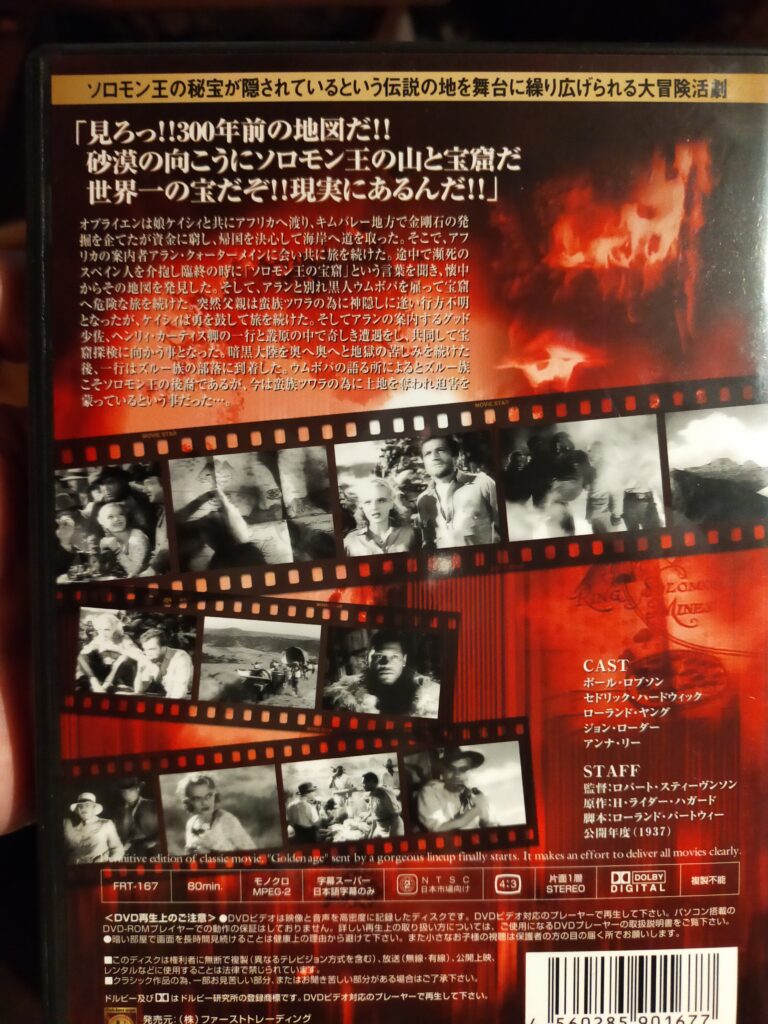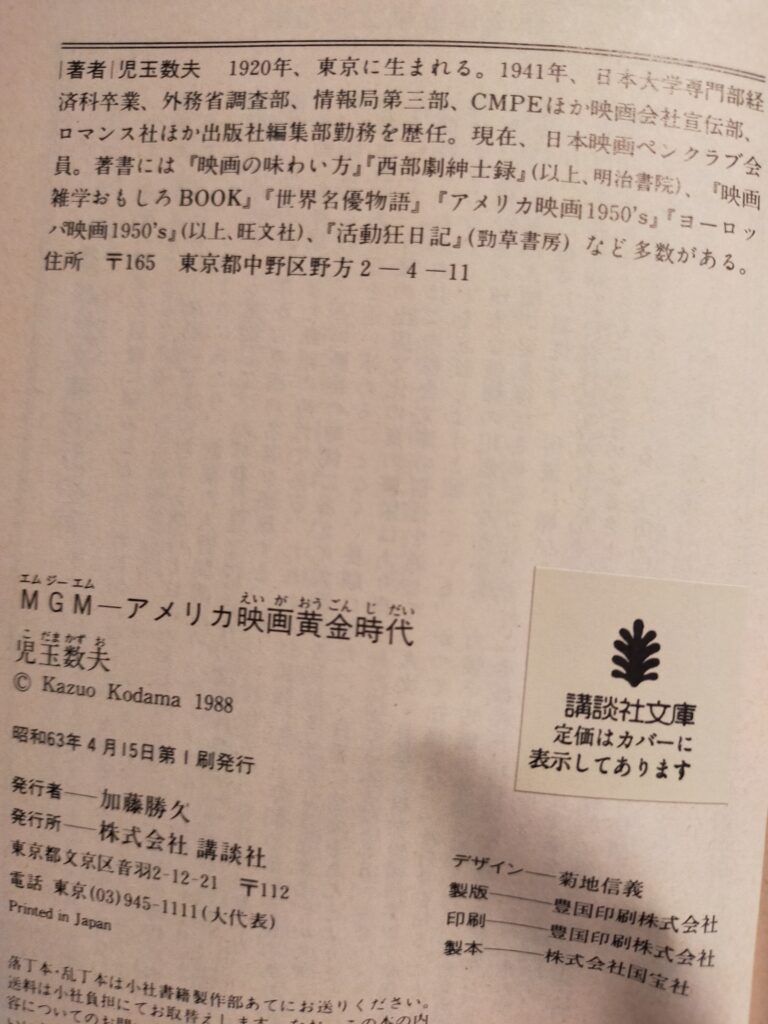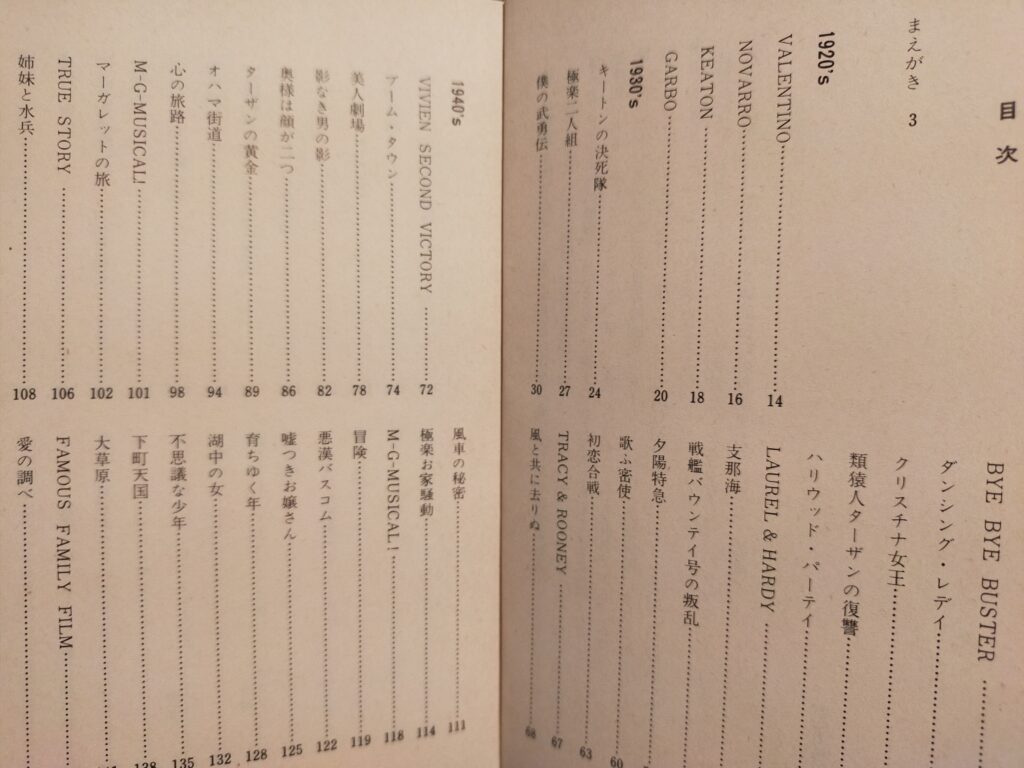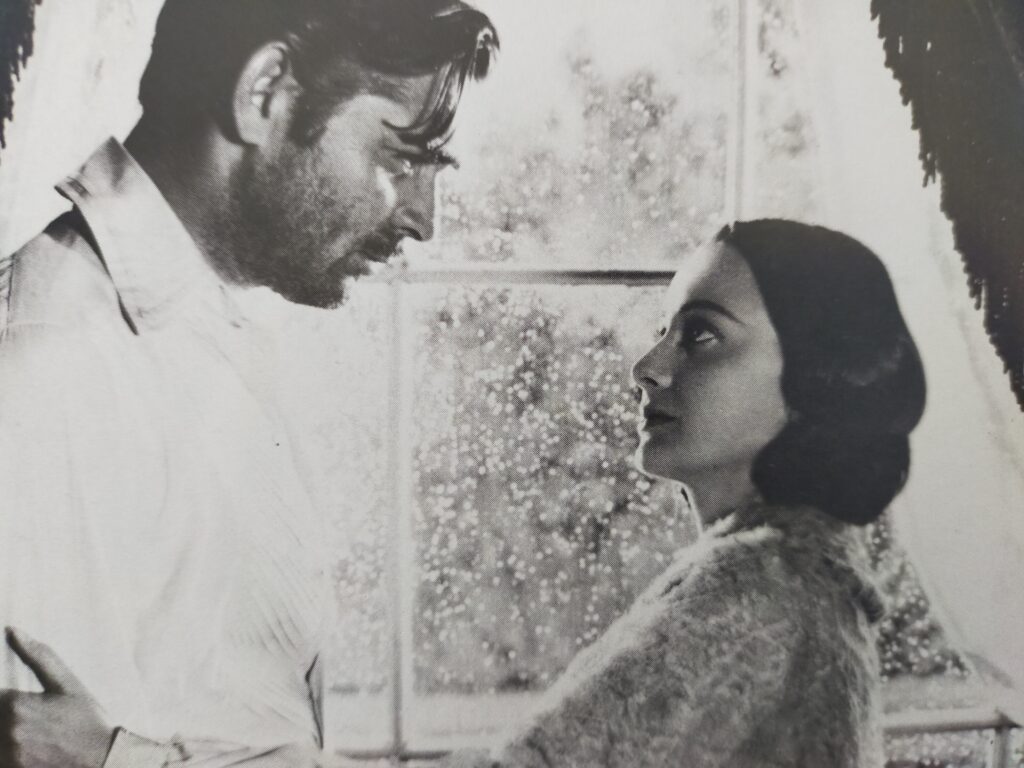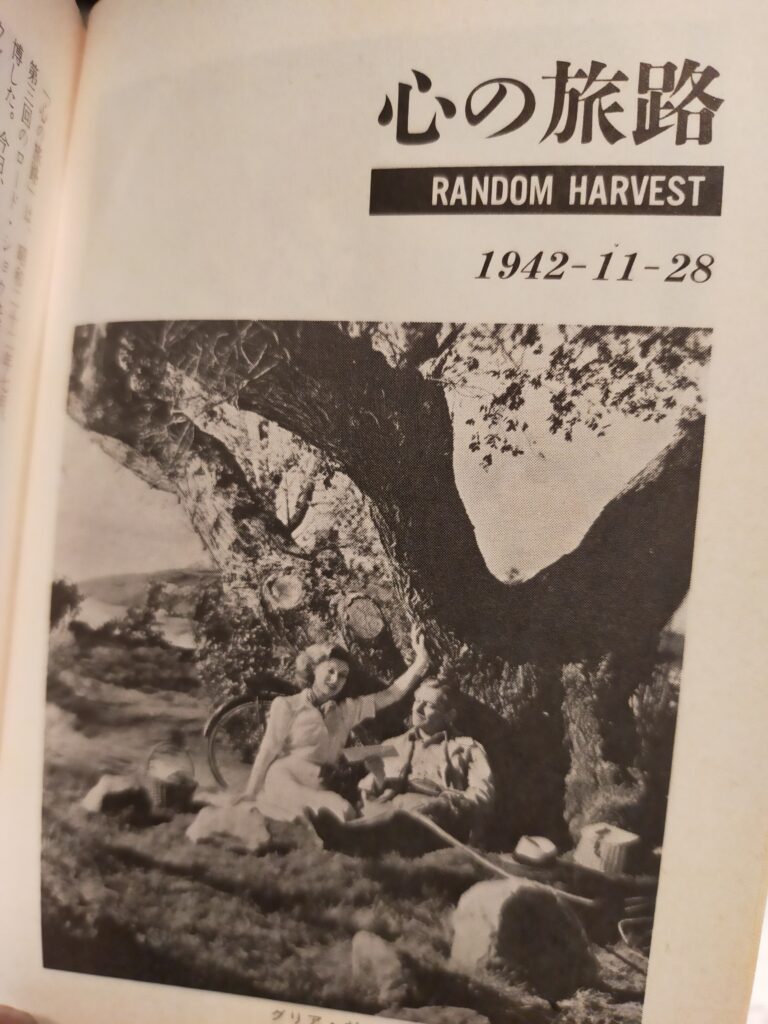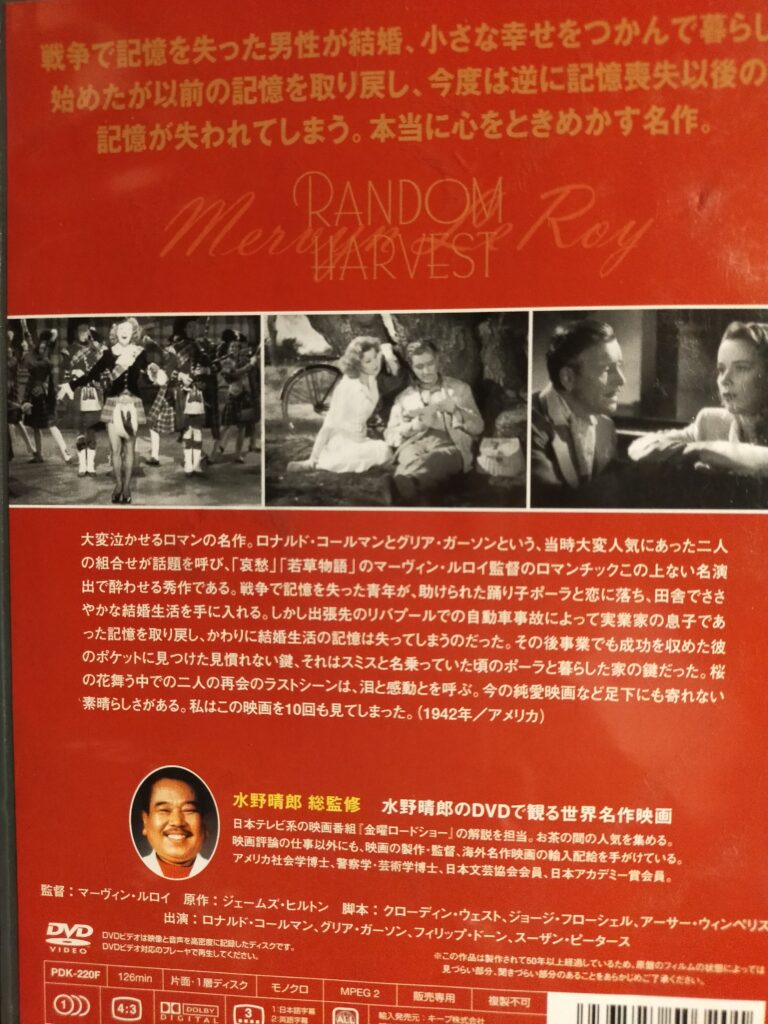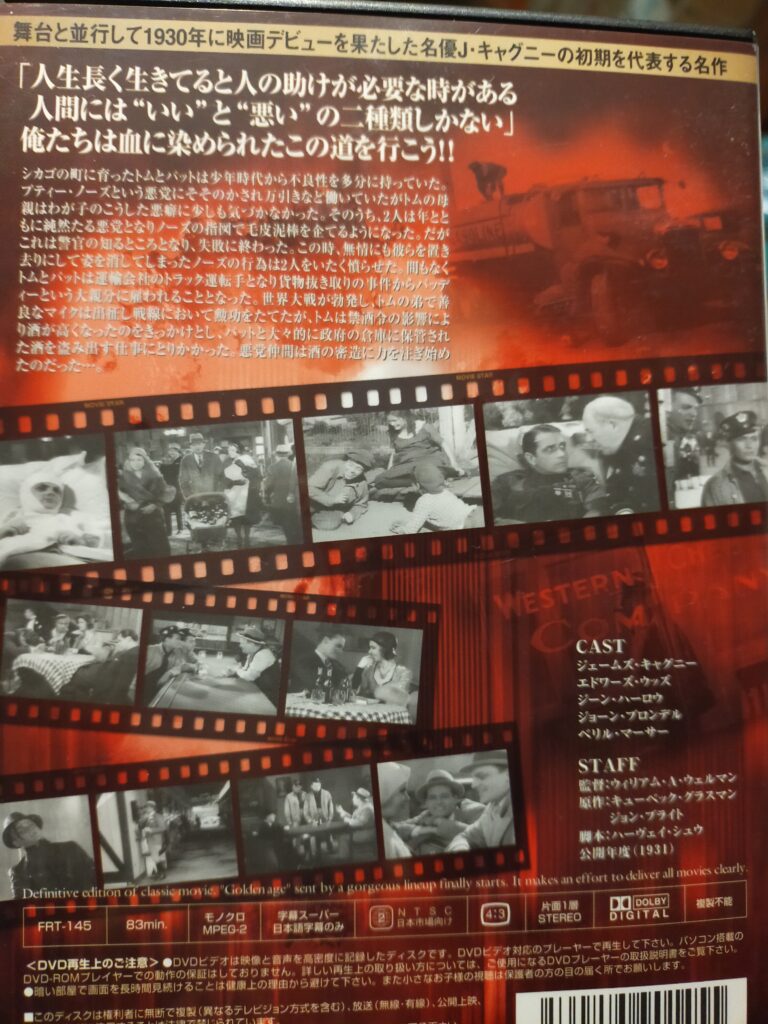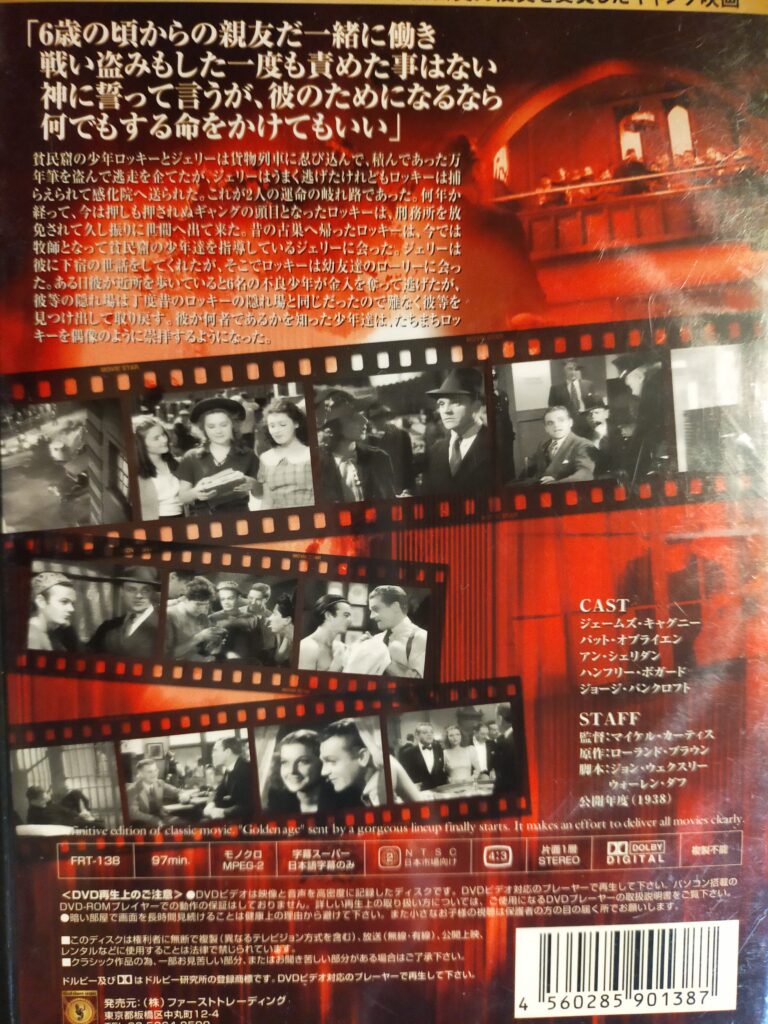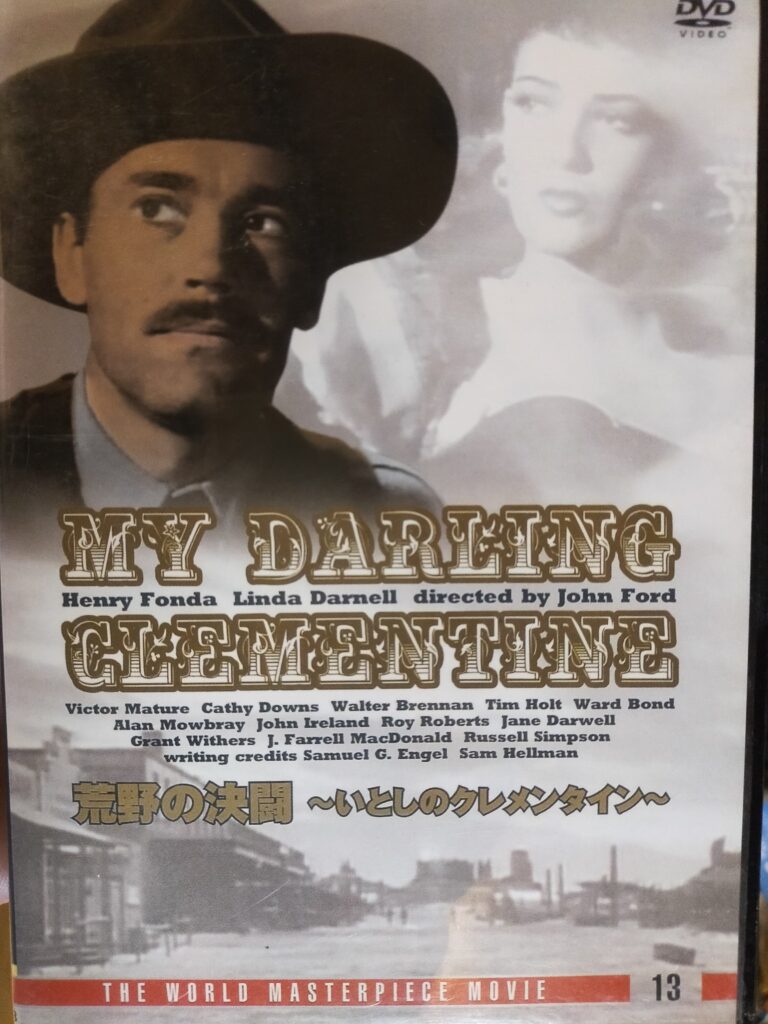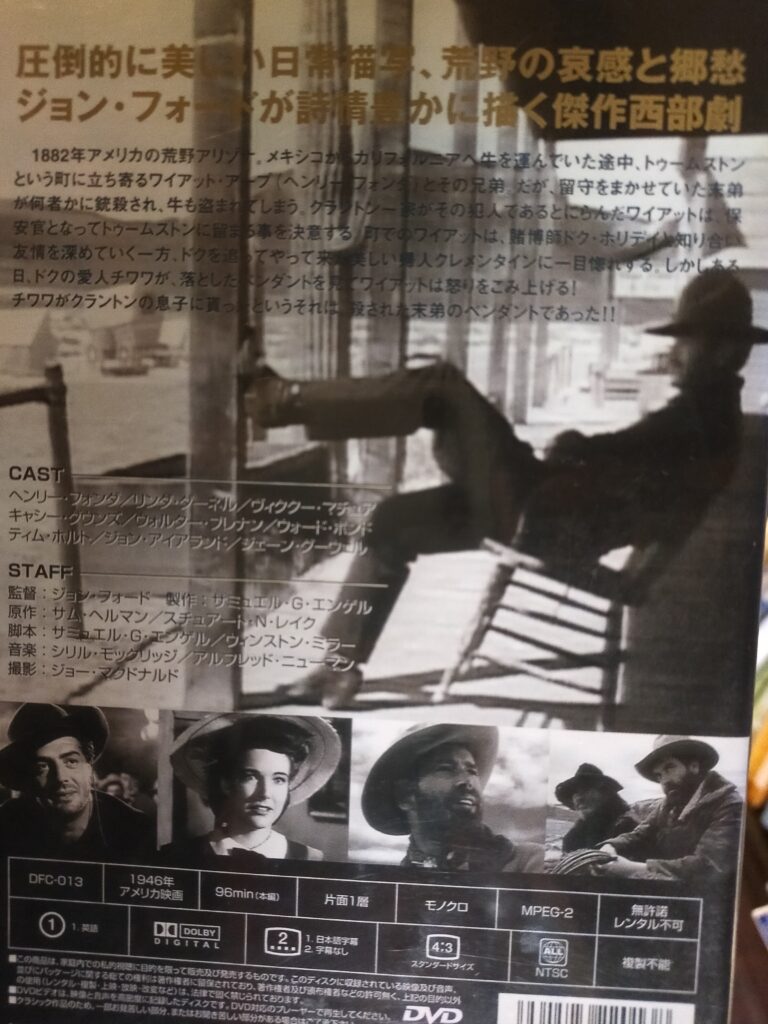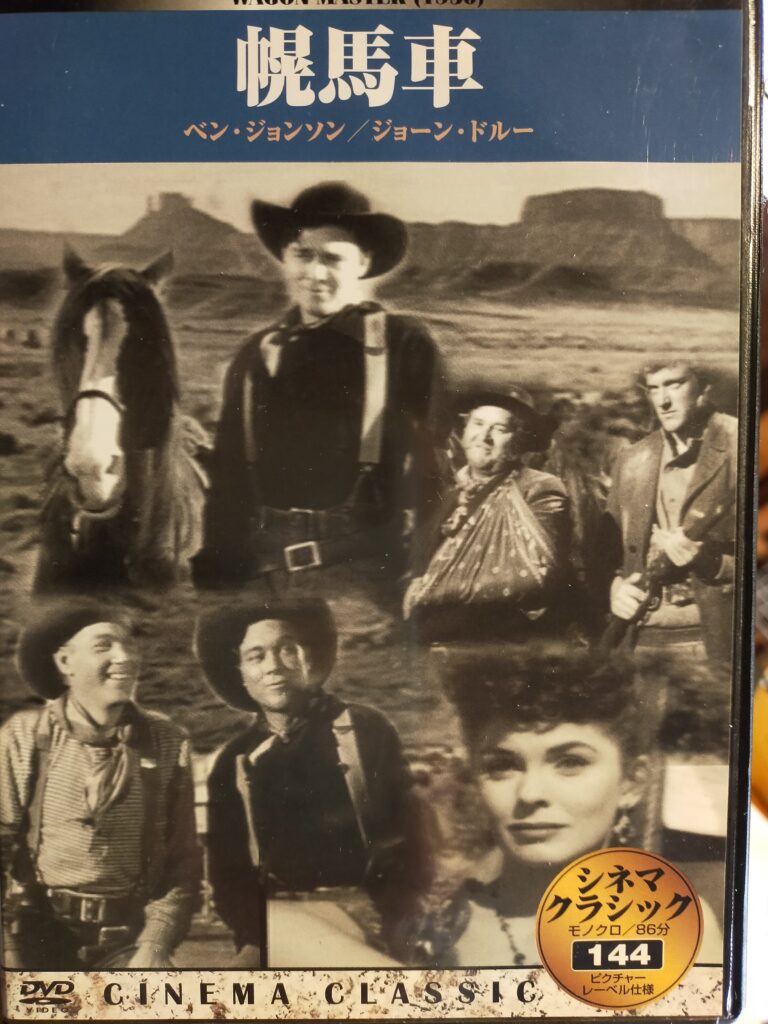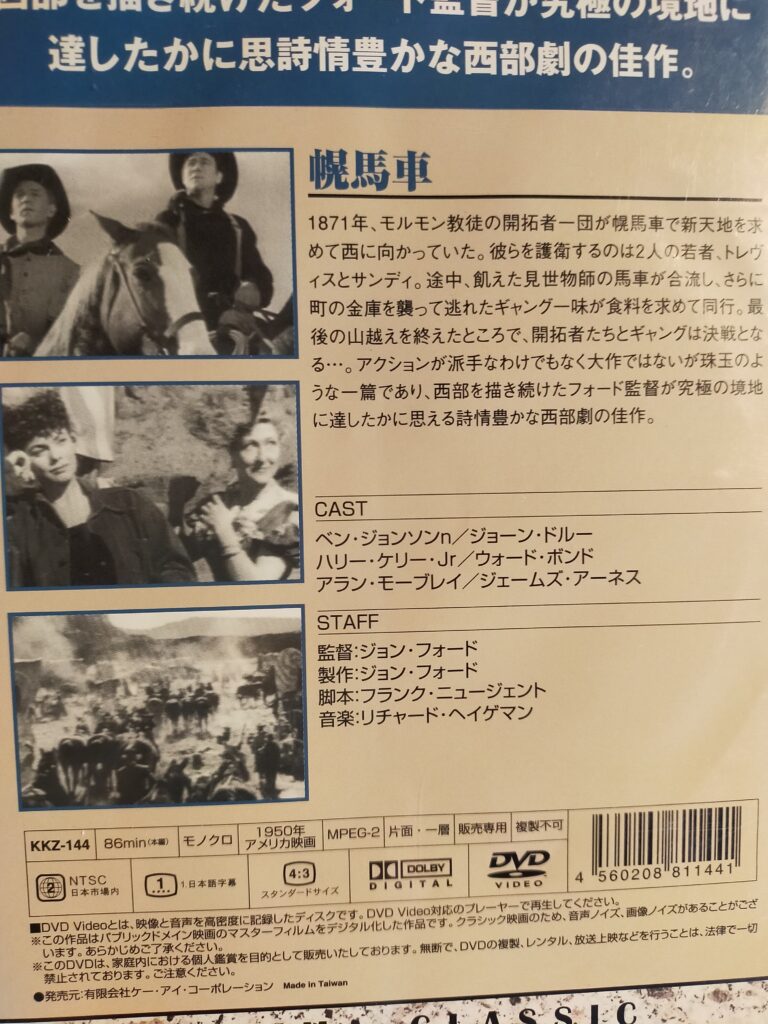全米映画協会が選ぶ歴代女優ベストテンで1位に輝いたのがキャサリン・ヘプバーン。
DVDで見た、「勝利の朝」(1933年)や「赤ちゃん教育」(1938年)がまずは面白く、主演のキャサリンが若々しく、エネルギッシュで可愛げもあり、いっぺんでファンになってしまった。

古本屋巡りの際に、キャサリンの自伝が文庫本上下巻セットで売っていたので買って読んでみました。
口語体でつづられる自伝は、あけっぴろげで明るさに満ちており、何より読みやすく、たちまち読了しました。

生まれてから演劇に目覚めるまで
名門というほどではないが、東部の裕福な家に生まれた両親の記述からこの自伝は始まる。
教養があり開放的な家庭を築いた両親をキャサリンは生涯誇りに思う。

活発な少女だったキャサリンは、両親、特に父親の元、ますます活動的に育つ。
水泳、飛込、乗馬、のちに車のドライブなどはこの時期に身についたという。
「フィラデルフィア物語」(1940年)で、見事な水着姿で鮮やかにプールに飛び込むシーンを思い出す。

高校時代に演じることの面白さに目覚め、カレッジ時代を通して演劇を続ける。
父親は眉をひそめたが干渉はしなかった。
駆け出し時代のキャサリンのエピソードが語られる。
ある演劇の端役をもらったときのこと。
衣装が配られる日に早めに駆け付けたが順番はびりだった。
残った似合わない衣装を持って呆然としていると、一番に並び、いい衣装を身に着けた女の子がキャサリンにこう言った。
「この衣装受け取ってくれないかしら。私、結婚するの。女優にはならない。でもあなたはなれると思う。大スターになるような気がするの。ね、受け取って」。
大スターになる星のもとに生まれてきた、キャサリンらしいエピソードではないか。
まるで映画のような話だが、どんなにドジでも、失敗しても、スターになる人はなるのだ。

こうして「勝利の朝」のストーリーそのままに、キャサリンの駆け出し時代が過ぎてゆく。
キャサリンはまたこの時代に生涯一度の結婚をする。
その相手とは離婚後も一生涯の友人の一人となる。
ハリウッドデビューと映画スターへの道
デビッド・O・セルズニック製作、ジョージ・キューカー監督の「愛の嗚咽」(1932年)でハリウッドデビュー。
出演に当たってはギャラと待遇をセルズニックと直接交渉しているのが、いかにもキャサリンらしい。
週給1500ドルの3週間契約だった。

ハリウッドといえば、業界の悪習渦巻く背徳の都、というのが山小舎おじさんの連想だが、キャサリンの自伝にもそれらしきエピソードが出てくる。
デビュー作「愛の嗚咽」の共演者がジョン・バリモアだった。
名優であり、キャサリンもリスペクトをもってバリモアを描写する。
撮影期間中バリモアの控室に呼ばれたキャサリンがドアを開けると、だらしない格好でソファに横たわっていたバリモアが毛布をはねのけた、キャサリンは部屋を飛び出した。
この事件の後もバリモアのキャサリンに対する態度は変わらなかった、云々。
こういったセクハラ?は被害者からの拒否にあうと加害者の態度が悪化するのが普通だが、そうならないところもキャサリンがスターの星のもとに生まれた証左の一つであろうか。

MGMではタイクーン、ルイス・B・メイヤーに可愛がられる。
本来は吝嗇で口うるさく高圧的でパワハラ満載なのがハリウッドのタイクーン像である。
「彼は私を自由に泳がせてくれた」(自伝上巻P367)とキャサリンは、メイヤーについて語る。
他人に言わせれば、キャサリンがタイクーンを上手く転がしているように見えるのだが、こういった大物とうまくやれるところもキャサリンの才能の一つである。

監督ジョージ・キューカーとの公私にわたる交友についてもページを割いている。
デビュー作、そして勝負作「フィラデルフィア物語」にはキャサリンのご指名で演出にあたった、演劇出身の名監督。
キューカーの豪邸にはキャサリンをはじめスターが集まった。
専用の部屋まで用意されていたキャサリンにとって、その豪邸はカルフォルニアでの定宿となっていたという。

ハワード・ヒューズはキャサリンのハリウッド時代の愛人だった。
ヒューズがキャサリンの舞台で見染め、旅公演にまでついてきたのが始まりだという。
別れた後も交友関係は続いた。
離婚相手とも、別れた元愛人とも、その後も友人でいられるところもキャサリン。
大物である。
そして最もページ数を割いて語られるのが最愛の人、スペンサー・トレーシー。
二人が出会ったとき、スペンサーには妻子がいた。
27年間キャサリンはスペンサーと暮らし、生涯深い敬愛を抱いた。
死をみとったのもキャサリン。
人情を越えた広い心を持つのもキャサリンか。
スペンサーの未亡人、娘とはその後親交を結んだという。
パトリシア・ニールが、妻子あるゲーリー・クーパーと愛人関係となって、クーパーの死後、残された娘に会って打ち解け、友人となったというエピソードを思い出す。

(余談)
自伝ではほとんど触れられていないが、1947年から始まった非米活動委員会(いわゆるハリウッド赤狩り)に際し、ハリウッドに対する政治の非干渉を求めて立ち上がった映画人グループの象徴的存在がキャサリンであった。
自由と正義を愛し、自分で考え、正しいと思ったことは表明し、突き進む、まことに彼女らしいふるまいだ。
非米活動委員会に召喚された、製作者、監督、脚本家の10人が議会侮辱罪で投獄される中、キャサリンとともに立ち上がった映画人にも変化が起こる。
迫害を苦にしての自死(ジョン・ガーフィールド)、仕事を干される(マーナ・ロイ)、運動からの撤退(ハンフリー・ボガート、ローレン・バコール)などなど。
結果的にキャサリンには何の影響も、お咎めもなかったのだが、その背景にはMGMの大立者、メイヤーの庇護、愛人ハワード・ヒューズの存在があった。
なにより本人がアメリカ支配層のWASP出身、があったからではないかと思うのは山小舎おじさんだけであろうか。