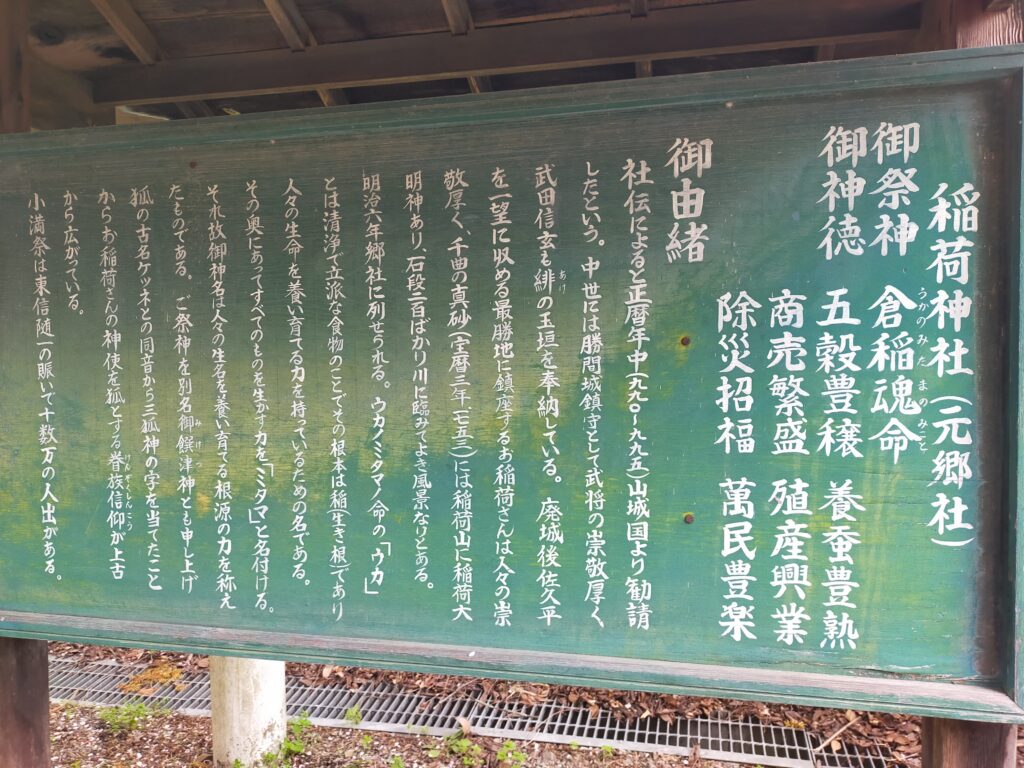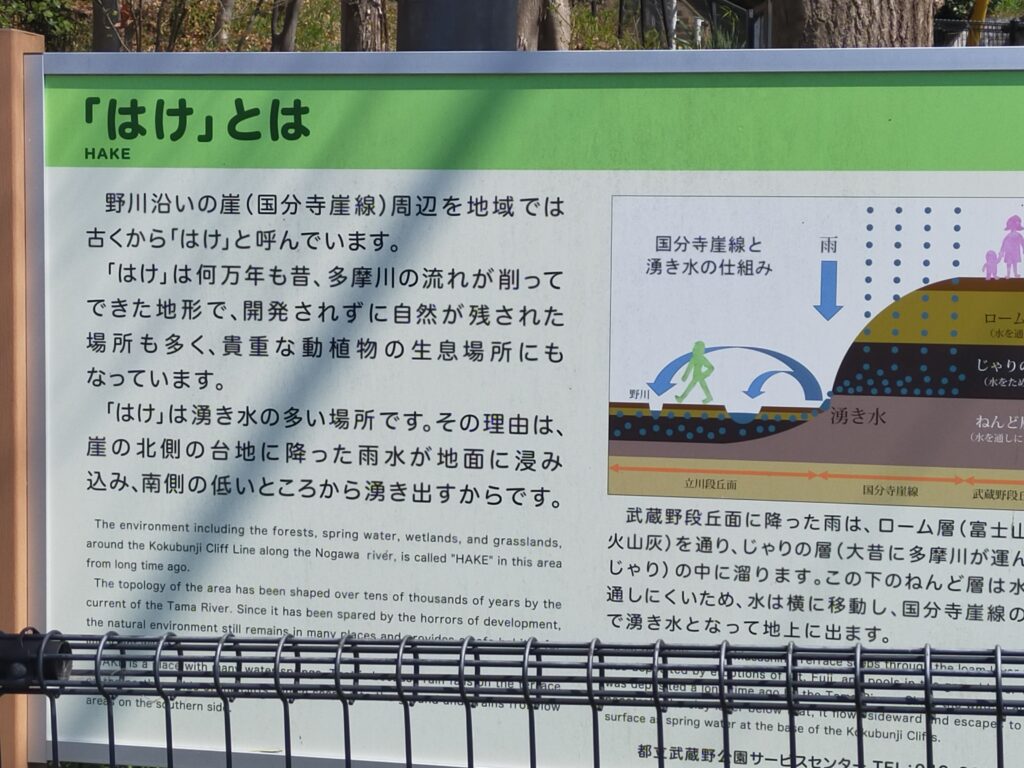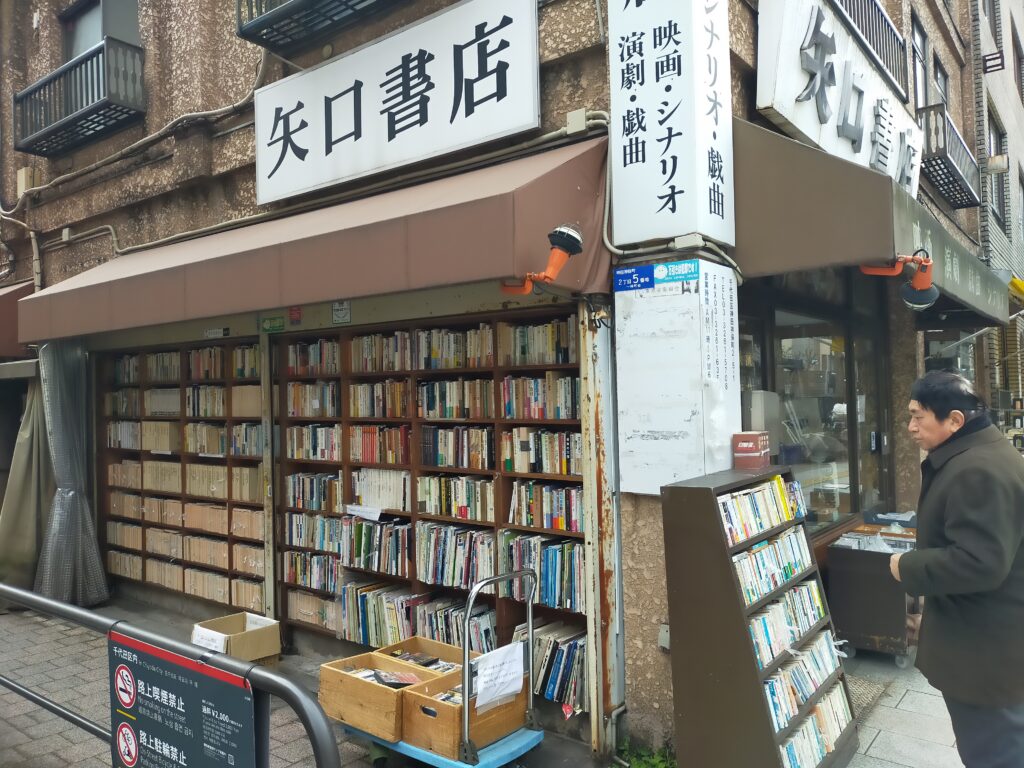令和6年の夏は、東京では梅雨明け以前に真夏日が続いたりと酷暑の様相を呈しています。
標高1400メートル以上の山小舎でも、7月中旬になって、30度以上の真夏日に襲われています。

今月になって毎週1回以上を草苅バイトに出ている山小舎おじさん。
猛暑日に当たると、日陰はいいのですが、日向での作業は強烈です。
かsら30分から40分に1回の休憩があり、平均年齢70歳のバイト仲間たちは気を使ってもらえるのですが、それでも体力が消耗してくるとダメージを食らいます。
山小舎おじさんはある時、午後になってから、熱がこもって気分が悪くなりそうでした。
つなぎを着ての仕事なので、暑さが逃げないのです。
それでも体力があるうちはいいのですが、午後になると体がギブアップしそうになる時があるのです。
先日も別のバイト仲間が苦しさを訴え、休憩してました。
バイト休みのこの日も真夏日です。
客用の布団や、ダイニングの椅子のソファーを、ぎらぎらの日光に当て乾かします。
バイト用のつなぎ服も干します。

30年以上住んでいる人によると、かつては「シーツが1日で乾かなかった」ほどの姫木も、温暖化の影響なのか真夏日に襲われるようにもなりました。

洗濯ものや、布団干し、これからシーズンの梅の土用干し、薪の乾燥などには都合がよいのですが、山小舎がこれだけ暑いと、平地の畑などの暑さはとんでもないことになっているので行動が制限されます。
山小舎周辺でも直射日光下での作業は気が進みません。
午後2時を過ぎるとひんやりした風が吹き始め、日暮れから翌朝までは涼しいことが救いです。