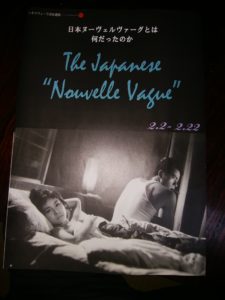三鷹駅北口の水中書店という古本屋で800円で購入した本を読んでいます。
599ページの大冊で、本体定価3,689円1994年初版の文芸春秋社刊の翻訳本「ハリウッド帝国の興亡」です。
小中学生時代に、リバイバル上映で「80日間世界一周」や「エデンの東」「シェーン」などを映画館で観て映画に心惹かれ、長じては生意気に監督別に作品を追っかけたりしてきた山小屋おじさんの映画人生ですが、齢を越えてようやく映画を「線」で観ようと思い立ちました。
個別の作品に感動したり、好きなスターや監督作品を追いかけるのが、「点」で観るということならば、映画の歴史の流れにのっとった形で作品を選択・鑑賞するのが「線」で観るということだと、遅まきながら気づいたのです。
名画座・渋谷シネマヴェーラではずいぶん前から「映画史上の名作特集」というのをやっていて、サイレント時代の「イントレランス」(1916年)から50年代の作品までデジタル上映しています。
当初は、翻訳なしの素材をやっていましたが、今では自前で翻訳しているようで、歴史上の名作を系統的に(フィルムノワール特集、ミュージカル特集、サイレント時代特集など)上映しています。
最初はこれらの古い名作群のラインナップに心が動かなかったのですが、フィルムノワール特集などで1,2本観てみるとそこには実に味わい深いものがありました。
「夜の人々」(1948年)、「ハイシエラ」(1941年)といった作品は、映画の原点ともいうべき要素が詰まっており、見ごたえがありました。
思い返してみると、おじさんが小学生後半から高校生にかけてテレビの古い洋画放送を観たときも、様々な作品に感動したものでした。
当時は淀川長治さん解説の日曜洋画画劇場のほか、金曜、土曜の夜、日曜の昼間、平日の昼間などに洋画放送があり、そこで数々の映画に接したものでした。
テレビで数々の作品にアトランダムに接したことは財産になりました。
「我が谷は緑なりき」(1941年)、「私は死にたくない」(1958年)、「アパートの鍵貸します」(1960年)、「終身犯」(1962年)などをの作品を思い出します。
ということで、山小屋おじさん、映画鑑賞人生50年の膨大な時間をブラウン管とスクリーンにかけてたどり着いたのが、1940、50年代のアメリカ映画(特にフィルムノワールと呼ばれる分野)と大蔵貢時代の新東宝映画、という魅力的な?「2大分野」です。
映画の歴史という「線」の中で浮かび上がってきた二つの「黄金の時間帯」です。
特に40年代のフィルムノワールがアメリカの映画界で生まれた歴史上の必然や、日本では知られていなかった作品群を知りたいなと思い、関連する本なども探してみたのです。40,50年代のアメリカ映画を「線」上で観るための参考書が欲しかったのです。
そんな時に見つかったのが「ハリウッド帝国の興亡」でした。
著者のオットー・フリードリックという人は1929年生まれ。40年代の映画はボストンでの学生時代に週2、3回観ており、イングリッド・バーグマンの大ファンで、ロナルド・レーガンが死を演じる場面には涙を禁じ得ない、との自己紹介。
本著作では40年代を各年ごとに章で区切り、著者が選んだエピソードを、辛辣な批評を加えるかたちでピックアップしています。
関係者にインタビューなどはせず、文献を漁ってまとめる手法で、矛盾するエピソードも並立に示して、全盛期のハリウッドの歴史、つまりは映画そのものの歴史についてつづっています。
前半の1945年までを読みましたが、そこでつづられているエピソードは、例えば・・・。
・ハリウッドの撮影所で絶対的な帝王として君臨するプロデユーサー達。
MGMのルイス・B・メイヤー、ワーナーのジャック・ワーナー、パラマウントのアドルフ・ズーカー、20世紀フォックスのダリル・F・ザナックなど。
⇒ロシヤや東欧出身で、屑屋や職人から身を起こしたそうした初代「帝王」たちの無知ぶりと暴君ぶり。
ジャック・ワーナーは靴職人時代からの癖で、撮影所内を歩いていても釘が落ちていると拾ってくわえていた、など。
⇒コロンビアの「帝王」ハリー・コーンのオフィスにはイタリアファシスト党の党首・ムソリーニの肖像画かかっていたり、MGMの「帝王」メイヤーのオフィスは、レザー張りの壁、4台の電話、暖炉、グランドピアノがすべて白で統一されていたそうです。
とにかく「帝王」たちは、『独りよがりで、無学、貪欲、冷酷で人をだます』人たちだった、とあります。
著者の「帝王」たちに対する姿勢には妥協も忖度もありません。
経営者たちの実像を描くことは、夢の工場と言われたハリウッドの産業としての映画のある意味での背景というか実像に迫ることでもあります。
・戦前にドイツから亡命してハリウッドにたどり着いた映画人たち。
フリッツ・ラング、ビリー・ワイルダー、ロバート・シオドマークなど。
⇒フリッツ・ラングのハリウッドにおける成功。
「激怒」(1936年)がヒットして以降、ドイツ人でもアクション映画が撮れると認められたこと。
ビリー・ワイルダーのハリウッドにおけるあくなき成り上がり。
・亡命してきた文化人たちのこと。
トーマス・マン(文学)、アーノルド・シェーンベルグ(音楽)、ベルナルド・ブレヒト(演劇)達とその顛末。
⇒なぜかハリウッド周辺にたどり着いた彼ら文化人亡命者。
その多くは祖国での栄光に比して、最後までみじめな境遇にあったこと。
・ハリウッドのスタッフ組合と、ロシア移民のチンピラだった、ウイリー・ビオツという組合ゴロの顛末。
⇒チンピラ上りが組合のボスを買収し、ストをチラつかせるなどして会社側をゆすり、のし上がっていった末の悲惨な終焉。

・戦争時におけるハリウッド人たちのふるまい。
⇒戦時債券を買った人にキスでお礼するヘデイ・ラマールとラナ・ターナーと、軍隊慰問に特化してゆくボブ・ホープのことなど。
・10万ドルの予算で年1本を自由に制作できる破格の条件でRKOというハリウッドの弱小スタジオに乗り込んだ23歳のオーソン・ウエルズが、ジョージ・シェーファーというプロデユーサーの後ろ盾を得て、「市民ケーン」を製作公開するまでの手練手管。
⇒モデルとなった新聞王・ハーストに批判的だとバッシングの中、ウエルズは「テスト」と称してカメラを回し撮影を敢行。
作品完成後は、敵対陣営からの高額でのネガの買取り申込みをシェーファーが謝絶。
作品公開直後にRKOが買収され、制作者:シェーファー、監督:ウエルズともに、RKOを追放されるまでのわずかの間に、「市民ケーン」という映画史上のベストワン作品(ウエルズが思うままに作った最初で最後の映画)が生まれたことの奇跡。
・俳優、スタッフを7年間縛り続けるハリウッド独特の契約システムと数々の犠牲者たちとその反撃。
⇒奴隷的契約に風穴を開けた、ワーナーに対するオリビア・デ・ハビランドの抵抗。
・ハリウッドの「帝王」たちが、末端の映画館までを経済的に支配した「ブロックブッキング」は1939年に独禁法違反となっていたが、「帝王」たちは無視していた。
そこに1944年司法省の告発が入って「帝国」の独占にひびが入り始める。
・のちの「ハリウッドの赤狩り」の萌芽ともいえる、映画人のいわゆるブラックリストが、撮影所の「帝王」たちによって作り始められた。
・著者お気に入りの監督のエピソード。
オットー・プレミンジャー、チャールズ・チャップリン、ジョン・ヒューストン、プレストン・スタージェス達。
⇒これらの監督たちがハリウッドで仕事するに至るまでの様々な経緯と、そのもてる才能のこと。
そして彼らを高額報酬で「囲った」挙句、その才能を換骨奪胎せんとする、撮影所の「帝王」たちとの闘いと往々にしての敗退。
・著者お気に入りのスターのエピソード。
リタ・ヘイワース、エロール・フリン、バーグマン、レーガンなどについての様々なこと。
⇒スペイン人の父を持ち、黒々とした巻毛の少女が、直毛の赤毛に直して芸名をリタ・ヘイワースとし、「カバーガール」(1943年)で女神になるまで、など。
以上、基本的に著者の好みに寄った選別でつづられるエピソードではありますが、リアルタイムに歴史に接してきた記述には臨場感があります。
といっても著者はハリウッドに暮らしていた、いわゆる関係者ではないので皮肉と辛らつを込めた距離感もあります。

ハリウッドのスキャンダルと言えば、写真をメインに、チャップリンやエロール・フリンなどのスキャンダルを集めた「ハリウッドバビロン」という本もありました。
本作もスキャンダルを扱ってはいますが、歴史、政治、芸術性の流れを見失うことなく、独特のユーモアある筆致が魅力的です。
本の後半が楽しみです。





 ラピュタ阿佐ヶ谷、モーニングショウの女優特集は、「江利チエミ」でした。
ラピュタ阿佐ヶ谷、モーニングショウの女優特集は、「江利チエミ」でした。



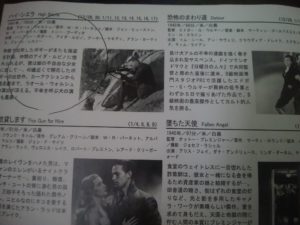



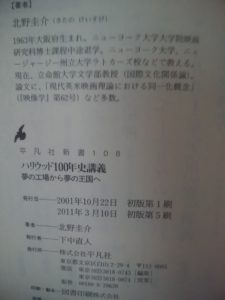






 ラピュタ阿佐ヶ谷のロビーでは往年の映画スターのプロマイドが売られています。女優さんの写真はよく売れるそうです。
ラピュタ阿佐ヶ谷のロビーでは往年の映画スターのプロマイドが売られています。女優さんの写真はよく売れるそうです。 ロビー奥には書籍コーナーもあります。
ロビー奥には書籍コーナーもあります。