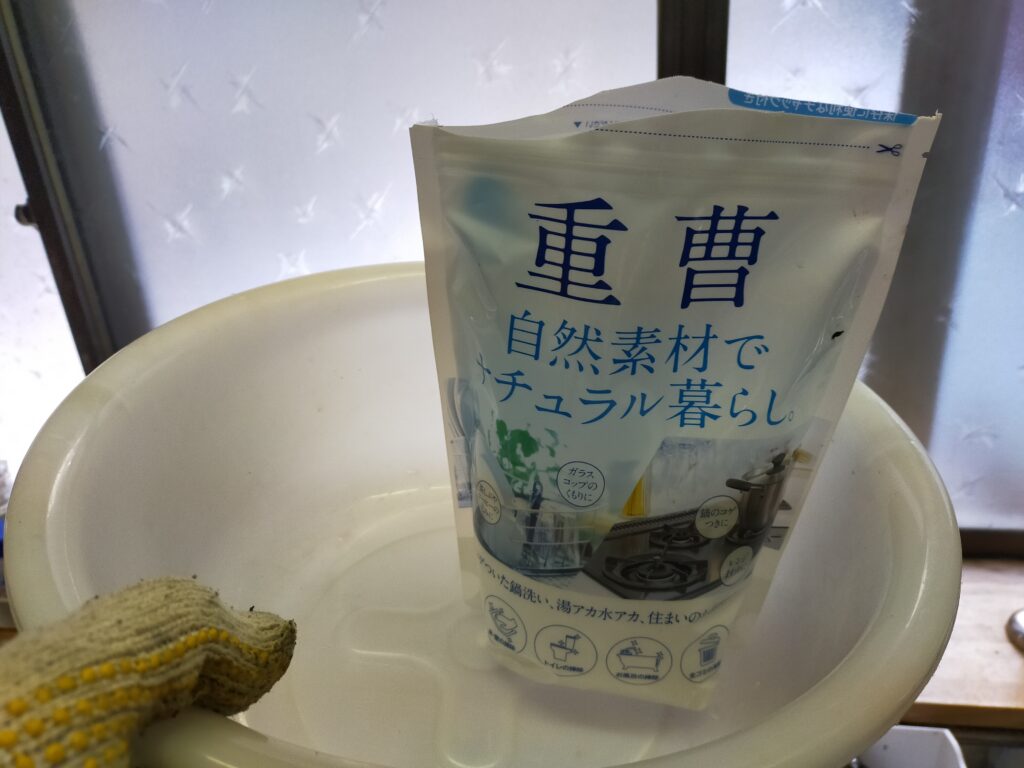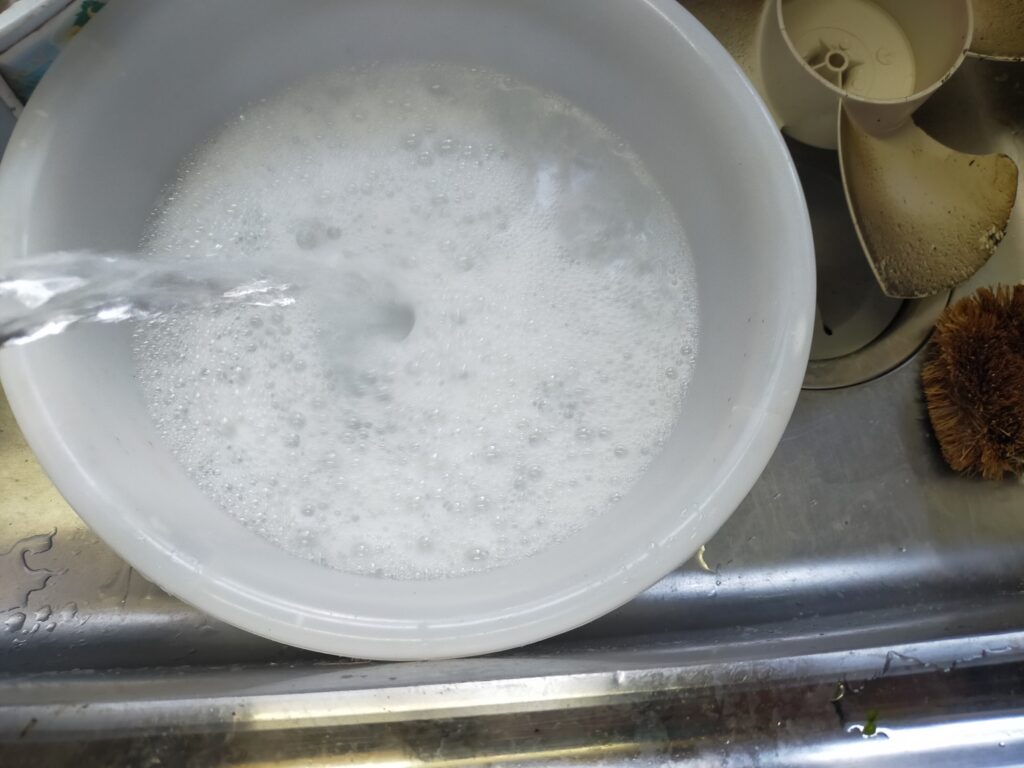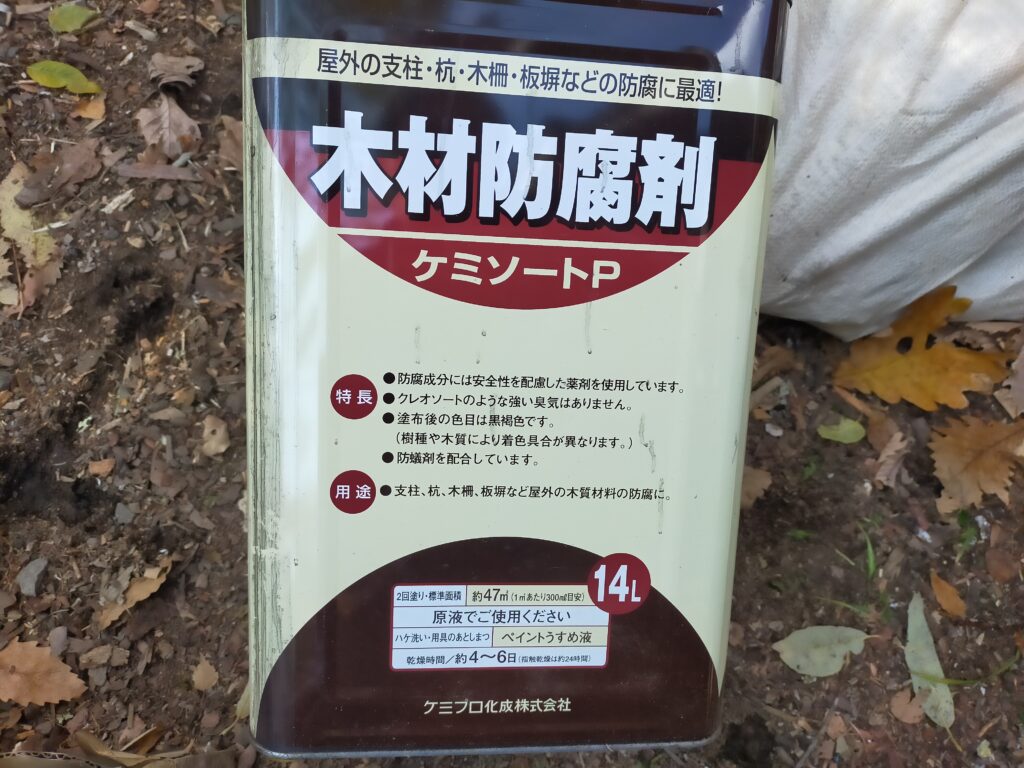年末です。
山小舎の大掃除をしています。
今年は特に、台所周りになぜか関心があります。
まずは食器棚などの上に溢れる食品類の整理です。
ついでにトースターの内部を洗います。



取り出した食品類は種類別に整理し直します。
缶詰類、調味料、主食、非常食、開封済みのもの、などなど。
寒い季節なので、食料保存用の部屋(主食、野菜、瓶詰類、漬物などの貯蔵部屋)を大いに利用します。


鍋釜、調理器具などが収まっている、流し台の下や引き出しなどもこの際きれいにします。
引き出しそのものも洗ったり拭いてから、新しく新聞紙などを敷き、調理器具などを収め直します。
使わない鍋釜や調理器具を廃棄します。




ついでに台所の上の部分をきれいにします。
上の部分とは、冷蔵庫や食器棚の天板、鴨居の上などです。
家族が来訪する際に室内で炭火焼きをすることが恒例となっている山小舎は、特に台所付近が油の煙で汚れています。
汚れがきつい部分は、重曹をつけたたわしでこすり、雑巾で拭き上げます。
埃が多いと先に科学雑巾で拭きます。



先代オーナー時代の備品が豊富な山小舎では、大掃除の旅に廃棄物が出ます。
燃やせるものは燃やし、プラスチック類、金属類は分別して捨てます。
この後は、流し、レンジ回りなどを洗って、台所の掃除は終了です。
使う道具は科学雑巾、たわし、布雑巾。
材料は重曹、EM菌溶液です。
なお、重曹は油汚れはよく落ちますが、洗い残しが白くなることがあるので、よくふき取ることが肝心です。
EM菌は少しの間匂いが残ることがありますが、トイレや残飯などに効果絶大です。