ジャック・フェデーはトーキー以降、戦前にフランス映画を3本撮っています。
本ブログでは、そのうち「外人部隊」と「女だけの都」を紹介しましたが、残り1本「ミモザ館」を見る機会がありました。
「ミモザ館」 1934年 ジャック・フェデー監督 フランス
フェデーがハリウッドから帰って「外人部隊」を撮った後の作品。
この後に「女だけの都」を撮ってパリを離れる。
「ミモザ館」を含めた戦前のトーキー3本は、いずれも夫人のフランソワーズ・ロゼエを主演クラスで起用している。

ミモザ館という安宿をニースで営む夫婦がいる。
夫は公営ギャンブル場の管理職で、ギャンブルデイーラーの養成学校の講師も務める。
夫婦には養子がいて特に母親(ロゼエ)は息子を可愛がっている。
時がたちパリに巣立った息子(ポール・ベルナール)は、詐欺師や売春婦がたむろする安宿を根城に、盗難車を転売している。
賭け事には眼がない。
母親が心配してパリにやってきて、折からギャングのボスに焼きを入れられた息子を看病する。
息子はボスの情婦(リズ・ドラマール)に手を出したのだった。
息子は母の説得でニースのミモザ館に帰り、車販売の仕事に就く、が、ボスの情婦が忘れられない。
やがて情婦もミモザ館で息子と暮らすが、庶民の暮らしで我慢できる女ではなく、母とも全く合わない。
母は息子を取り戻すため情婦の居所をボスに伝え、やってきたボスが女を連れ去る。
息子は落胆し、また会社の金を使って賭博で穴をあける。
息子は自死して母の見守る中、その生涯を終える。

「外人部隊」は社会人としてダメダメの男が、パリで別れた女を生涯忘れられない、という作品だった。
「ミモザ館」の息子も、ぜいたくで浮気性で華美なパリの女を忘れられず人生が破滅する。
どうやら、浮気性の女へのダメな男の片思い、というのがフェデー好みのシチュエーションのようだ。
ぜいたくで、華美で、浮世離れして、だからこそ魅力的な女性と、何度も同じ失敗を繰り返すが人間味はある男の出会いこそが、フェデー劇のパターンの一つのようだ。
フェデーの狙いは、弱い人間同士がどうしょうもない己の業に振り回される様を、ある時は同感を込めてある時は淡々と見つめること。
そこでは倫理観や宗教観に基づく価値判断はない。
フランス映画らしい「人間主義」が貫かれる。

さらにこの作品では、ロゼエ扮する母親の息子への愛という禁断のシチュエーションが加わる。
これこそ無償のといおうか禁断のといおうか、周りが何といっても突き進むタイプの愛情だ。
この作品でも破滅に瀕する息子に妄信的な愛をささげる母親をロゼエが演じる。
一方息子は息子で、出て行った女を死ぬ間際でも忘れられないのが、フェデー流人間描写の粋なのだが。
フェデーとシャルル・スパークによるダイアローグの名調子を、舞台出身の名優たちが名演技で応える。
フランス映画のまさに黄金時代の作品。
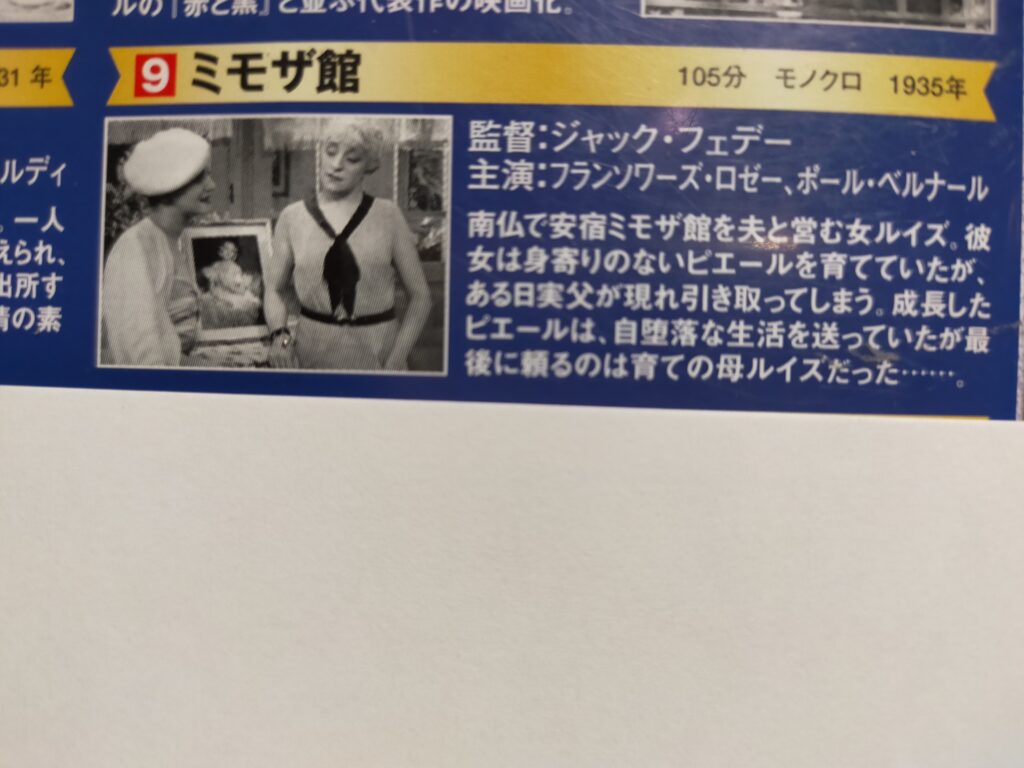
フェデーについての文献は手元にないが「天井桟敷の人々」の名女優、アルレッテイの聞き書きがある。
この中にフェデーと「ミモザ館」についてのアルレッテイの言葉がある。
「ミモザ館」での、詐欺師と売春婦が集うパリのカフェ兼安宿のシーンで、息子を待つフランソワーズ・ロゼエの隣で食事をしつつ会話を交わす夜の女の役でアルレッテイが出演しているのだ。

アルレッテイ曰く「フェデーは天性のプレイボーイなの。頼りがいがあってエレガントで、それはもう魅力いっぱいなわけ。(中略)完全主義者で厳格この上ないけれど、常にエレガンスをまとっている人。(中略)フランソワーズ・ロゼエは優しい人で、いつも役者たちの面倒を見ていたわ。」。
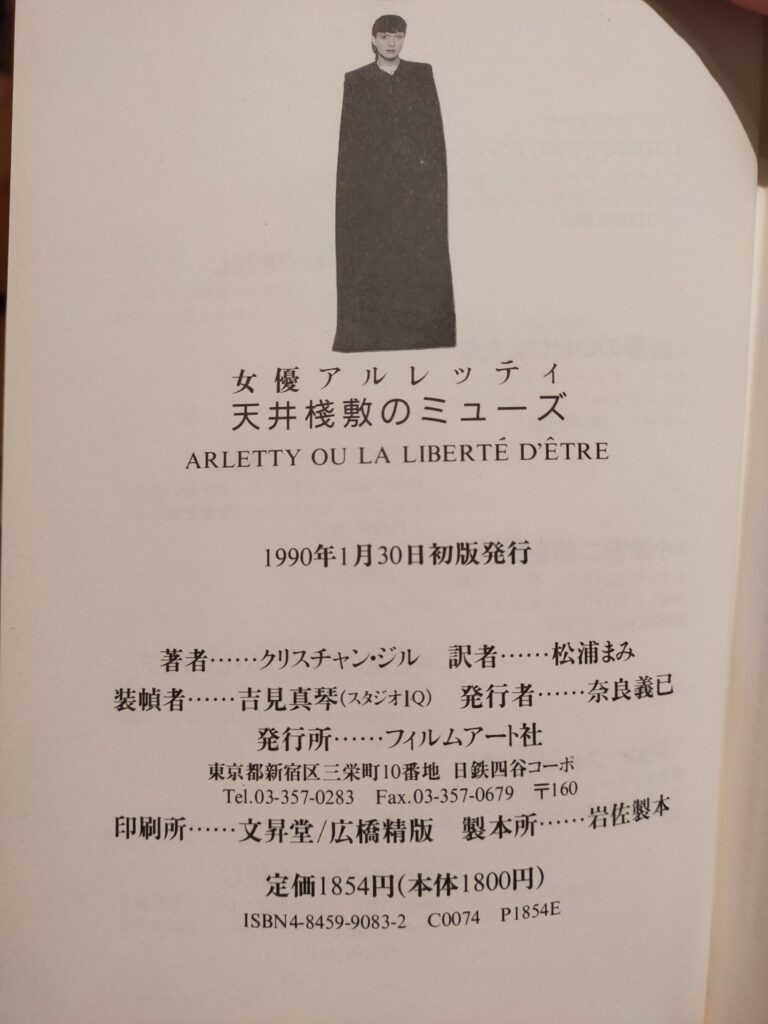
フランス映画黄金時代の巨匠、の歴史的位置づけには異論がなかろうが、今では忘れられてしまった感のあるジャック・フェデー作品。
ヒリヒリとした人間の描写に重みとフランス映画の歴史が感じられる。
