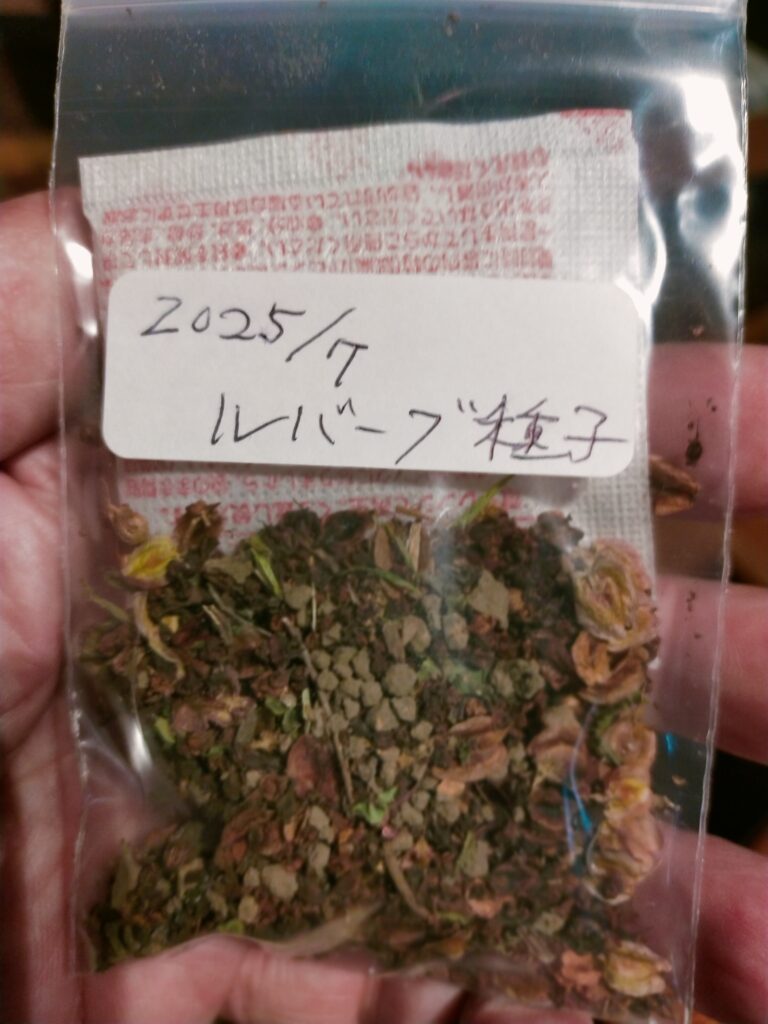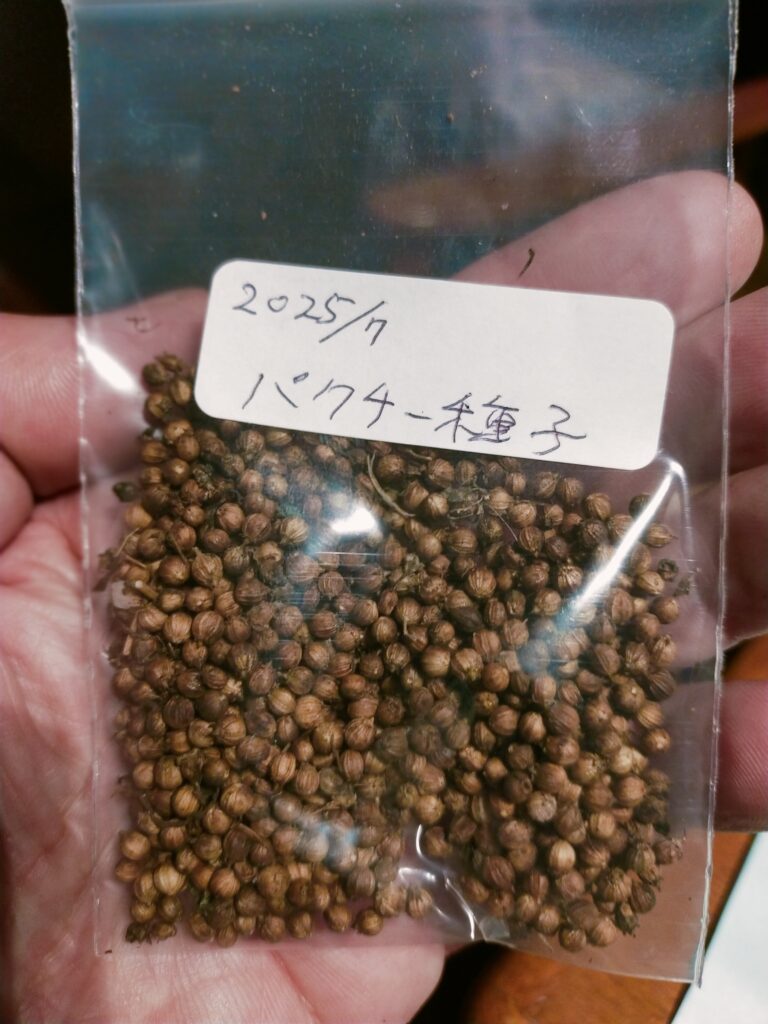畑に敷いていたビニールマルチを剥がしました。
11月下旬、たまたまポカポカ陽気の日が続きました。
「今だ!」。
気になっていた畑に出かけました。
夏野菜を植えた畝に黒いビニールマルチが十数列被せてあります。
雑草に覆われ、その雑草も枯れはて、また収穫の際ちぎれたままのマルチが並んでいます。

鍬をもって端から剥がし始めます。
押さえの石をどけます。
鍬をふるって端っこの土を起こしマルチの端っこを掘り出します。
両端が土に埋まったマルチをちぎれないように注意しながら、丸めるようにして剥がしてゆきます。

この時に問題点が二つあります。
特に土をかぶせて押さえていた両端の部分がちぎれないようにする事、マルチと一緒に丸め込まれる枯れ草をどうするかです。
両端のマルチがちぎれて土の中に残らないように鍬を使って土ごと起こしてゆきます。
丸めてゆくうちに枯れ草がマルチとともに巻き取られてゆくので、時々草を取り除きます。
手を使って丸め取ってゆくと腰が痛くなるので、主に鍬で土ごと掘起し、ある程度マルチが丸まってくると丸まったマルチを転がすように巻き取ってゆきます。
ちぎれた部分はその都度回収します。
2,3本の畝をマルチを残して越冬しようかな?とも思いましたが、ビニールがボロボロになるのは嫌なので全部剥がしました。

冬の日差しは、作業をしていると汗が流れるくらいですが、午後になると陽が陰ります。
日の当たらない冬の畑は寒々しいものです。
剥がしたマルチは山にして乾かします。
集めてゴミで出すのは来春でしょうか。