ハックルベリーという作物がある。
おじさんは長野に来て初めて見た。
直売所で買おうとして、レジのおばさんに、生食できないよ、と言われてびっくりした。
ジャムのレシピをもらって帰り、さっそく作った。
日本で食用にしているものは、ガーデンハックルベリーと呼ばれるナス科の植物とのこと。
本場の北米では、マーク・トゥエインの小説「トムソーヤの冒険」の続編的な「ハックルベリー・フィンの冒険」で主人公の通称となるくらいポピュラーな存在とのこと。
今年、定年おじさんが畑を作付けするとき、直売所の苗売り場で、これの苗を見つけた。
2本買い、植えた。
順調に育ち、8月には実を収穫し、朝市にも出した。
ジャムの作り方を説明すると、買ってくれるお客さんがいた。
畑のハックルベリーは、放っておいたところ、第二弾の花が咲き実がつきだして、生命力にびっくりした。
畑も10月下旬となり、最後の収穫をした。
根が強く張って引っこ抜くのが大変だった。
収穫量は小さいボールに一杯くらいも。
予定外の収穫だった。
ジャムを作る。
まず、あく抜き。湯でこぼした。
重曹などを使う方法もあるらしいが、おじさんは単なる湯でこぼしにした。
そのあと、砂糖を入れてストーブに掛けた。
色がいい。
ブルーベリーの5倍のアントシアニンの含有量だ。
煮ると同時に保存瓶の消毒も行う。
ジャムが煮詰まってきたら、 熱々の瓶にジャムを入れ、軽く蓋をして再び煮沸。
熱々の瓶にジャムを入れ、軽く蓋をして再び煮沸。
こうやって瓶の中の空気圧を抜いておく。
蓋をきっちり締めて完成。
ちゃんと作れば、常温保存で夏場を超えても傷まない。蓋を開けるときに苦労するくらい密閉されている。
このジャムは、おじさんが来年、朝市にハックルベリーを出品する際の試食用にする予定だ。



 急がないときや、煮込み料理にストーブは便利で威力を発揮する。
急がないときや、煮込み料理にストーブは便利で威力を発揮する。
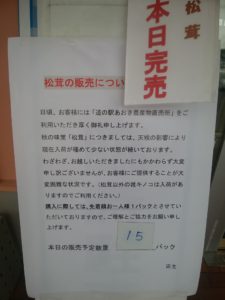






















 砂糖の分量はその後の保存を考えると材料の1/2が目途といわれるが、素材の香りなどを考えると1/3くらいか。
砂糖の分量はその後の保存を考えると材料の1/2が目途といわれるが、素材の香りなどを考えると1/3くらいか。  実が煮崩れてツヤがでてきたらアツアツのうちに、これまた消毒済みのアツアツの瓶に入れ、軽く蓋をする。
実が煮崩れてツヤがでてきたらアツアツのうちに、これまた消毒済みのアツアツの瓶に入れ、軽く蓋をする。 数分ののち引き上げ、瓶を固く締めて出来上がり。
数分ののち引き上げ、瓶を固く締めて出来上がり。
