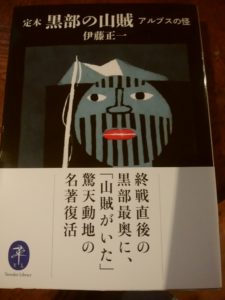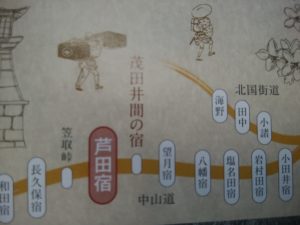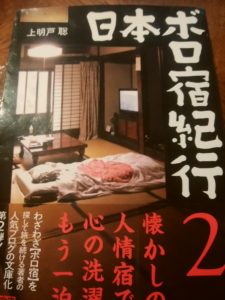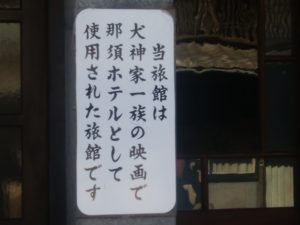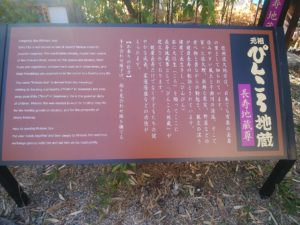13日付のブログで「畑の冬じまい」をご報告しました。
3年目を迎える一番慣れた畑の冬じまいの様子でした。
同様に今年から始めた畑の冬じまいをしようとしましたが、今度は思うようにゆきませんでした。
今年から始めた畑は全部で4枚あり、総面積も200坪ほどの広さです。
段々畑で元は水田。
粘土質の上、水はけがよくありません。
4月の春先にはそれでも耕運機で耕して、ジャガイモ、藍などを作付けしたのです。
が、冬じまいの耕耘をしたときは、土がぬかるんで耕運機のタイヤが滑ったり、刃が泥でつまったりして全くはかどりませんでした。
台風19号で1年間の降水量の40%が降ったという長野県です。
粘土質の畑にはその時の水分がまだたっぷり残っているのでしょうか。
それでも頑張って耕運機を操り、2枚半耕しましたが、そこでギブアップ。
年内の耕耘をあきらめました。
畑表面の雑草と枯れ草が土壌の乾燥を妨げているのかな?
と草刈り機で生え残っている雑草を借り、枯れ草を集めて、畑の表面に直接日光を当ててみようかな?
と思いましたが、土壌のぬかるみ?は短期間では乾きそうもないとわかりました。
ということで、この畑、年内の作業は枯れ草、枯れ枝の野焼きと排水のため排水路の整備にしました。
どこまでできるか。
今回は、畑の周りと排水路周りの雑草、枯れ枝を集め、野焼きの準備をしました。

排水路については、隣の山すそ沿いに1本、段々畑の各石垣沿いに1本(山すそ方向と、農道方向に)素掘りで掘ったもの(の名残)があります。
今後、それらを再度掘り直し、水の通りを良くしたいと思います。
この畑の排水には数年かかるものと思います。
畑の前任者による排水パイプが残っている。
利用したい。