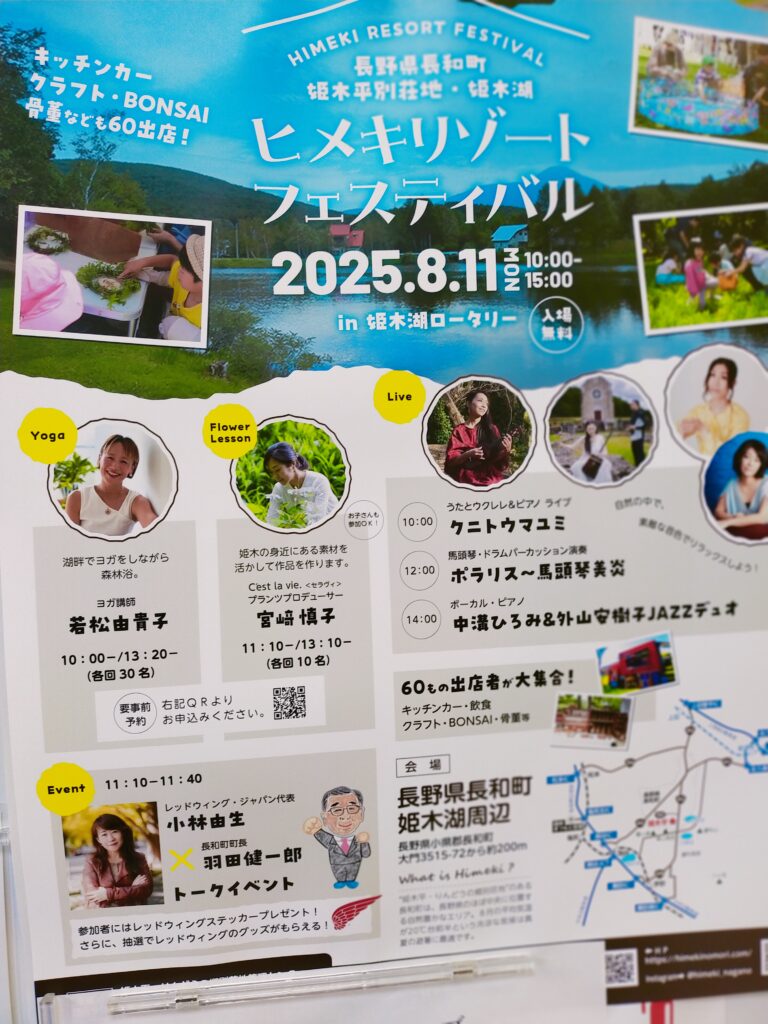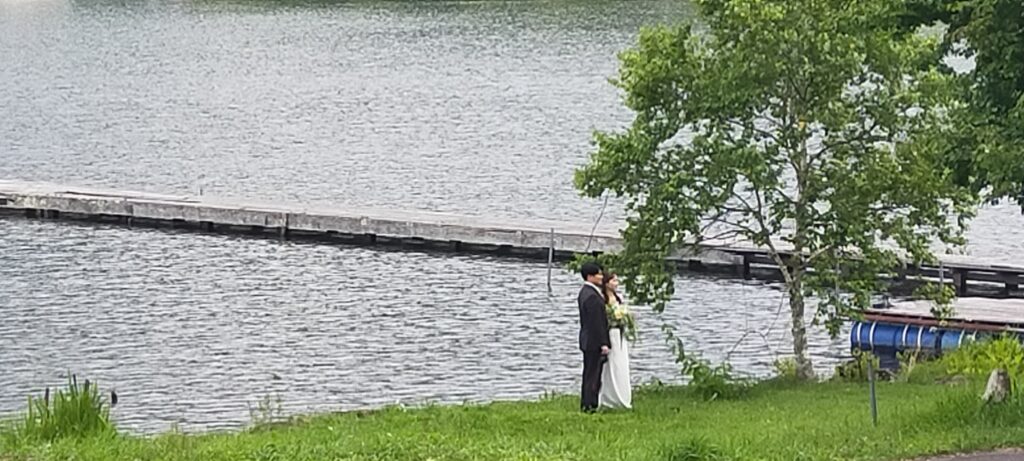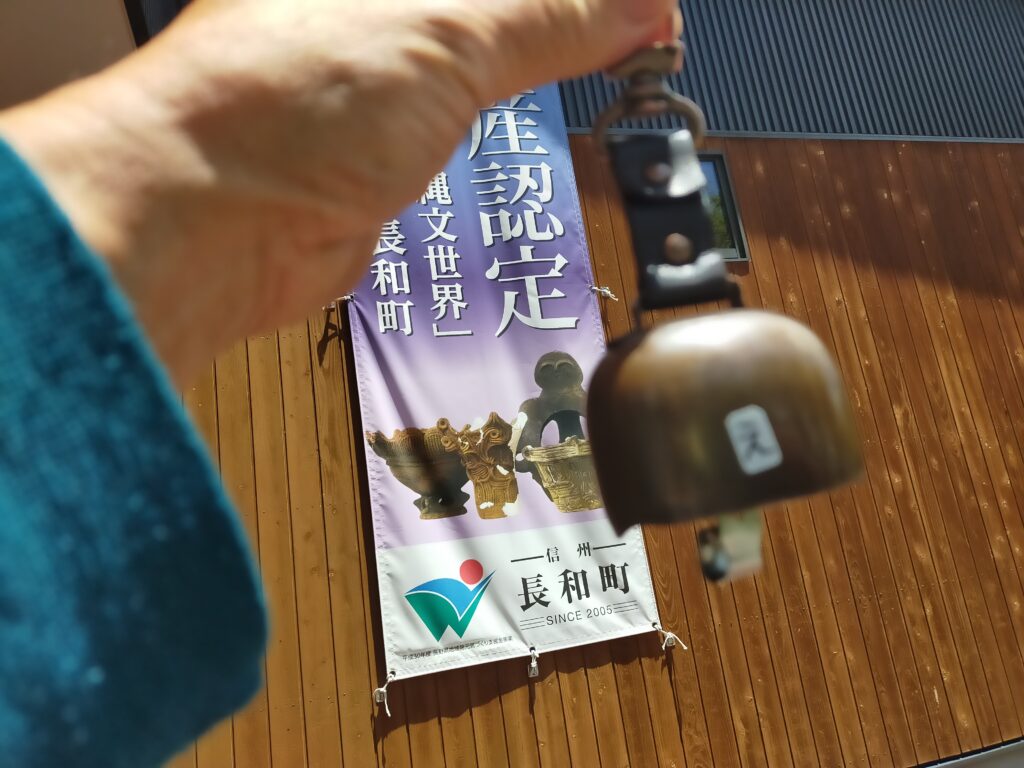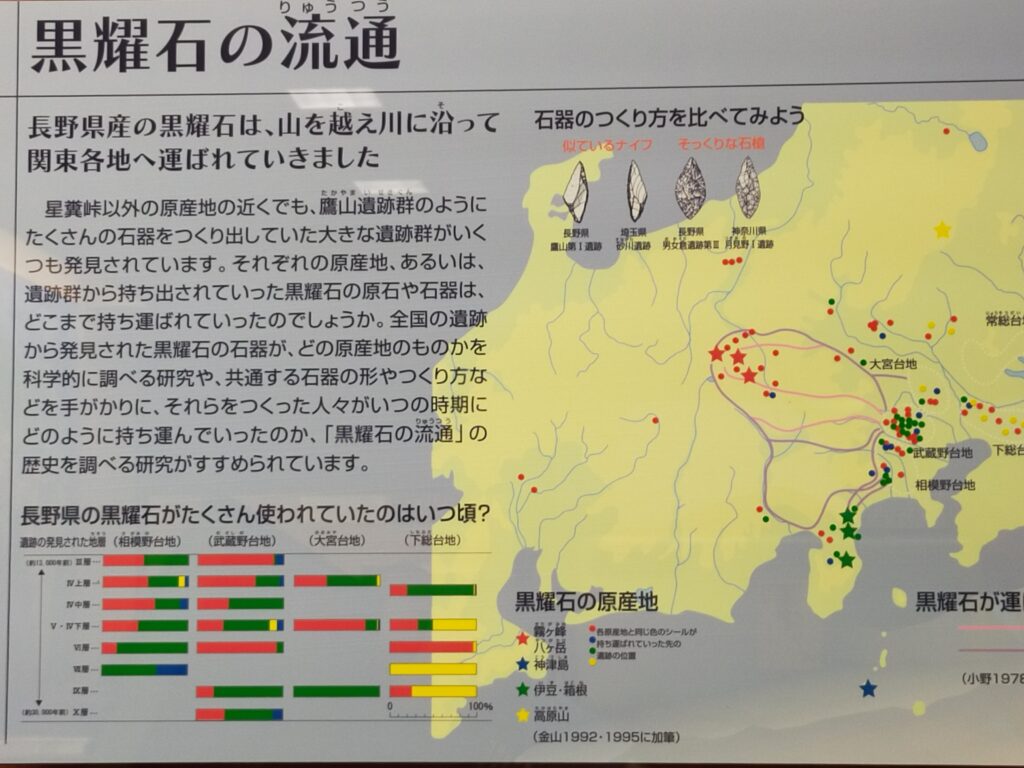山小舎の正月を孫らとともに過ごしました。
その間、台所の水道が不通でした(洗面所、風呂、洗濯機、トイレの水は出た)。
地下に下りて、水道管の損傷のなさ、電熱線の稼働を確かめ、問題がないことを確認しました。
それでも水が出ないのは素人の手におえず、業者を依頼。
山小舎おじさんが一人残って対応を予定します。
ダメもとで蛇口付近の水量調節のねじを緩めてみると水がドバっと出ました。
解決です。
凍結ではありませんでした。
業者に断わりの連絡を入れました。
単身、独力で自宅に戻ることにします。
交通手段は長和町のコミュニテイバスで白樺湖まで、アルピコ交通の路線バスで茅野駅まで、そこからはJRです。
当日の白樺湖発の路線バスの時刻に合わせて、長和町コミュニテイバス・ながわごんを予約します。
当初は定時運行だったコミュニテイバスはデマンド方式に代わっています。
山小舎の玄関前まで来てくれて一律300円で、町内全域と白樺湖周辺、丸子中央病院やスーパーツルヤなどに行ってくれます。
出先からもオーダーできます。

当日、朝8時20分にやってきたながわごんで西白樺湖バス停まで。
待ち時間がありましたが、空いていた土産物屋で過ごし、9時ころの路線バスで茅野駅まで行きました。
運賃は2000円。
値上がりしてましたが、シーズンオフでも1日2本の路線バス(茅野駅、車山高原間)が運行しているのは心強いものです。



真っ白な白樺湖御周辺の雪景色の中をバスでらくちんな移動です。



茅野駅で立食い蕎麦で腹ごしらえ。
甲府行きの普通列車に乗り込みます。
大月で東京行きに乗り換え、三鷹で降りてバスで帰宅しました。