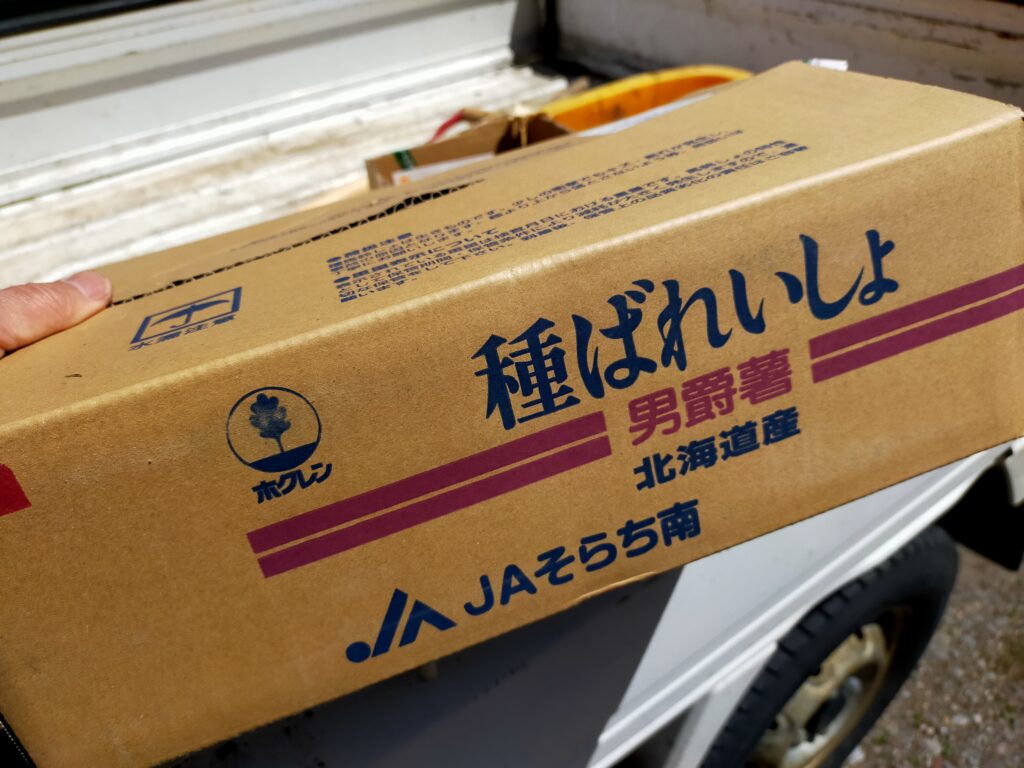4月に入り信州も畑の季節到来です。
寒い日は気温が氷点下になる時もあります。
こんな寒い日に植えられても野菜も大変だろう?と思うような日もあります。
八ヶ岳の山頂は雪が残っています。
一方で、畑の雑草は着実に成長しており、ナズナ、タンポポなどは花を咲かせており、季節は進んでいます。
ことしの山小舎おじさんの畑ライフ。
省力、省栄養、無農薬、無害獣をモットーに今年も頑張る予定です。
無肥料、無農薬、不耕起のガッテン農法を取り入れて4年目になります。
ガッテン農法式で起こした畝は計15畝ほどにもなります。
一度起こしたら再耕は不要といわれる畝です。
実が成る夏野菜は、例年通りこれらの畝に植えます。
ガッテン式の畝立てをしていない場所もたくさんあります。
鹿よけのネットで囲まれた場所、ネットなしの場所、そもそも畑として利用していない場所も。
ネットに囲まれた場所には、害獣防止のため、鹿が好む作物を植えましょう。
インゲン、キヌサヤ、枝豆、大豆、トラ豆などの豆類、かぼちゃ、ジャガイモ、サツマイモなど。
ネットなしの場所には鹿が好まない作物を植えましょう。
菊芋、里芋、ヤーコン、ウコン、長ネギにエゴマ、ほうずきなど。
山小舎おじさんの力と根気がなく、やむなく耕作放棄している場所は、春先に管理機をかけ、雑草を起こしておきましょう。
夏ころには草刈りも何度か必要になるでしょう。
集落設置のフェンスに覆われた場所は、ほぼ全面をガッテン式畝立て済みです。
夏野菜、キャベツ、ハーブなどを植えましょう。
今年はビーツにも挑戦したいと思っています。
さて4月も中旬になろうとする畑。
畑の準備に並行して植え付けを開始しました。
キヌサヤの苗を買ってきて植えました。
 キヌサヤの苗
キヌサヤの苗
キャベツ50株とレタス少々を定植しました。
 キャベツの苗。トレイに50株ほど
キャベツの苗。トレイに50株ほど
トレイで発芽させて売っているキャベツの苗。
山小舎おじさんのような、素人さんの畑にはトレイからポットに移して、もう少し大きく育てた後に植えた方がよいのかもしれません。
ですが、朝晩の寒暖差が激しく、温室もない山小舎で春先の育苗は難しいので、このまま定植しました。
定植前には苗にえひめAIの希釈液を吸わせておきます。
事前にマルチで地温を高めておいた畝に植えてゆきます。
トレイは小さいので手で苗を取り出すことは困難です。
小さいフォークを使ってトレイから苗を掘り出します。
 トレイからフォークで取り出す
トレイからフォークで取り出す
 マルチにあけた穴に植えこむ
マルチにあけた穴に植えこむ
苗をマルチの穴に置いたあと、苗に体重をかけて鎮圧します。
苗と土壌を密着させ、自力で給水させるためです。
これまでのキャベツ栽培は、乾燥のため初期の生育が悪かったり、育っても長雨でカビが発生したりしました。
初期の育成促進のために、植え付け前の畝に去年から自作しておいたボカシ肥料を入れてみました。
しばらくは畑に行くたびに水やりもしようと思います。
果たして今年のキャベツの生育はいかに。
 キャベツの定植終了
キャベツの定植終了