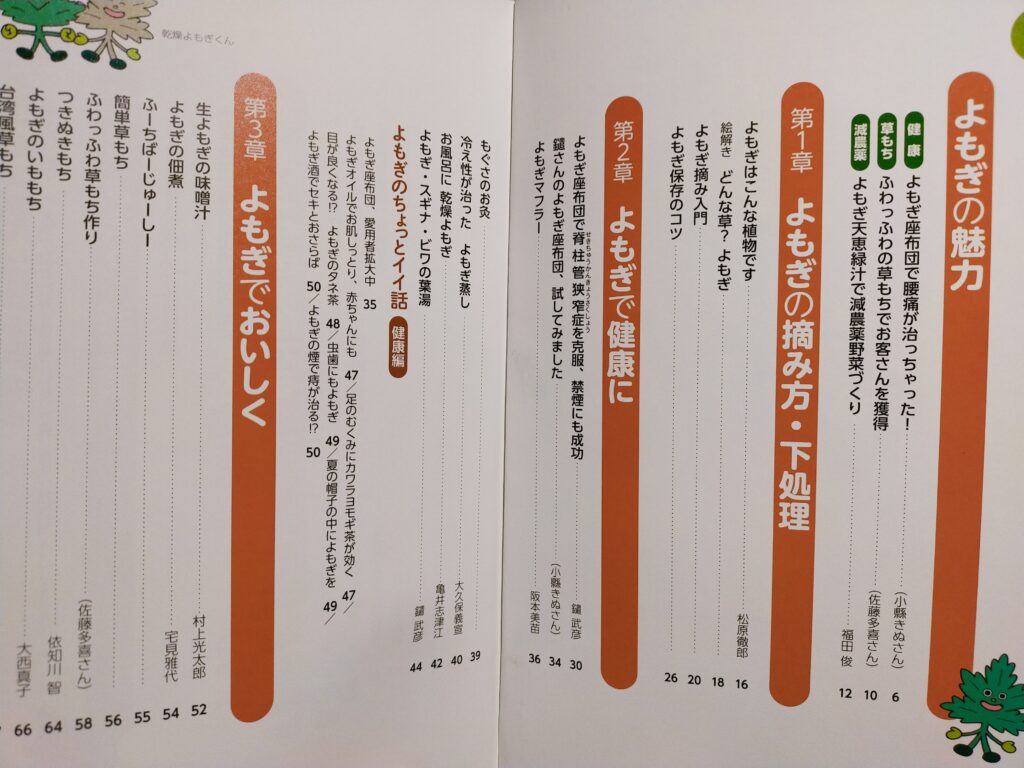12月に入っての戸外作業はするものではないことを痛感しながら、雪の中で薪割りを再開します。
根雪を予感させる、さらさらの白銀の世界です。
薪に付着した雪は、溶けかかっているわけでも、手でサラサラと払い落とせるわけでもなく、凍りついています。
思わず、話に聞いたシベリア抑留での冬の森林伐採作業が頭をよぎります。
 雪の中で始動を待つ薪割り機と玉の山
雪の中で始動を待つ薪割り機と玉の山
冬の日差しが雪面にキラキラ反射するなか、わが薪割り機が排気ガスを噴射して始動します。
まったく頼りがいのある機械です。
己の水分で凍り、くっついた玉を、蹴っ飛ばしてから薪割り機に乗せます。
割った薪を、軽トラの荷台に放り投げます。
 サラサラの冷たい雪の中で奮闘する薪割り機
サラサラの冷たい雪の中で奮闘する薪割り機
作業の段取りは、軍手の上に厚手のゴム手を履きます(手袋を「履く」というのは北海道弁です)。
軍手だけで雪中作業をすると手が濡れてとんでもなく冷たくなり、作業を継続できません。
また、足元の長靴は事前にストーブのそばで温めておきます。
玄関などに置きっぱなしにした長靴は、たとえ濡れたりしてはいなくても、冷え切って足先を強烈に凍らせるからです。
 雪の作業で必要なゴム手。指先が破れている
雪の作業で必要なゴム手。指先が破れている
 長靴をストーブのそばで温める
長靴をストーブのそばで温める
シベリア抑留はともかく、子供のころ旭川で遊んだ冬の日の防寒事情が、60年ぶりに思い出されます。
さて、軽トラの荷台に積んだ薪をどうしましょうか。
本来ならこのまま斜面下の乾燥台に運びたいのですが、雪の斜面で軽トラを使うとしたら、下りはともかく、登る時のスタックが当然予想されます。
でも、人力で雪の積もった斜面下に運ぶとしたら、絶望的な労力が必要です。
ここで北国育ちの山小舎おじさんのカンが発動します。
「今日の雪の状態、積雪量、斜面の角度、軽トラ四駆の能力を勘案すると、軽トラの使用は可能。スタックしたら、車輪に板か毛布をかませて脱出しよう。」
ということで軽トラを雪の斜面に突入させました。
 軽トラで斜面下の台に薪を運ぶ
軽トラで斜面下の台に薪を運ぶ
案ずるより産むがやすし。
登る際に多少蛇行はしたものの、スタッドレスの四駆がしっかり雪を噛み、無事軽トラは役目を果たし、山小舎おじさんを感激させました。
 無事雪の斜面を登り切った軽トラのタイヤの跡
無事雪の斜面を登り切った軽トラのタイヤの跡
さあこのまま薪割り作業で突っ走るぞ、と意気込んだその時。
それまで黙々と木材に刃を割り込ませていた薪割り機が、へなへなとストップしました。
硬い場所や節の部分に当たった時に、エンストするのはよくありますが、そうではないときのエンストは初めてです。
エンジンをかけようと、チョークやアクセルを駆使しても発動しません。
「はい、今年の薪割り作業終了!」。
山小舎おじさんの心の中でファンファーレが鳴り響きました。
甘味な安心感を伴った体の叫びです。
「休憩して、それでもエンジンが作動しなかったら、薪割り機を返そう。」。
休憩後もエンジンは動かず、機械を管理事務所に返しました。
 雪の中の薪割り作業
雪の中の薪割り作業
あっさり今シーズンの薪割りが終わりました。
冬を迎えてからの作業の困難さ、無理さ加減を改めて痛感。
苦しく、冷たい中で、機械のご機嫌を取りながらの作業からの解放を体は喜びつつも、仕事が残った中途半端さも感じざるを得ませんでした。
しかし、まだ最後の仕事として、割り残した玉の山を、隣地から山小舎の敷地内に運ぶ作業が残っています。