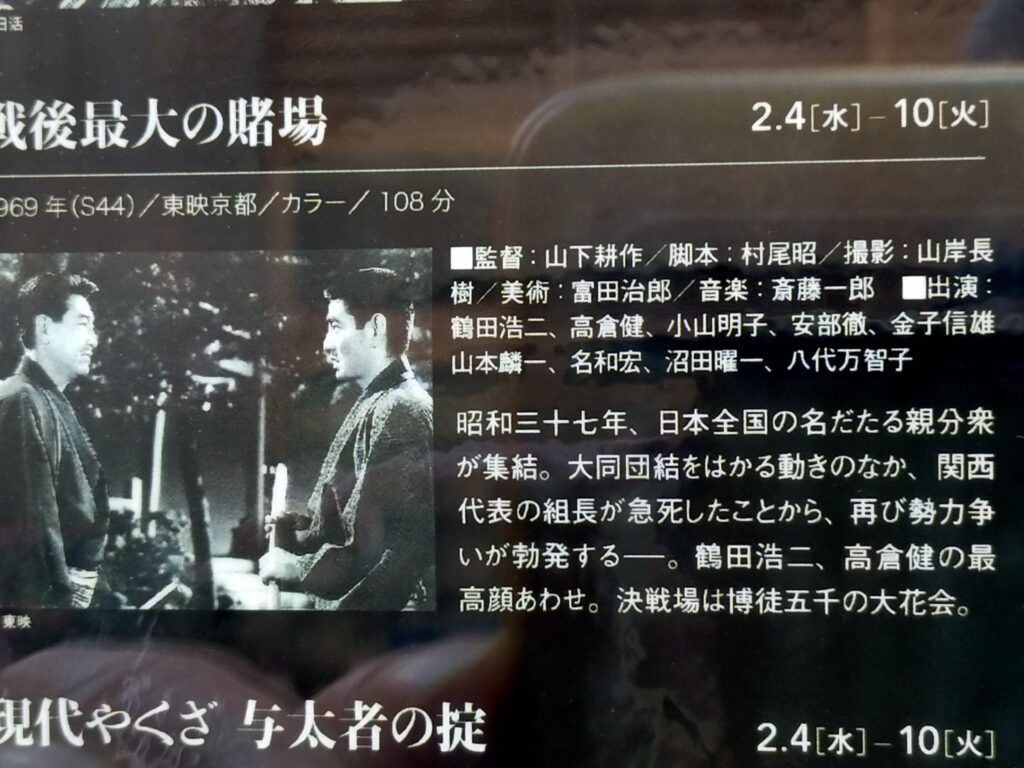ラピュタの「血沸き肉躍る任侠映画・其の弐」の特集上映。
この日は小山明子がゲスト出演する「戦後最大の賭場」に駆け付けました。

1969年の東映京都作品のこの映画は、ラピュタの特集で初めて知りました。
「関の弥太っぺ」(63年)で渡世人と小娘のつかの間の交流を中村錦之助の好演で描き、「博奕打ち総長賭博」(68年)では三島由紀夫に”ギリシャ悲劇にも通じる”と評せしめ、極めつけは東映と山口組の昵懇ぶりを象徴する「山口組三代目」(73年)を任されるに至った山下耕作の監督作品です。
主演は鶴田浩二。
高倉健と山本麟一が助演、悪役は安部徹、金子信雄、名和宏のお馴染みメンバーに、新東宝出身の沼田曜一が抜擢です。
小山明子は鶴田浩二の女房役。
作品の時代背景は昭和37年(1962年)ですから、明治時代のヤクザの女房的な大時代的な味付けはないものの、昭和のヤクザの女房としてのふるまい、男尊女卑、家制度の尊重に徹した女性像を演じます

この時、プライベートでは、小山明子は大島渚の女房。
松竹を、勢い(自らの結婚式で新郎・大島らが松竹首脳を糾弾したため)で退社した後、主婦としてまた二児の母として一家を支え、フリーの女優としても活躍中でした。
フリー後の出演作「続・兵隊やくざ」(65年)では、従軍看護婦役のきりりとした黒い制服姿で、弾避けにと“毛”をねだる勝新をあしらっていました。
本作撮影時は、伴侶・大島作品でいえば「少年」(69年)のメガネの母親役のころ。
赤ん坊をおぶりながら少年に当たり屋行為を強いる役でした。
いずれも彼女のイメージに近い、クールで冷たさのある役処。
1969年当時の実年齢36歳、女優として最盛期のころだったのではないでしょうか。
「戦後最大の賭場」 1969年 山下耕作監督 東映京都 ラピュタ阿佐ヶ谷(35ミリ上映)
この日のラピュタの上映技師は確か女性。
客席から見えるラピュタの映写室内ではテキパキと準備する技師の働きぶりがうかがえる。
プリントの貸出条件が厳しいといわれる、国立映画アーカイブ所蔵作品も、映写技術の高いラピュタではたびたび上映される。
本作は、東映京都のエース監督・山下耕作の最盛期の作品。
「仁義なき戦い」(73年)の出現による実録やくざ映画の台頭を目前にして、さしもの任侠映画の人気も下火になりかかっていたころ。
世の中は、東大安田講堂の陥落が前年で、70年安保闘争も決着がついていた。
本作は、1962年のヤクザの抗争事件を伝える新聞紙面のショットから始まる。
すわ、実録ものの先取りか?
「仁義なき戦い」だったら、センセーショナルな音楽を新聞記事のショットにヒステリックに被せて、物々しいナレーションが社会情勢をドキュメンテルに語りながら物語に入ってゆく導入部となるところ。
ところが山下の作風は全く違う。
新聞紙面のショットによる社会情勢の説明が終ると、何事もなく作り物めいた映画の世界に戻ってゆくのだ。
のちの実録映画では、野外の場面はロケに拘り、例えば警察の手入れのシーンなどでは、急停車したパトカーから警官がバラバラと飛び出す緊迫感のある撮り方をし、何ならストップモーションで切ったその後に騒動場面のスチールショットをつなげるくらいのセンセーショナルな演出が行われるところだ。

山下は、そういった場面でもスタジオ内で、ライトを明るく当てた作り物めいた雰囲気の中で撮っている。
緊迫感やドキュメンタルに拘らず説明に徹した演出だ。
これは山下の特質でもあるのか、東映が右太衛門、千恵蔵ら両御大の”ご存じ”な時代劇が終焉を迎え業績低下。
苦肉の策のアイデア”集団時代劇”が、つかの間流行った頃の作品「大喧嘩」(64年)の田圃の中の決闘シーンの山下演出を思い出す。
様式的な殺陣が飽きられ、殺伐とした抗争場面に活路を求めた集団時代劇にあって、主演の大川橋蔵が必死に田んぼの中を走り回り、ドスを振り回していた、山場の殺陣。
望遠レンズを多用し、ピーカンの田んぼの新緑がフォトジェニックに切り取られた「大殺陣」のハイライト場面。
そこに青春の徒労感は感じられても、殺伐としたヒリヒリ感はなかった。
これが山下の特質かと思った。
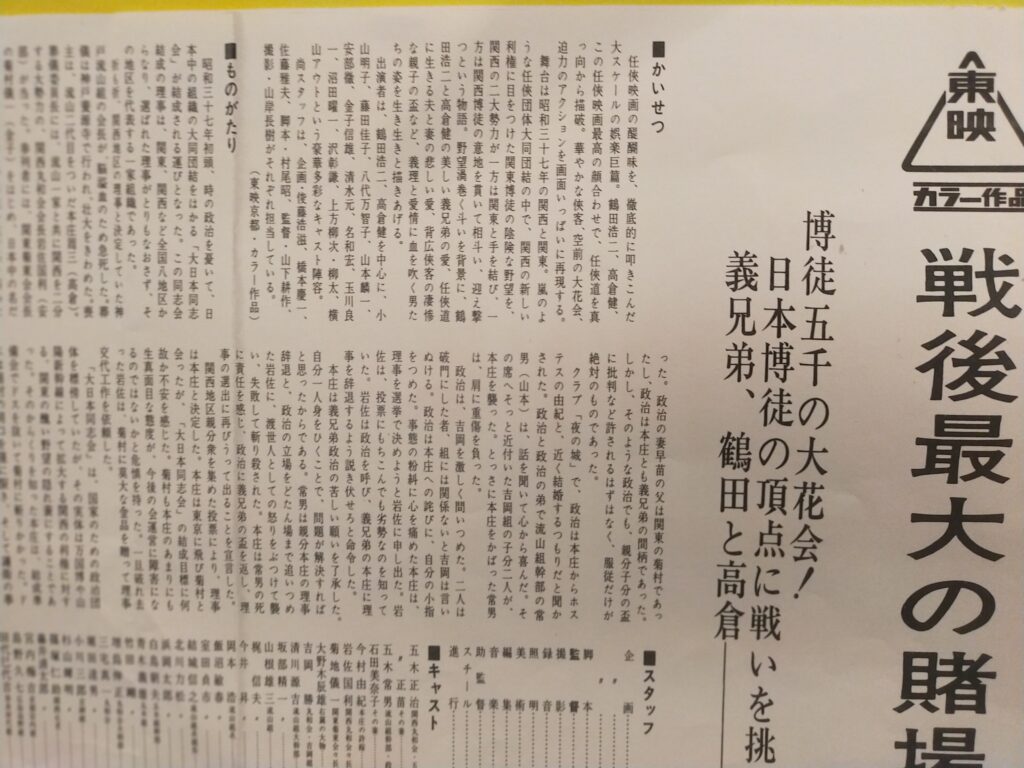
本作「戦後最大の賭場」での配役は、いつもの時代遅れで義理堅い鶴田浩二と、義理との板挟みながら正義を通す高倉健というワンパターン。
悪役はわかりやすいほどの安部徹と、「仁義なき戦い」で吹っ切れる前の中途半端な金子信雄。
最初誰だか分らなかった不気味なキャラ(田代まさしに似ていた)作りの沼田曜一には新味があったが。
一方で、小山明子には映画女優として場数を踏んできた存在感がたっぷり。
これが貫禄というものだろう。
典型的な”よくできたヤクザの女房”的な振る舞いでにこやかに登場し、後半になると組織と個人の板挟みとなって苦労する鶴田に『私は嫁いできたこの家の人間です』と冷静に覚悟を伝え、鶴田に殉じる。
これは、任侠映画に必須の、男尊女卑、家制度尊重、旧道徳観念そもののの女性像であるが、力のない女優が演じると、必死さのみが伝わる(若い女優によるそういったエモーションの発露もいいのだが)演技となる所、凄味さえ伝わってきて納得感がある。
一人仏壇に手を合わせる場面も、何やら妖気すら漂いかねないショットであった。

実録的なセンセーションとは無縁な山下作品にあっては、情念の交流を描くのがその真骨頂。
本作では小山明子の存在が、夫役の鶴田浩二との交流場面でその役割を果たしていた。
彼女がフリーとなった後に各社のやくざ物にたびたび呼ばれてゲスト出演していたものむべなるかなである。