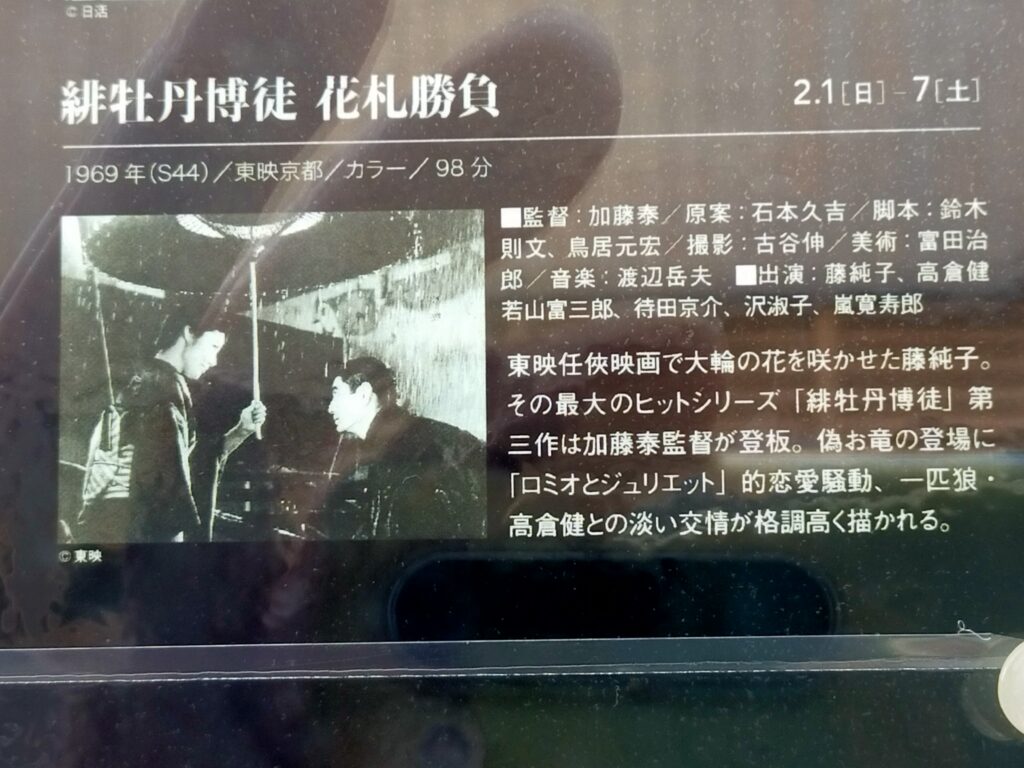2026年最初のラピュタ阿佐ヶ谷では、「血沸き肉躍る任侠映画・其の弐」が特集上映されている。
久しぶりの東京の映画館で35ミリプリントによる上映を楽しみました。

任侠映画というと、東映京都作品のイメージですが、東映東京作品をはじめ、日活、大映、松竹と各社作品を取りそろえたラインナップは相変わらず意欲的なラピュタです。
今回はそのラインナップから、任侠映画の脇を務める女優たちにフォーカスして鑑賞しました。
最初は藤純子です。

「緋牡丹博徒・花札勝負」 1969年 加藤泰監督 東映京都 ラピュタ阿佐ヶ谷 35ミリプリント
「緋牡丹博徒」シリーズは7作品作られた。
ご存じ、藤純子の人気シリーズにして、東映任侠映画の最後の仇花でもある。
加藤泰監督はうち3作品を手掛ける。
最後には藤に「加藤が監督では出ない」とごねられたとのこと。
助監督として、「羅生門」で大映に来た黒澤明に付いたが、喧嘩して下りたというエピソードや、後の自身の監督作品「丹下左膳・乾雲しん竜の巻」(62年)での左膳の隠れ家のセットの念の入りすぎた作り込みを見ても、加藤の性格のこだわりの強さや映画製作時の粘りと入れ込みようがうかがえる。
加藤の諸作品を見ると、そのこだわりぶりが印象的で、そのこだわりは、しばしば映画的な流れや心地よさよりも優先される傾向にある。
修行の旅の途中、義理堅い親分(嵐勘十郎)一家にわらじを脱ぐ、緋牡丹のお竜(藤純子)。
若頭(山本麟一)が何くれとなく面倒を見てくれる。
親分に対抗するあくどい組長(小池朝雄)がいて何かと言いがかりをつける。
緋牡丹のお竜を騙るイカサマ女博徒(沢俶子)がいる。
あくどい組にわらじを脱ぐ旅人(高倉健)がいる。
組同士の抗争、にせお竜の始末、旅人との義理と人情の絡み。
修業の渡世で、義理に縛られつつ、弱者に味方するお竜の意地は貫き通すことができるのか・・・。

本作では、主演の藤の渡世人としてのスーパーヒロインぶりは描かれない。
また藤を取り巻く味方の男たち、高倉健や山本麟一、待田京介そして若山富三郎までもが、人間的な個性の発揮を許されず、ひたすら類型的な”背景”としてワンパターンな演技に終始する。
加藤監督が型通りの任侠の世界を描くことに関心を持っていないことがわかる。
必然的に、緋牡丹のお竜の渡世人としての活躍は、この映画の主題とはなっていない。
では、この作品の影の主人公たちとはだれなのか。
緋牡丹のお竜を騙り、盲目の幼女を抱えながらイカサマ博奕で日陰の人生を凌いでいる中年女と盲目の娘、そしてその娘の別れた父親の、これまたヤクザに便利として使いまわされる、アザを持つ博打打ち(汐路章)の3人なのだ。
監督の思い入れはこの3人についてだけなされる。
名もなく、金もなく、虐げられ、おまけにハンデキャップを持ちながら社会の底辺で生きる3人は、人間としての最後のプライド(他人からの良心に対する義理)をもって死んでゆく。
娘だけは生き残る。
3人に情けをかけ、守ることで、藤が映画の主人公として存在する。
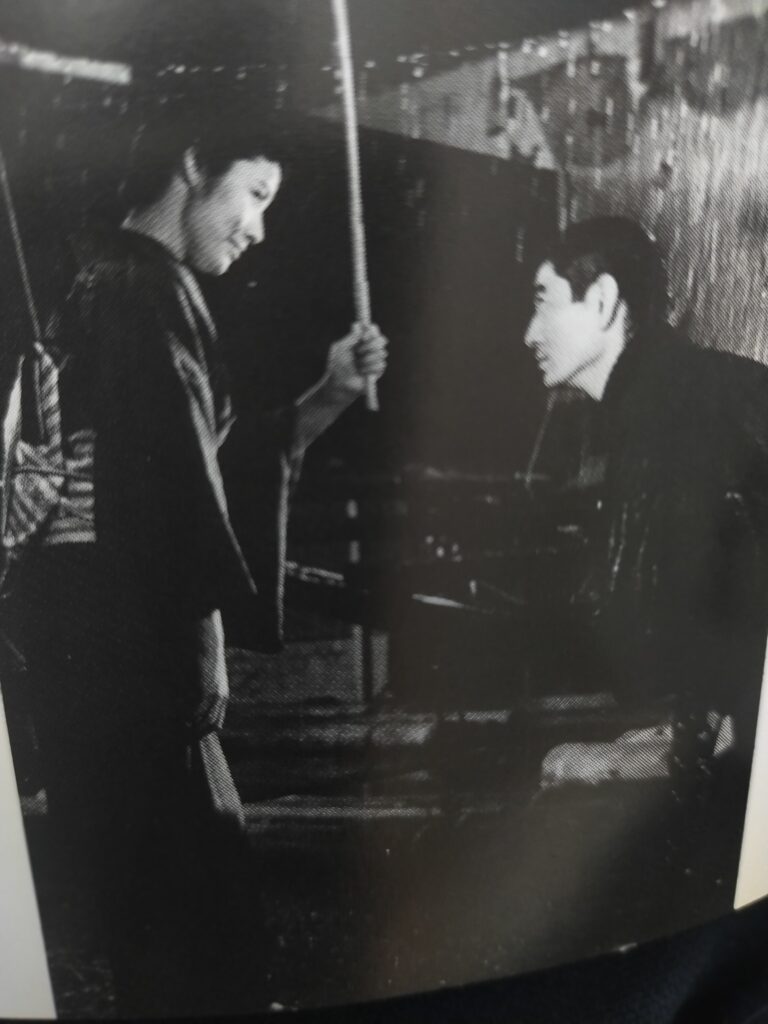
この作品の藤純子は、アクションよりも人間としての誇りと苦悩を表現して心に残る。
若さの残る横顔のクローズアップのあごのあたりに女ざかりを迎える色気と情念がある。
その情念は、底辺をはい回る3人の同情と救済に向けられており、高倉や待田に対する、様式上の任侠美学よりよほど見るものに訴える。
加藤泰の映画的様式には、ローアングルに対するこだわりや、必要以上のセットの作り込み、あるいは極端な描写(「車夫遊侠伝・喧嘩辰」でのコミカルさや、「明治侠客伝・三代目襲名」での鶴田浩二の空中浮遊など)があるが、この作品ではそれが目立たなかった。
東映の看板シリーズとしての制約や、すでに東映の看板監督となっていた加藤自身の成熟もあったのだろうか。
繰り返し出てくる、ガード下の場面。
通り過ぎてゆく蒸気機関車の煙が線路からガード下に湧き下がるシーン。
さらりとこだわったセットの作り込みがよかった。