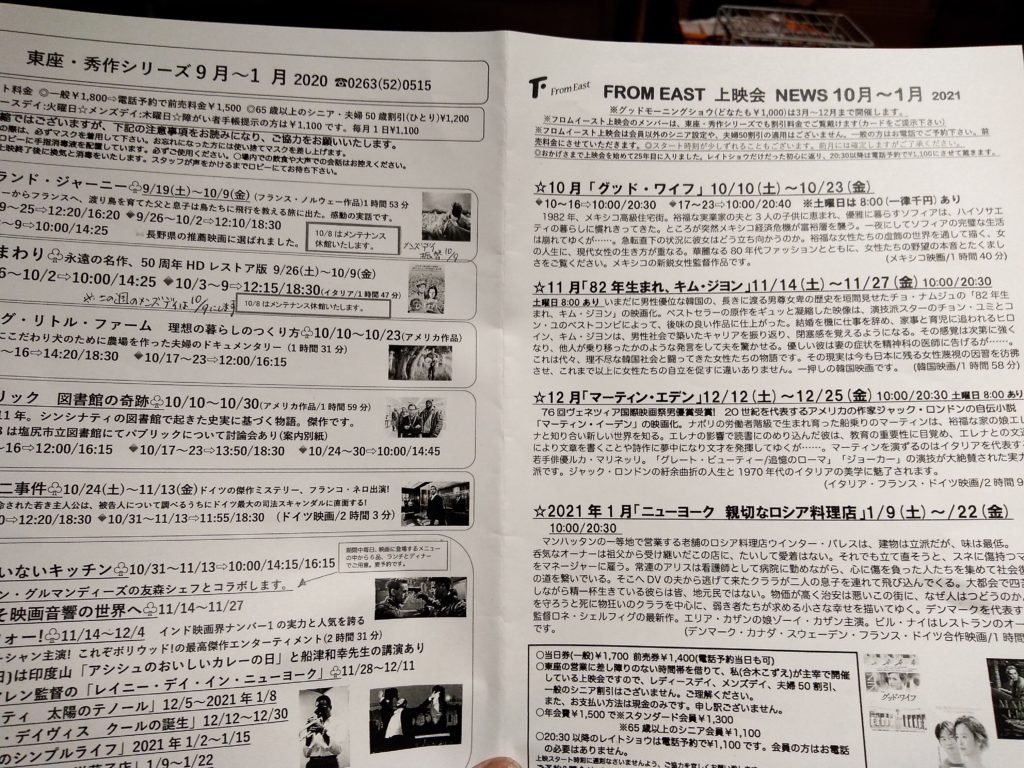塩尻に東座という昔ながらの映画館があります。
シネコンではなく、フィルム上映も可能な、座席数168の映画館です。
1号館、2号館があり、それぞれ一般映画とピンク映画を上映してます。
 「大蔵映画」の看板を掲げる映画館は他に現存しているだろうか
「大蔵映画」の看板を掲げる映画館は他に現存しているだろうか
たまたま塩尻を訪れたときにこの映画館を見つけ、是非一度映画を見に来たいと思っていました。
調べてみると「ひまわり」(1970年、イタリア・ソ連合作)がリバイバル上映中とわかり、改めて駆けつけました。
 一般映画の上映作品はいわゆるミニシアター系が多そう
一般映画の上映作品はいわゆるミニシアター系が多そう
「ひまわり」は、日本公開当時の1970年時点で10代以上の映画ファンなら、誰でも知っているであろう名作です。
ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニという、イタリアでは人間国宝級の二人の共演。
監督はヴィットリオ・デ・シーカ。
戦後直後に、イタリア社会の現実をドキュメンタルに描写した「ネオレアリスモ」と呼ばれた一連の作品群の代表作である、「靴みがき」(1946年)、「自転車泥棒」(1948年)を監督した人です。
デジタル上映でよみがえった名作を見て感じたことを表してみたいと思います。
 館内は傾斜があり、とても見やすい。この回の入場者は6人ほど
館内は傾斜があり、とても見やすい。この回の入場者は6人ほど
その1、イタリア軍のロシア戦線の従軍
「ひまわり」は愛し合った男女の戦争による離別を骨格とした物語です。
イタリアの男は戦争当時、徴兵されることが当然でした。
主人公もそれは覚悟で、徴兵の猶予期間(12日の新婚期間、入営が猶予される)狙いで結婚し、あまつさえ狂言で精神病院へ入院までするのだが、狂言がばれて送られた先がロシア戦線だった。
第二次世界大戦で、イタリア軍も北アフリカでドイツ軍の補助に参加したのは知っていたが、ロシア戦線に従軍したのは知らなかった。
調べてみると計23万人ものイタリア軍がドイツ軍に呼応してロシア戦線に従軍したとのこと。
当初はルーマニア、ハンガリーもドイツ軍として従軍したロシア戦線。
スターリンの圧政に苦しむ当時のウクライナでは、ドイツ軍が「解放軍」として迎えられたとのエピソードが示す通り、複雑かつ混とんとした情勢の中、ソ連軍の反抗と冬将軍の到来に撤退を余儀なくされた時、イタリア軍は15万人になっていたという。
「11人以下の人数の戦い(サッカーのこと)だと強い」「マンマが見ているときだけ強い」などと揶揄されるイタリア男性。
イタリア軍についても、「エチオピアを植民地とすべく攻め込んだイタリア軍が、騎馬と槍で武装したエチオピア軍に何度も跳ね返された挙句、毒ガスを使ってやっと勝った」とか、「北アフリカ戦線で、水不足とSOSを発したイタリア軍部隊に、救援のドイツ軍部隊が駆けつけてみると、盛大にスパゲテイを茹でていた」など、うそか誠か、でも「いかにも」と思わせるエピソードに事欠かない。
ところが、第二次大戦のロシア戦線でのイタリア軍は奮戦したらしい。
ドン川周辺の占領地域の防御戦で再三ソ連軍の反抗を跳ね返し、ソ連軍に「白い悪魔」と呼ばれたスキー部隊もいた、とのこと。
本作での、ロシア戦線での戦闘描写、厳寒の雪原を敗走する場面、戦後になって妻がソ連に夫を探しに行ったときに目の当たりにする、丘一面の無数の白樺の墓標、は決して大袈裟な描写ではなかったのだ。
映画「ひまわり」の歴史的背景描写と史実は決して乖離してはいなかった。
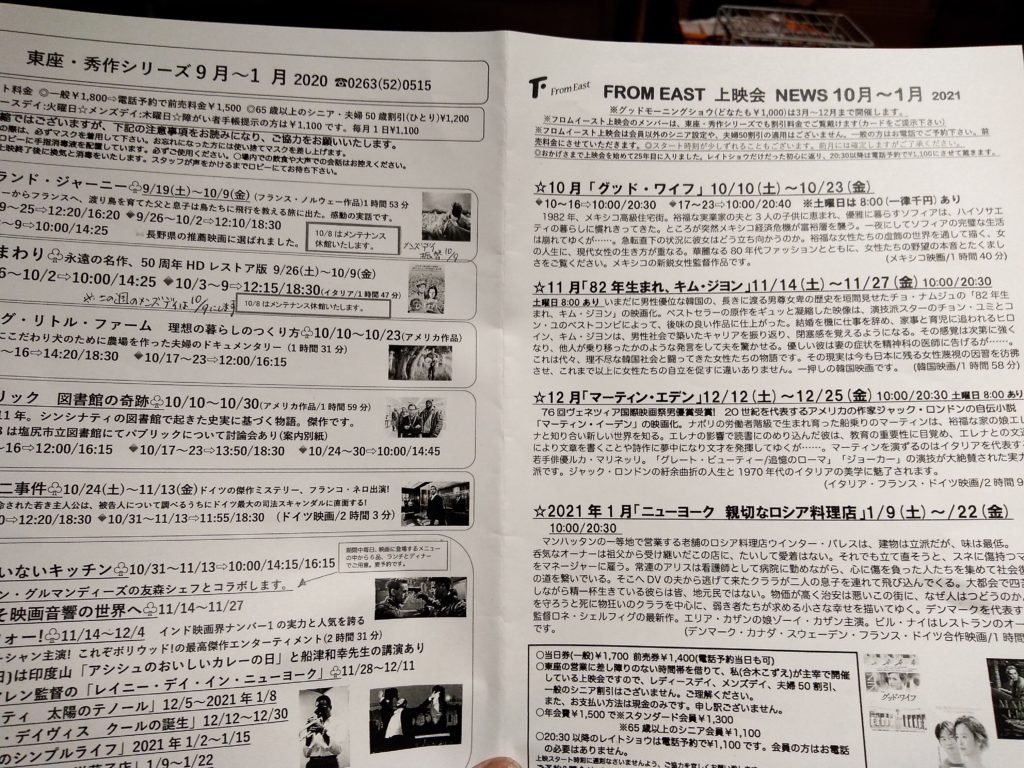 上映予定表。予約割引、メンズデイなどの有益情報も記載されている
上映予定表。予約割引、メンズデイなどの有益情報も記載されている
その2、イタリア映画の豊かな伝統
「ひまわり」は、イタリアの大プロデユーサー、カルロ・ポンテイの製作作品で、ソビエトロケやトップ女優・リュドミラ・サベリーエワの出演など、ソ連との合作によって実現した大作という側面が強い。
一方で、イタリア映画の細かな伝統を随所に感じさせる作品でもある。
【イタリア映画の伝統その1】
主人公二人が新婚時代を過ごす町の広場で三々五々過ごす人々の自然な描写。
駅で出征兵士を送る母親年代の女性達の味のある顔また顔。
イタリア映画のエキストラの存在感。
セリフもないエキストラ達は、アップになっても得も言われぬ存在感を醸し出す。
演技がうまいのか、もともと人々の個性が強いのか。
多分両方なのだろう。
画面を引いて、駅の建物一杯に人々が行きかう群衆シーンになっても画面のリアリテイは失われない。
【イタリア映画の伝統その2】
カメラを固定させ、アップもパンも多用しなかったネオレアリスモの時代の後、イタリア映画に於ける撮影はその技量を高めていったように思う。
質感あふれる引きの構図があるかと思えば、独創的な移動ロングショットがあったりする。
マストロヤンニとサベリーエワの夫婦が都市のアパートへ引っ越すときのトラックを、前面から回り込み助手席のサベリーエワ親子をアップでとらえるまでのワンショットの移動撮影。
カメラマンのよほどのやる気と技術と準備がなければできない撮影だ。
イタリア映画でのエキストラの活かし方と、熟練の撮影は、ベルナルド・ベルトルッチ監督にも引き継がれている。
同監督の「暗殺の森」(1970年)、「1900年」(1976年)では、迫真に迫るエキストラシーンと、見事な撮影を観ることができる。
 ロビーに置いてあるマップ。塩尻の食堂、カフェなどの情報満載
ロビーに置いてあるマップ。塩尻の食堂、カフェなどの情報満載
その3、主題は戦争の悲劇にとどまらず
さて、本作の主題。
ここにもイタリア映画の伝統が強烈に顔を出す。
「ひまわり」という映画のこれまでの印象はというと、山小舎おじさんは「戦争が引き裂いた夫婦の別れ。二人とも運命を受容。悪いのは戦争だ」、というもの。
だからこそのキレイな悲劇の物語。
実はそれにとどまらないのがイタリア映画のしつこいところ。
戦争などで引き裂かれても、イタリア女性はそんなことではあきらめない。
死力を尽くして愛する夫を探し当てる。
女性は、戦争などでは夫への愛を「あきらめ」ないが、反面、夫が別な女性と愛し合っている事実を確認すると、「あきらめ」る。
後に、ソ連からやってきた元夫とイタリアで再会した時も、戦争のせいにする夫を許しはしない。
肉食的というか、頭ではなく体で生きるというか。
イタリア女性の面目躍如。
きれいごとで済まさないところがスゴイ。
それを扱うイタリア映画もスゴイ。
とはいえ、別れた時間は容赦がない。
それぞれに家庭と子供があり、元に戻ることは現実的にはできない、という「落としどころ」に落ち着く。
「ひまわり」撮影時、ソフィア・ローレン34歳、マストロヤンニ46歳。
名コンビとはいえ、新婚時代からを演じるにはギリギリの実年齢。
無理がある?とも思ったが、合作の大作としては必要なキャステイングだったのだろう。
結果としてはリバイバル上映にも十分耐えうる二人の存在感には何も言えない。ソフィアは、若い時と、夫を探すとき、夫を見切ってから、と3つの時代を演じる。
それぞれが素晴らしいが、特に夫をソ連に探しに行ってから見切るまでの時代の演技が素晴らしい。
ソ連で「戦争と平和」のヒロインを演じたこともある、モスフィルムの名花にして、当時のソ連を代表する美人女優のリュドミラ・サベリーエワ。
本役にはもったいないくらいの美貌だが、彼女とてただの悲劇のヒロインではない。
随所に現れる、サベリーエワの人間臭いセリフと動作。
さすがイタリア映画の演出である。
ただの悲劇のヒロインなど一人も出てこない。
随所に現れるマストロヤンニの母親。
息子の行方不明を嘆き、初めて嫁であるソフィアのところへやってきたとき、コーヒーを勧める嫁に、それを断るところ・・・。
人間の描写にいちいち真実をつかないと気が済まない?のがイタリア映画。
これが「人間復興」というものなのか?ルネッサンスの伝統なのか?
一筋縄では行かない大作の「ひまわり」でした。