ヌーベルバーグという言葉を聞いたことがあるだろうか?
フランス語で「新しい波」の意味。
1960年前後のフランス映画のムーブメントを表す言葉として有名だが、そもそもは映画のみならず、当時の新人小説家フランソワーズ・サガンなどと、映画を含む各分野の新人を特集したフランスの雑誌のコピーから派生した言葉だった。
今回、シネマヴェーラ渋谷で「ジャパニーズヌーベルバーグ」として、1960年代の「日本映画の新しい波」の特集上映があった。
何本か見に行ったが、改めて当時の作品群と時代背景に興味をひかれた。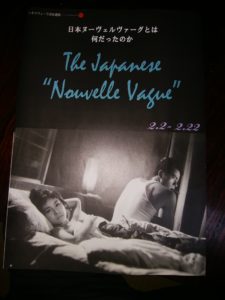
本家ヌーベルバーグのこと
1960年前後のフランス映画の新しい波は、「カイエ・デュ・シネマ」という映画雑誌の若き批評家連中が、実際に映画を撮り始めたことによって起きた。
クロード・シャブロル、フランソワ・トリュフォー、ジャン=リュック・ゴダールなどである。
作品では「いとこ同志」「大人は判ってくれない」「勝手にしやがれ」など。
本家ヌーベルバーグの発生である。
これらの作品はヒットし、作り手たちはこの後も映画監督として制作を続けてゆく。
1960年。
ベトナム戦争がはじまり、フランスが初めての核実験を行う。
5月革命といわれたフランスの文化運動を8年後に控えた時期でもあった。
トリュフォーやゴダールたちは、批評家時代「カイエ・デュ・シネマ」紙上で、アメリカB級ギャング映画や、ジャン・ルノワールを熱心に論じていた。
彼らは、撮影現場では、若い俳優を使った即興演出により、作者の身近な世界を描出する作風を示した。
それは、時代のニーズにマッチしたことから、フランス国内のみならず世界中の映画界の一大ムーブメントとなった。
ゴダールがその後、各分野の文化人にもてはやされる現象も起き、「ヌーベルバーグ」という言葉も「カイエ・デュ・シネマ」の名前も、独り歩きを始め、文化・現象としてファッション化し一部では権威化されるに至った。
1960年前後の日本映画界
産業としての日本映画は1958年に映画人口(観客動員数)11億人の最高を記録、以後減少している(1970年以降は1.5億人前後)。
興行収入は、単純比で、1958年の500億円から、2010年の2000億円に増大。
集客の減少を単価のアップでカバーし、映画産業そのものはしぶとく存続している格好だ。
1958年当時の映画制作会社は、大手6社(東宝、松竹、大映、日活、東映、新東宝)の時代で、各社は直営の撮影所(松竹、大映、東映は東京と京都の2か所)を持ち、各都市に直営もしくはフランチャイズの上映館を持っていた。
各社は制作部門の専属として、俳優、監督と契約し、また製作スタッフ(助監督、撮影、照明、大道具などの現場のスタッフ)を、社員として抱えていた。
1955年ころに、石炭産業と並ぶ花形産業としての映画は、いまだ絶頂期にあった。
その当時、1本の映画には、総勢数十人からのスタッフがついていた。
助監督だけでも1本に4人付くのが普通で、松竹大船撮影所だけで在籍する社員の助監督が数十人いたといわれる。
各撮影所では、月4本から8本の製作本数を抱え、多忙を極めた。
将来のための人材育成をと、1950年代中盤から60年にかけて、松竹だけでも毎年、助監督を公募していた時代である。
ちなみに現在は、東宝、松竹、東映の大手映画会社が自社作品を作るのは、年に何本あるかないか、である。
撮影所スタッフの数は激減し、そのスタッフも大手映画会社の社員ではないことが多い。
その背景には、娯楽の多様化などによる映画人口の減少=映画会社の売上の減少がある。売上が減った会社が生き残るためには、新商品の開発により売上を伸ばすか、あるいは経費を節減しなければならない。
そこで、映画会社は制作部門をリストラし、費用を節減したのだった。
こうして、撮影所が閉鎖され、(松竹、大映は京都の撮影所を閉鎖)、製作スタッフをリストラし、新規採用をストップした。
映画会社の撮影部門は、スタジオ(スタッフを含む)のレンタルや、不動産業、観光業で稼がざるを得なくなった。
もっとも、映画会社として最低限度の上映作品は必要なので、まず、制作部門そのものを別会社化し、映画製作にかかる経済的リスクを会社の決算の外とした。
次に、既存のプロダクション、独立監督などに作品を発注したり、あるいは、プロダクションが製作した作品を買付けた。
なお、大手映画会社から制作を請け負う側も、スタッフ数を、大手映画会社の撮影所時代の数十人から、10人以下にまでに減らし、また、デジタル化やCG化などの技術を取り入れて直接制作費を減らすなど、映画製作にかかる経済的なリスクを軽減しようとしているのが現状だ。
その点、配給事業というものは、契約した額で作品を制作サイドから購入し、興行後は、興行収入から映画上映にかかる諸経費(プリント作成費、宣伝費等)を差し引き、黒字が出れば制作サイドに分配すればいいので、作品が極端に不入りではない限り、経済的リスクは少なく、またヒットした場合の実入りは青天井となる。
こうしてみると産業としての映画製作は、1955年から1960年までのつかの間の全盛期の後、今に至るまで下落し続けているのがわかる。
この衰退は、映画会社本体に及び、1961年の新東宝の倒産、1970年代の大映倒産、1980年代の日活倒産が起こる。
制作、配給も含めた旧来の映画産業が、会社の数で行っても半減したのが半減したのである。
ヌーベルバーグがフランスで発生した、1960年は日本の映画産業の絶頂期の終末期に当たり、衰退の影におびえ始めた頃だったのである。
その時代はまた、戦後15年を経た、世相の転換期でもあった。

日本ヌーベルバーグ前史、松竹大船撮影所の場合
数年前に亡くなったが、大島渚という映画監督がいた。
1954年に京都大学から松竹大船撮影所に入社。
同じころ、吉田喜重、山田洋次(いずれも東大卒)が入社している。
大島は、晩年は海外のプロデューサーと組み、世界と商売をしたカリスマ性を持つ人材だったが、松竹の社員時代に4本の映画を残した。
「愛と希望の街」(59年)から「日本の夜と霧」(60年)に至る、アグレッシブで時代批評性に満ちた作品群。
特に、「青春残酷物語」「太陽の墓場」(いずれも60年)の2本はヒットし、折からのフランス映画の新しい波現象を受けて、マスコミ的にも「ヌーベルバーグ」と呼ばれた。
1959年当時27歳の大島が、チーフ助監督の経験もないのに監督に昇進できたのは、シナリオの執筆力もあったにせよ松竹首脳やマスコミに対するアピールを含む政治力に優れていた理由のほかに、映画界を取り巻く外的理由があった。
すなわち、1958年をピークとする映画人口の減少は、事業会社としての映画会社を直撃し、特に小市民的なホームドラマを路線としていた松竹において、新しい作風、路線、新しい作り手を模索せざるを得なかった。
それが時代の流れだった。
実際、この流れに沿って松竹で監督昇進した当時30歳前後の助監督には、大島のほか吉田喜重、田村孟、高橋治、斎藤正夫、森川栄太朗、篠田正浩などがいた。
全員、1955年前後に猛烈な倍率をかいくぐって入社した有名大卒者であったし、入社後はシナリオ執筆などで実力と意欲をアピールした連中だった。
この一群は、旗手・大島の2本のヒット作の影響もあり、会社の抜擢によって次々に作品を発表したが、大島が1960年に制作した「日本の夜と霧」が、上映4日間で打ち切られ、かつ大島がその件について松竹を批判し、挙句、同調者を引き連れて松竹を退社したことによって急激に退潮した。
「日本の夜と霧」は安保闘争現場を舞台とし、新左翼の視点から旧左翼を批判した学生演劇のような作品で、ヒットしなかったのは当然。
今では、若き大島の熱気が商業映画撮影所の中で実現した記念碑的な意味を持つ作品と評価が定まっているが、当時の(そして今も)映画会社松竹としては扱いに困る作品だったろう。
権力側をはじめ、右翼、旧左翼など各方面からいちゃもんをつけられる可能性が高い作品を、ヒットしないことを理由に打ち切ったのが実情だった。
大島にとっては確信犯的に自分の主張のみを前面に押し出したのだった。
結果として大島のみならず、ヌーベルバーグの旗のもとに売り出された少壮監督の全員が松竹を去ることになる。
大島、吉田、篠田はのちに独立プロを起こして映画省察を続け、田村は大島が起こした創造社の一員に、高橋は小説家に、斎藤と森川はテレビに移っていった。
彼ら全員が、大島のように自己プロデュース力にたけたアジテーターであるというわけではもちろんなかった。
総括、日本ヌーベルバーグの時代とは?
発生
(時代の要請)
映画人口の減少の中、映画会社の旧路線では集客がじり貧で、新しい路線を求めた。
新しい路線とは、時代を背景とした生々しく、刺激的で、若々しい感性に満ちたものでなくてはならなかった。
世の中は、安保闘争、ベトナム戦争に揺れ動いていた。
(人材の登用)
・1955年前後に一般募集で入社した優秀な人材が助監督経験を経て30歳前後となっていた。
彼らは監督昇進を目指し、シナリオ発表などで意欲と実力をアピールしていた。
何より、現代社会の問題性に肉薄し、また若者風俗や気分を取り入れた画面作りに意欲的だった。
・この現象は松竹のみならず、東宝、大映、日活でも同時代的に発生し、岡本喜八、須川栄三、恩地日出夫、増村保造、中平康、今村昌平らがデヴューした。
総括
・日本ヌーベルバーグとフランスヌーベルバーグは、時期と気分を同じくする(いわゆる同時代性を持つ)が、別の土壌(かたや映画撮影所、かたや映画批評)から発生。
・映画の技法的な面(カメラの移動、長回し、ロケ、同時録音の多用、若手俳優の抜擢)などは、日本のみならず、世界がフランスの影響を受けて、継承している。
・日本ヌーベルバーグの場合、映画撮影所が、有能な若手人材を抱え、育て、発表させることにより実現した。
彼らの残した稚拙であるが若く熱気ある作品を見るにつけ、意欲的な作り手と映画会社の歴史上の幸運な邂逅を再確認するという喜びを感じざるを得ない。
大島の全4作品、田村孟の「悪人志願」(60年)、恩地日出夫の「若い狼」(61年)、山際栄三の「狂熱の果て」(61年)。
映画会社が映画製作の現場を含有していた時代の奇跡のような一瞬の輝きだった。
この輝きは1960年だったから可能で、これ以前もしくは以降の日本映画界では実現不可能だった。
日本におけるヌーベルバーグの時代は1958年に始まり、1961年に終わった。







































 (かつて駅の入り口だった場所)
(かつて駅の入り口だった場所)





















 皮製品、帆布、木製品などのショップです。
皮製品、帆布、木製品などのショップです。


























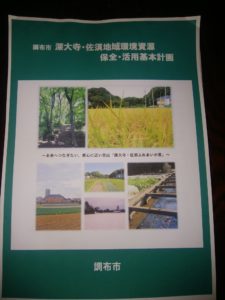


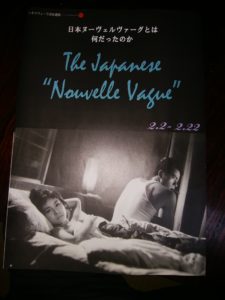










 左手が場外馬券売り場、右手がかつて浅草名画座など映画館3軒があった場所。
左手が場外馬券売り場、右手がかつて浅草名画座など映画館3軒があった場所。












 五色不動尊の一つ。目黒が地名になり有名です。
五色不動尊の一つ。目黒が地名になり有名です。











