山小舎おじさん、9月初旬にも自宅に帰りました。
その際、渋谷シネマヴェーラで「サンセット大通り」をやっていたので見てきました。
ここのところ気になっているビリー・ワイルダー監督の1950年作品です。
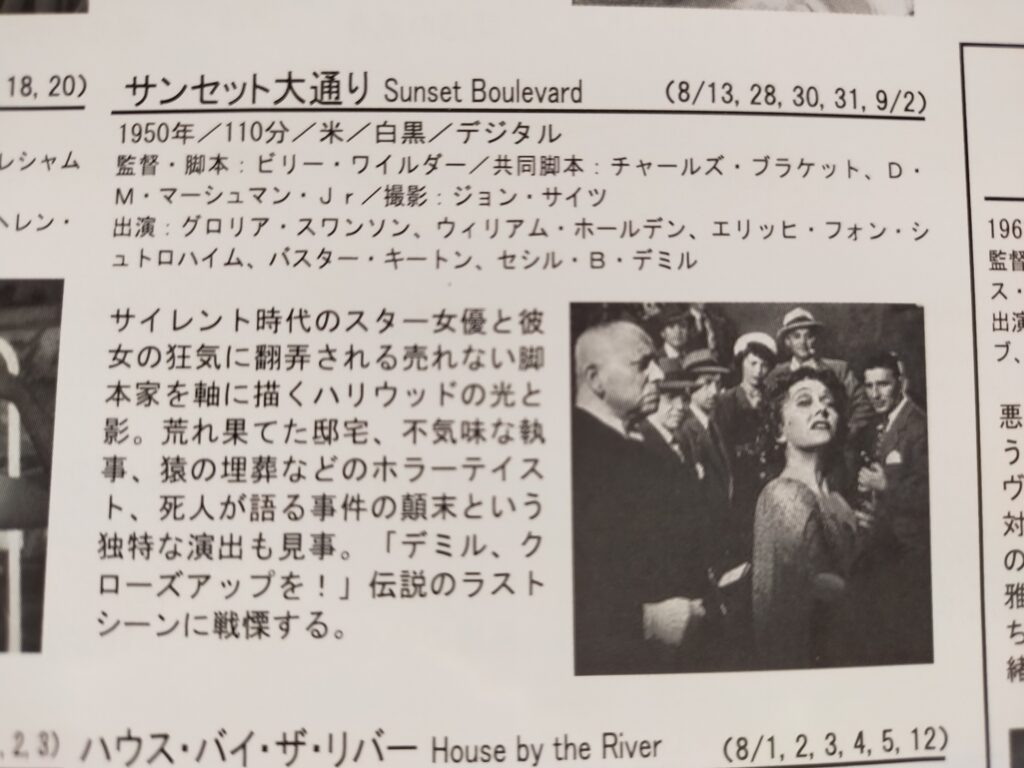
アメリカ映画は暴露ものが好きなのか?
「サンセット大通り」は名監督ワイルダーの代表作の一つ。
40年代から活躍し始めたワイルダーが評価を不動のものした記念碑的な作品でもあります。
ストーリーはサイレント時代の大女優が、時代がかった執事(往時の名監督で最初の夫でもあった、という設定)とハリウッド近郊の古い邸宅の中で暮らしているところへ、ひょんなことから売れないシナリオライターが迷い込み、大女優の妄執に翻弄された挙句、悲劇の結末を迎えるというものです。
大女優役は実際にサイレント時代のスターだったグロリア・スワンソンが扮し、執事役には実際にサイレント時代の名監督だったエリッヒ・フォン・シュトロハイムが扮しています。

これって、いわゆる「暴露もの」ではないでしょうか。
そうじゃなかったら「あの人は今」的な「のぞき見」もの。
アメリカ映画には「市民ケーン」(1941年 オーソン・ウエルズ監督)で当時の新聞王ハーストを批判的に描き、「独裁者」(1940年 チャールズ・チャップリン監督)で当時の対立世界の覇者ヒトラーをカリカチュアライズした、という「実績」があります。
当時のハーストを扱うということは、現代でいえは、ステイーブ・ジョブスだったりビル・ゲイツといった億万長者兼実業界のカリスマの裏面を暴くようなものでしょう。
また当時、勃発中の第二次大戦の主役の一人だったヒトラーを馬鹿にすることは現在でいえば習近平やプーチンにケンカを売るようなものでしょう。
その点、ワイルダーの「サンセット大通り」はすでに名声時代が過ぎ去った主人公たちを扱っています。
本人たちが納得ずくで没落した人物を演じるのですから、名誉棄損の批判を受ける心配もありません。
ワイルダーの狡さというか意地悪さが見て取れるのは私だけでしょうか。
主人公二人のほかに、セシル・B・デミル、バスター・キートン、ヘッダ・ホッパーなどの映画人を実名で登場させ、ヴァレンチノ、グリフィスなどの実名をセリフで言わせていますが、そこでは抑えた演出をしています。
ワイルダーにとっての暴露すべき悪とは
ワイルダーの演出は、主人公二人(スワンソン、シュトロハイム)については、暴露もの的な意味で、デミル、キートンについてはあの人は今的ない意味で使っています。
スワンソンとシュトロハイムに関しては思いっきりイジワルな演出をしています。
が、ワイルダー自身にはほとんど危害が及ばないところがミソです。
後で述べますが、結果としてスワンソン、シュトロハイムに関しては悲惨さよりはアイコンとしての貫禄が画面から漂い、ワイルダーの毒というか本心は露骨に表れない、という結果になっています。
表面には現れませんが、ワイルダーがケンカを売りたかったのは、ハリウッドシステムの尊大な滑稽さで、大女優と執事はその犠牲者という位置づけだったのかもしれません。
ワイルダーにとって本当の敵とは何だったのか?
祖国からの亡命を余儀なくさせたナチスドイツか?ユダヤ人という宿痾か?尊大で欺瞞に満ちたハリウッドシステムか?
それぞれのテーマをある程度は匂わせながら決して肉薄しないのがワイルダーです、隠しきれない毒は画面のそこかしこに現れてはいますが・・・。
ワイルダーは正義派でも社会派でもありません。
良い作品ができる題材と、多少は自分の毒が満足できる演出ができればそれでいいのでしょう。
自分に危害が及ばないのなら、他人の尊厳、プライバシーを犯すことに良心の呵責はありません。
1950年制作の「サンセット大通り」まではそれでも際物的な要素のも取り入れながら作品を作っていましたが、名声を得た50年代以降は際物的な要素は少なくなってゆきます。
「サンセット大通り」は転換期に当たる作品なのではないでしょうか。
グロリア・スワンソン
なお、暴露ものというジャンルはアメリカ映画の専売特許ではありません。
日本映画には権力者を批判的に描く骨のある暴露ものの作品はあまり思い浮かびませんが、実録もの、事件の再現ものなどのジャンルがあります。
事件の再現ということでは、あの阿部定がのちに座長として巡業したとか、アナタハン事件の後で事件の女主人公が再現劇で巡業したなどの話を聞きます。
暴露ものがあらゆるメデイアにとって親和性のあるジャンルということがわかります。
「サンセット大通り」の表面上のモチーフの「年増女が若い燕に狂って破滅する」は、2時間サスペンスや、ワイドショーのネタ、ドリフのコントのネタ、などとして綿々と受け継がれてもいます。
事実この作品を見ていて、コントみたいだと思った瞬間がありました。
それを防いだのはグロリア・スワンソンの存在そのものでした。
老醜、妄執がコンセプトの大女優役に於いて、当時50歳のスワンソンが実に魅力的だったのです。
まだまだきれいで、いわゆる怪奇派としての老嬢役に収まりきらない魅力が垣間見れるのです。
自分が所属していたマック・セネットの水着ガールやチャップリンの物まねまで再現、披露します。
ワイルダー演出は老嬢の若作り、悲惨さを狙ったのかもしれませんが、さすが往年のスター。
演技がしっかりしており、ポーズも決まるので単なるカリカチュアにとどまらないスワンソンの演技に、山小舎おじさん、魅入ってしまいました。
ストーリーの間に挟まる、若い燕・ホールデンと若い女性の逢引のシーンの方が70年前のアメリカ映画の古臭さを隠しきれないのに対し、スワンソンが出てくるシーンは時間が超越されているようでした。
本物は、類似品がのちにテレビのコントになって消費される時代が来ても古典として残るのだなあと思いました。
スワンソンの演技は、暴露ものという映画の設定を突き破り、自身のキャリアの尊厳を逆説的に主張しているかのようでした。
その点が作品に深みと救いをもたらしてもいます。
それがワイルダーが最初から意図したものだったかどうかはわかりません。

