山小舎暮らしで映画に飢えている昨今。
古本屋で見かけた100円のDVD。
こんなに安く映画が見られるんだと思った。
ブックオフに行って見るとDVDのコーナーがある。
よく見ると500円以下の廉価コーナーもあり、古の名作が安く販売されている。
山小舎でも映画が見られると気が付き、廉価版を中心に集めてみた。
山小舎版名画劇場という塩梅だ。
ジーン・アーサーは1930年代に活躍したアメリカ女優。
セシル・B・デミルやフランク・キャプラといった巨匠作品で、ゲーリー・クーパーやジェームス・スチュアートらと共演した。
彼女の30年代の出演作4本プラスアルファを続けて見た。

1,「平原児」1936年 パラマウント映画 セシル・B・デミル監督
パラマウント映画のタイクーン、アドルフ・ズーカーを先頭に、製作、監督、出演者名が画面下から上に、斜め後方に流れてゆくクレジットタイトルで始まるこの映画。
このタイトル方法は「スターウオーズ」がのちにマネをした。
西部の大立者、ワイルド・ビル・ヒコックとバッファロー・ビルの友情に、カラミテイ・ジェーンが絡むという、日本でいえば、〈ご存じ次郎長三国志〉のような物語。
大向う受けを狙ってハリウッドのタイクーンが企画し、国民的巨匠のデミルがタイクーンの意を受けて現場を仕切って作り上げた作品であり、また、正攻法で作られた大作の楽しさに満ち満ちた作品である。

ジーン・アーサー扮するカラミテイ・ジェーンは男勝りの西部の女。
ゲーリー・クーパー扮するワールド・ビル・ヒコックを見かけるなり、抱きついていきなりキスする登場シーン。
男勝りながら純情なカラミテイは、ビル・ヒコックへの追慕を隠さない。
健気でガラッパチながらも、かわいらしいカラミテイのキャラクターは、ジーン・アーサーのイメージに重なっており、愛らしい。

南北戦争が終わり、ガンマンだのバッファロー狩りだのの時代は終わりつつあり、インデアンとの戦いにも先が見えてきている。
遅れてきたガンマン二人のストイックな時代遅れの友情と、彼らを追慕する独立心にあふれてはいるが純情な女性像。
古き良きアメリカへの賛歌であり挽歌でもある。
ロケの群衆シーン、騎兵隊とインデアンの戦闘シーン、その全部がエキストラを使って再現されている。
今の時代では不可能なぜいたくさであった。

2,「オペラハット」1936年 コロンビア映画 フランク・キャプラ監督
西部の男勝りから一転して、ニューヨークのマスコミのキャリアウーマンを演じるのがこの作品のジーンさん。
都会的でスレていて、てきぱきと事を進める役もジーン・アーサーには似合っている。

相手役は、まだ若さが残り、イノセントな田舎者の役が似合っていた頃のゲーリー・クーパー。
イノセントな田舎者のクーパーが、遺産相続で都会に出てきて、狡猾な都会人に騙されようとするが、クーパーは信念の人でもあり、自らの人間性を頼りに、悪漢たちを退け、女性の愛も獲得する、という物語。

田舎で、〈妖精つき〉ともいわれた純朴、マイペースの変人ぶりをクーパーが好演。
すれっからしのジーン・アーサーが、この田舎者をネタにマスコミではやし立てるが次第にクーパーの本質に惹かれるというシンデレラストーリー。
クーパーの田舎では全員が〈妖精つき〉だというオチもつく。
ジーン・アーサー全盛期の美貌を堪能できる。

3,「我が家の楽園」1938年 コロンビア映画 フランク・キャプラ監督
続いてもキャプラ監督作品で、ジーンさんの相手役は若々しいジェームス・スチュアート。

スチュアートは大企業の御曹司で副社長だが、買収を繰り返す企業戦士の親父社長とは正反対の性格。
都会に生まれた〈妖精つき〉。
ジーン・アーサーは副社長の秘書で仕事はできるがスレてはいないキャラクター。
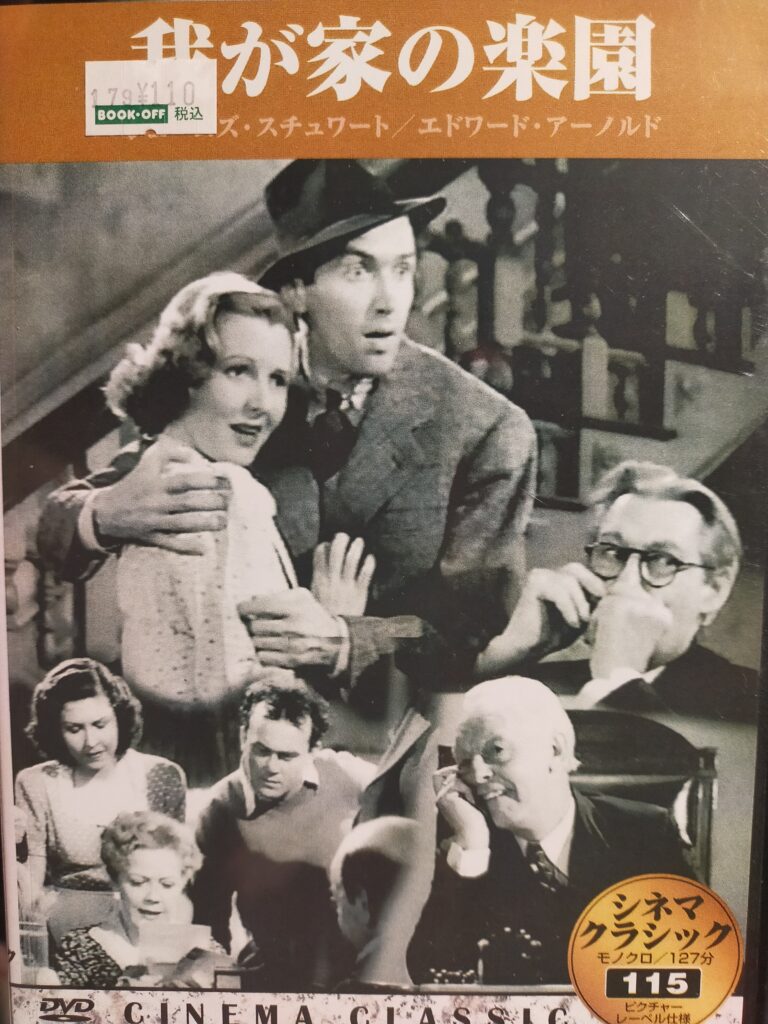
この二人が惹かれ合って、ジーンさんの実家へ挨拶することとなった。
ところがこの実家、企業戦士を退職してから自分に正直に生きている祖父を中心に、自分に正直すぎる人々が集まっているシェアハウスのような場所。
スチュアート自身は、通じるものを感じるが、ゴリゴリの現役企業家である父親を連れての再訪では、お約束通りの大混乱と相成る。
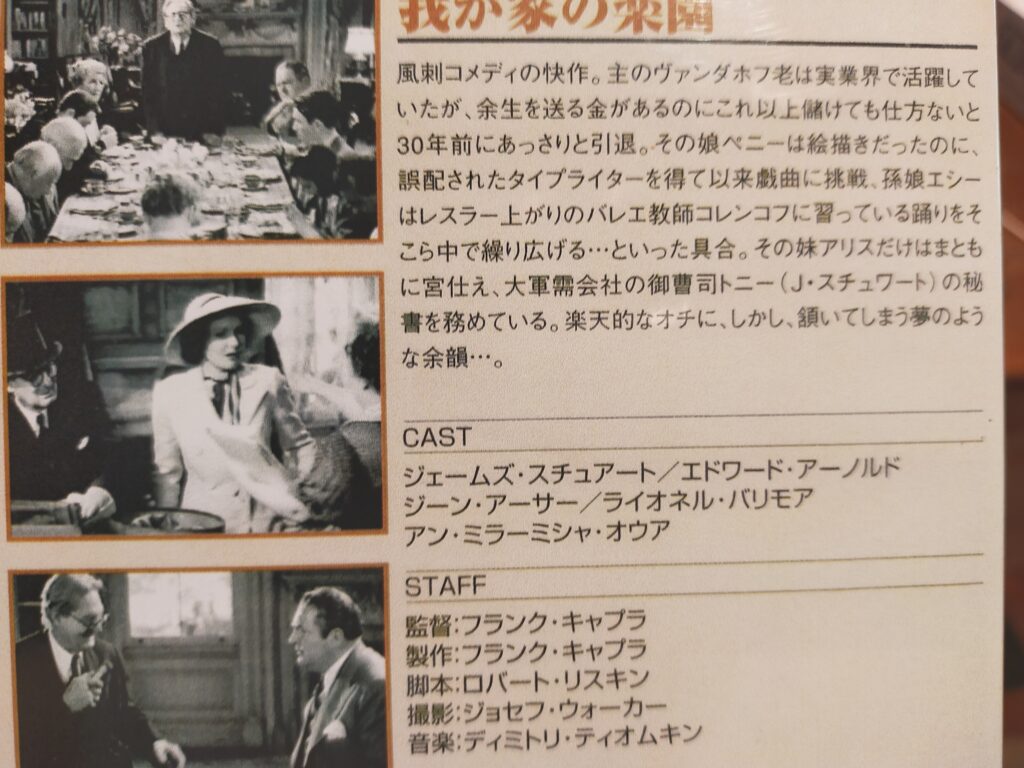
この作品でのジーンさんは、都会人ながら純情一方のキャラで、だからこそ役柄に屈折がなく、印象が薄いものの、〈妖精つき〉の相手役に惹かれる役柄という点では、ほかのキャプラ作品同様であり、彼女一流のイメージに合っている。
まさに現代のおとぎ話。
これがキャプラタッチというものなのだろうか?
ジーン・アーサーのおとぎ話のヒロインぶりも一興。
4,「スミス都へ行く」1939年 コロンビア映画 フランク・キャプラ監督
キャプラ作品が続きます。
ジーン・アーサーが出演したキャプラ監督の上記3作品。
コンセプトは共通していて、〈妖精付き〉のヒーローを、実は純真な心を持つヒロインが支える、という設定です。

この作品は、まだおどおどした演技が似つかわしかった頃のジェームス・スチュアートが田舎から補選の上院議員としてワシントンに上京し、政治の現実に夢破れるものの、最後に上院で自らの思いのたけを延々とぶちまけて信念を通すというお話です。
ジーン・アーサーは上院議員秘書を演じて、当初は田舎者のスチュアートに失望するものの、その信念を通す姿に味方となって助けます。
政治の世界の裏も表も知って、仕事はできるが疲れも出始めている、議員秘書の感じをよく演じています。

〈妖精つき〉で最後は己の信念を貫き通す主人公と、彼を陥れようとする〈私利私欲の〉勢力の対決、という構図は「オペラハット」と同じですが、この作品の方が、〈私利私欲の〉勢力の描き方がより強烈でリアルになっています。
したがって、陥れられる〈妖精つき〉主人公の追いつめられ方もより深刻で、切羽詰まっています。
とはいえ、ベースにはユーモアがあり、例えば上院議長役のハリー・ケリーの、世の中の正義もインチキもわかっているかのような議事進行ぶりと、馬鹿正直な主人公に一服の清涼剤をもたらすかのような仕草など、観客にとってもユーモラスな息抜きとなる演出です。
また、「我が家の楽園」ではジーンさんとスチュアートのデートシーンに流しの子供楽隊が急に現れ、見るものを驚かせ、喜ばせますが、本作では本格的な子供のマーチングバンドが要所で登場し、大々的に主人公たちを〈応援〉し、またまた見るものを驚かせます。
キャプラ監督一流のユーモアに満ちた前向きな場面転換のテクニックの炸裂です。
ジーン・アーサーは「オペラハット」同様、ラストの議会(この作品では法廷)での主人公の懸命な自己発露を女神のように見守り、励まします。

番外、「シェーン」1953年 パラマウント映画 ジョージ・ステイーブンス監督
ジーン・アーサーの存在感については、全盛期の30年代の上記作品より、この作品において一番重く感じるのは邪道だろうか。
最後の映画出演、彼女50歳前後の作品である。

この作品のジーンさんは、表立って主張しない。
30年代の懐かしい彼女の横顔。
微笑んで、目をキラキラさせる。
がみられるのは、独立記念日のお祭りに切るドレスを選んで、長持ちの底からウエデイングドレスを見つけるときのシーンくらい。
後は、ひたすら自分の夫と、息子と、特にシェーンを見守り、料理し、喧嘩の手当てをし、ひそかに思いを寄せる。
自分の意志を表示したのは、息子に「シェーンを好きになったらだめよ。いつかいなくなるのだから」といったときと、最後に夫がガンをもって対立する悪徳牧場主に殴り込みに行こうとするときに「私のために行かないで」という時くらい。
シェーンとの別れの場面でも、「もう会えないのね」「死なないで」と言って万感の握手をするだけだった。

ガンマンがもう流行らなくなり、そのことを自分が一番理解しているシェーンもまた、ひたすら堅気(開拓民)の一宿一飯の恩義に感謝しつつ、自分を殺している。
感情を発露したのは、悪漢の牧場主に「(開拓民の家で働く目的は)女房か?」とある意味図星の指摘を受けたときに「黙れおいぼれ」と悪態をついた時だけ。
男として、時代遅れのガンマンとしての矜持を貫いたのは、前半で悪徳牧場主一味に挑発され、一度は引き下がったものの、再び酒場でまみえたときにウイスキーを浴びせ返して殴り合いになった時と、最後に殴り込みに行こうとするヴァン・ヘフリン(ジーン・アーサーの夫)を力づくでひきとめたとき。
力ではもう、ヘフリンに敵わなくて、ガンで殴って気絶させ、彼の馬を追い放ち、拳銃をジーン・アーサーに隠すように託す。
40年代にスターとなり、素早い動きでギャング映画で一時代を築いたアラン・ラッドも俳優としては晩年。
低い身長を隠すこともなく、ラブシーンもなく、正体不明の中年ガンマンとして流れ着き、去っていく役を寡黙に演じきった。
時代遅れではあっても、己の信念と人間としての矜持を貫く役柄は、現実のラッドの俳優人生ともオーバーラップし、思い残すことはないだろう。

ジーン・アーサーも中年となり、母親役を演じた。
往年のこぼれ出るような色気は封印しても、控えめに大事な存在を見守り、平和を説き、バックアップする女性像を、彼女の女優人生の集大成として演じた。
映画人生最後の役柄は、心ひそかに愛するヒーローを見守る以上のことはせず、最後までキスもしないヒロイン役だった。
監督のジョージ・ステイーブンスは十分なリスペクトをもって彼女を演出した。
余談
ラストのジャック・パランスとの決闘シーン。
酒場のカウンターに寄りかかったシェーンとパランスは2,3のやり取りをする。
シェーンはパランスを挑発して応える。
「うそつきの卑怯者」と。
パランスは「抜け」と応じる。
この時のシェーンの言葉。
山小舎おじさんが中学生の時にリバイバルで観た版では「南部の豚野郎」だったと記憶している?!
今回見たDVDで原語を確かめると「なんとか・ヤンキー・ライヤー」と言ってる。
ライヤーはうそつき、最も相手を否定する言い方だ。
ヤンキーとは、アメリカで南部の住民が、北部の住民を軽蔑して呼んだ言葉だそう。
とすれば「北部の嘘つき野郎」が直訳である。
では山小舎おじさんの記憶にある「南部の豚野郎」とはいったい?
山小舎おじさん得意の記憶違い、なのか?
やっぱりそうなのか。
南部と北部の対立は歴史的にも根深い宿命的なものがありそうだ。
この作品の制作当時にあっては、南北戦争勝者の北部(北軍)に対する批判はタブーだったろう。
ということは、このシーン、ぎりぎりの北軍批判だったのか?
ちなみに、インデイアンなどに対する北軍のふるまいや、北軍そのものの程度の悪さなどは、のちの「ソルジャーブルー」(1970年 ラルフ・ネルソン監督)や「ダンスウイズウルブズ」(1990年 ケビン・コスナー監督)に描かれた通りなのだろう。
「シェーン」にとって南北対立はどのような意味を持つのか?
