今回はルネ・クレールの「奥様は魔女」とマックス・オフュルスの「忘れじの面影」。
第二次大戦時にドイツ、フランスからアメリカに渡った両監督がハリウッドで作った名作です。
「奥様は魔女」 1942年 ルネ・クレール監督 ユナイト
クレジットにはルネ・クレールプロダクション製作、とある。
さすがは戦前のフランス映画界において、ジャック・フェデー、ジャン・ルノアールと並んで三巨匠と呼ばれた名監督だけある。
ドイツから逃れてきたユダヤ人監督たち(フリッツ・ラング、ロバート・シオドマク、マックス・オフュルスら)とは待遇が違ったようだ。
クレールがハリウッドで選んだ題材は「奥様は魔女」。
山小舎おじさんの世代だと、「旦那様の名前はダーリン、奥様の名前はサマンサ。二人はごく普通の恋をし、ごく普通の結婚をし・・・ただ一つ違うのは、奥様は魔女だったのです」のナレーションで始まるアメリカ製テレビドラマの「奥様は魔女」の方が馴染みがあるが、ルネ・クレールの本作がオリジナルである。

とにかく魔女役のヴェロニカ・レイクが可愛い。
40年代が全盛のハリウッド女優で、アラン・ラッドとの共演でフィルムノワールっぽい犯罪映画に出ていた。
現代のおとぎ話である本作では、浮世離れした魔女のキャラクターにぴたりとあてはまり、天然にコケテッシュな振る舞いと豊かな金髪で、現世の人々をきりきり舞いさせる。
きりきり舞いさせられる、現代の人々にフレデリック・マーチとスーザン・ヘイワード。
特にヘイワードはマーチと結婚寸前の花嫁(田舎議員であるマーチの後援者の有力新聞社社長の娘。ワガママで鼻持ちならず、婚約者のマーチをバカにしている)役で、結婚式の段取りの悪さにかんしゃくを起こしたり、観客の前でだけ無理な笑顔を作る演技がケッサク。

クレールの演出は、正攻法で奇をてらわず、しかもユーモアを欠かさない。
全編を覆う、いい意味での緊張感のなさは大監督の悠々迫らぬ余裕のなせる業か。

エピローグのシーン。
結婚したマーチとレイク。
子供が4人ほどいる。
女の子がホーキに乗って遊びたがるのをマーチ扮する父親が注意するが、レイク扮する母親は、さすが魔女の子孫と気にもしない。
この場面を見て、のちにテレビ版「奥様は魔女」が作られたわけがわかるような気がした。
典型的な中流階級の家庭に潜む秘密をベースにしたコメデイというコンセプトこそ、無限のエピソードの源泉だろうからだ。
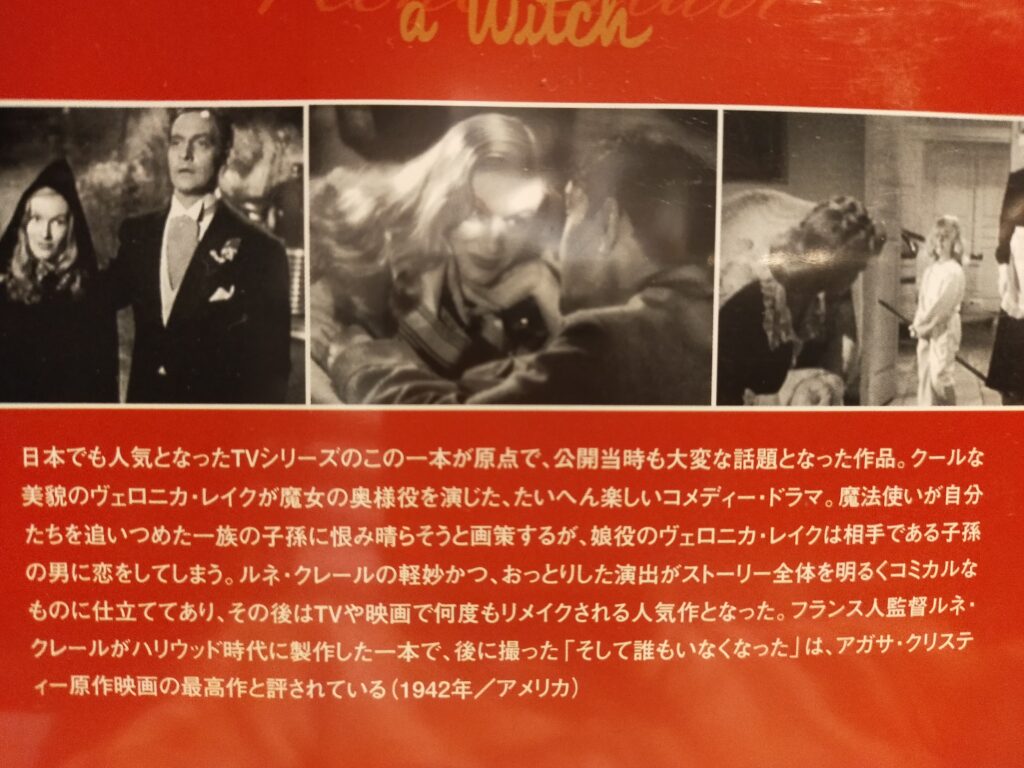
「忘れじの面影」 1948年 マックス・オフュルス監督 ランバート・プロ
メロドラマかな?と思って見た。
その体裁を取ってはいるが、一人の女性の魂の遍歴を描いた、忘れられない場面の数々に彩られた映画だった。
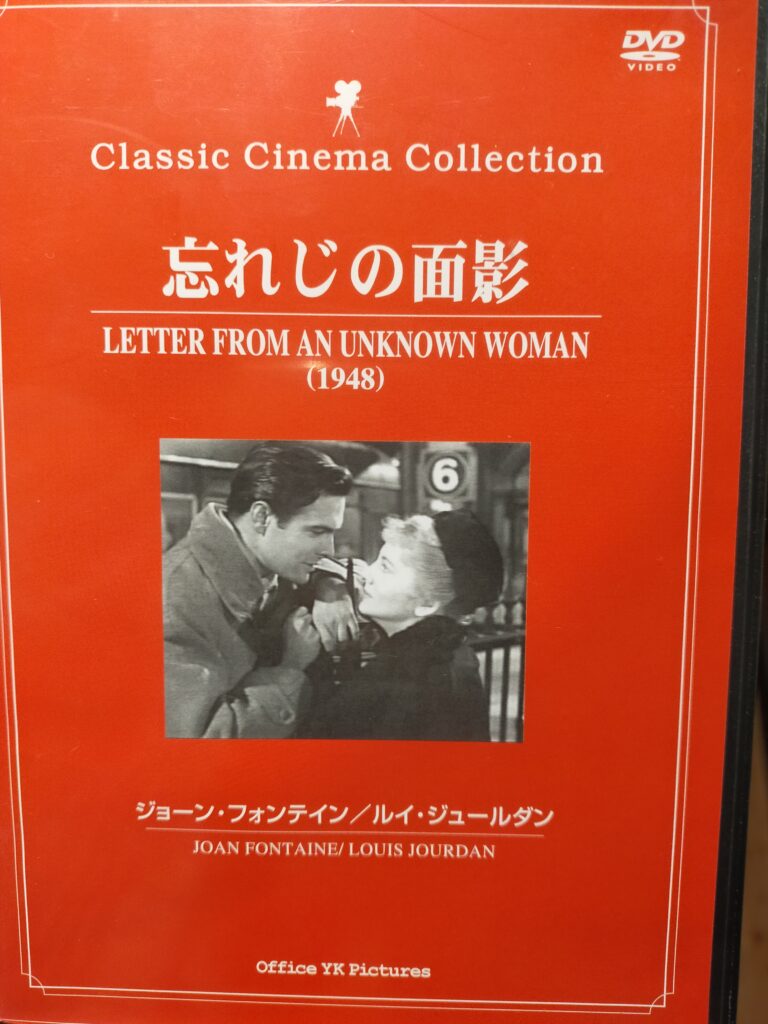
主人公を、その少女時代からジョーン・フォンテイーンが演じる。
周りになびかず、自分の世界に閉じこもりがちな少女が、自分が住むアパートに越してきたハンサムな音楽家に惹かれる。
それが一生続く。
主人公にとって、音楽家との関係が唯一の〈現実〉だった。
母親が継父とともに引っ越す列車に同乗せず、音楽家の住むアパートへ戻る。
音楽家が住むウイーンで洋服店のモデルの仕事(お客に気に入られると指名同伴?するような仕事)をして一人の時間を過ごす。
雪の日の夜に偶然、音楽家に出会う。
かつての少女のことなど忘れている音楽家との再会。
主人公は音楽家と遊園地や、ダンスホールでデートする。
たった一度のデートで音楽家の子供を妊娠し一人で産む。
資産家に見染められ、連れ子ともども何不住なく暮らすが、オペラハウスで落ちぶれた音楽家の姿を見た瞬間、ぜいたくな暮らしと誠実な夫を捨てて音楽家のもとへ走る・・・。
主人公の世界は一貫して変わらず、行動も一貫している。
たとえ音楽家が己の存在を記憶していようがいまいが。
この主人公の心理は、彼女個人にのみ特有なものなのだろうか、それとも女性に、人間に、普遍的なものなのだろうか。
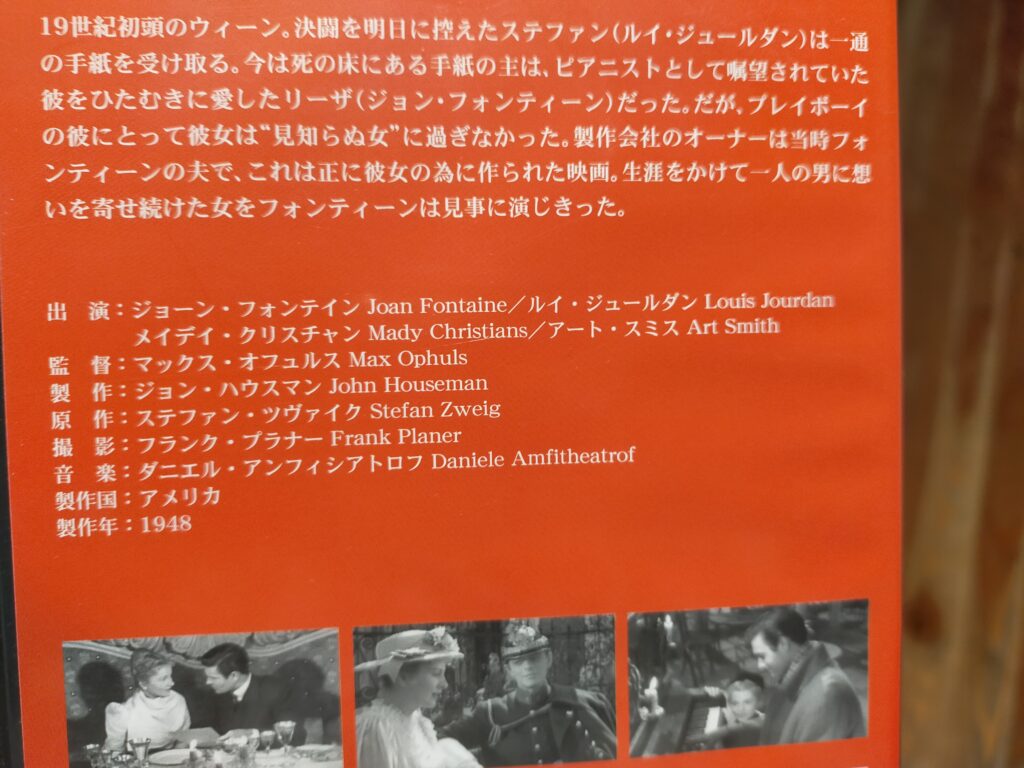
雪の日の街角での出会いの幻想的で映画的記憶に満ち満ちた場面。
世界旅行の書割をバックに尽きることない時間を過ごす遊園地のシーンの不思議な懐かしさ。
オーストリアからの亡命者でユダヤ人のオフュルス監督は、アパートの中庭や、お屋敷のセットには階段を用い、出演者に階段を上り下りさせて、立体的な画面作りを試みる。
移動、パン、クレーンを多用した流麗なカメラワークのは、夢の中を生き切った主人公の心理を表しているかのよう。
ジョーン・フォンテイーンは、持ち味の普通ッポさ、オドオドした感じを前面に出し、この特異で一途だが、普遍的でもあるキャラクターを好演。
忘れられないこの作品の象徴となった。

(番外) 「レベッカ」1940年 アルフレッド・ヒッチコック監督 セルズニックプロ
「忘れじの面影」を見て、ジョーン・フォンテイーンが気になり、彼女の出演作を探した。
ヒッチコックの渡米第二作の「レベッカ」は、フォンテイーンにとって、製作者セルズニックに見いだされてのメジャーデビュー作だった。

レベッカという名の前妻の影が色濃く残るお屋敷に後妻となって移り住んだ主人公のフォンテイーン。
彼女の持ち味の、普通さ、オドオドした自信なさげなキャラクターにより、まがまがしいレベッカの恐怖が強調されるミステリー。

途中までは、フォンテイーンを後妻にめとったローレンス・オリビエの正体が不明で、死んだレベッカにかしずく屋敷の女執事長の正体やいかに、というミステリーに満ち満ちていた。
が結末では合理的な説明がなされ、レベッカという稀代の魅力的な美女にして悪女に振り回されてのまがまがしさだったことがわかる。
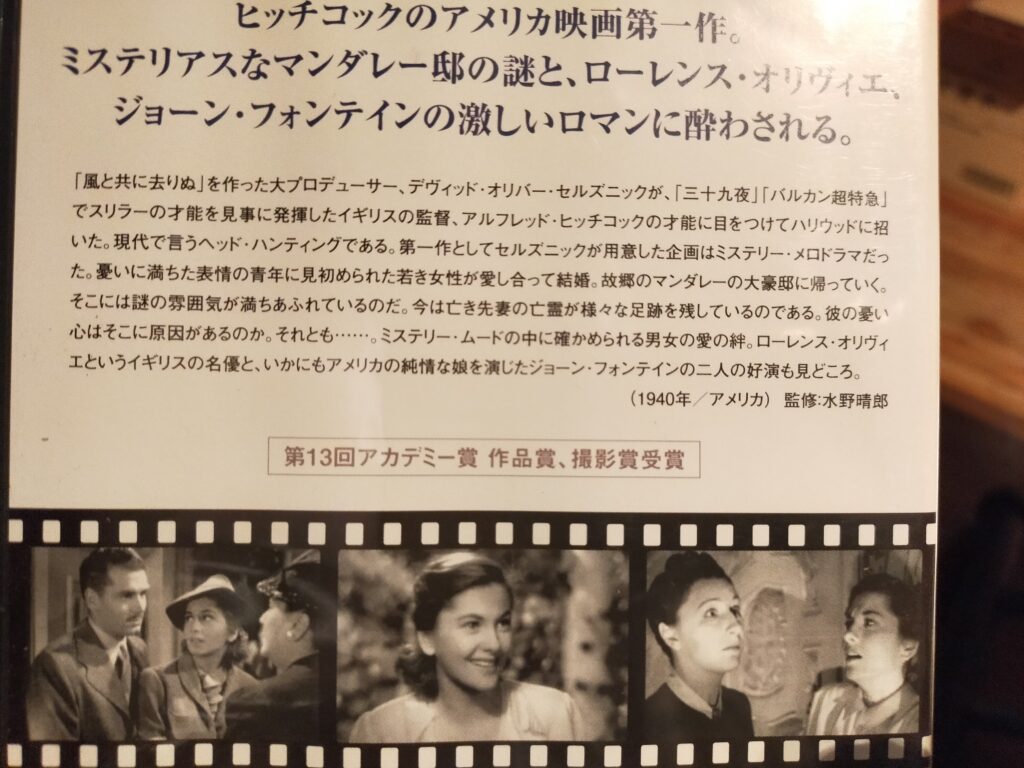
ジョーン・フォンテイーンは確信的悪女そのものだったレベッカとは対極にある、平凡で常識的なキャラクターを好演し、変質者(女執事)や神経衰弱(ローレンス・オリビエ)が跋扈するこのミステリアスな物語の被害者を演じつつ、安心感に満ち満ちた結末をもたらすべく、夫を励ます健気な新妻を演じきった。
