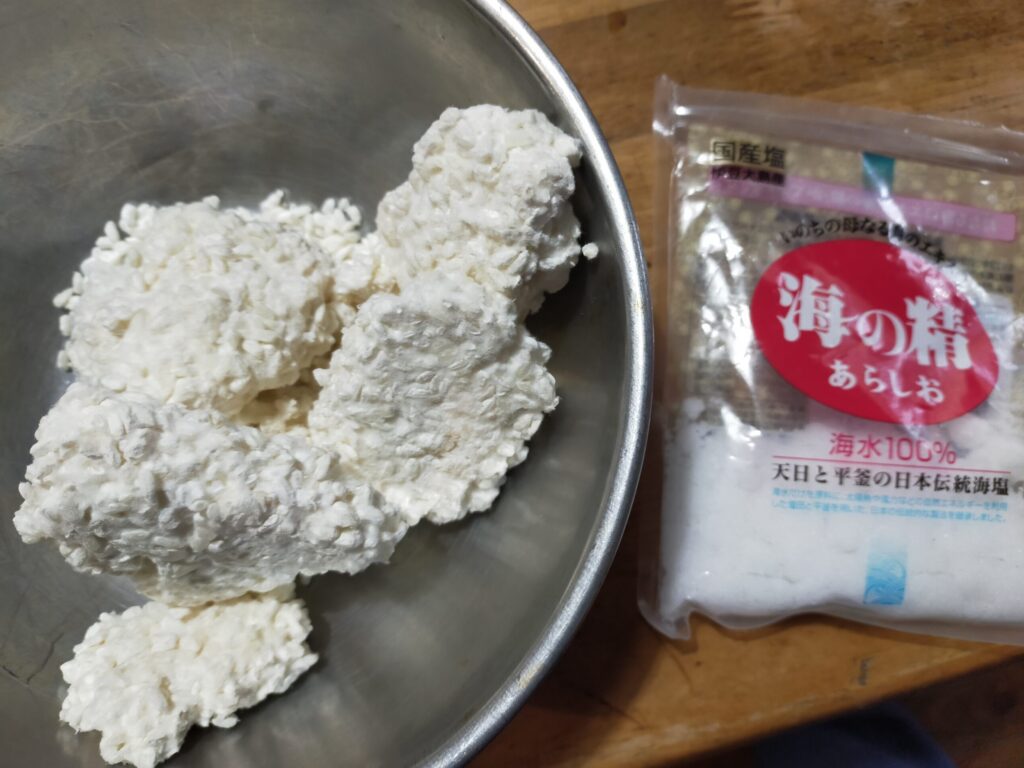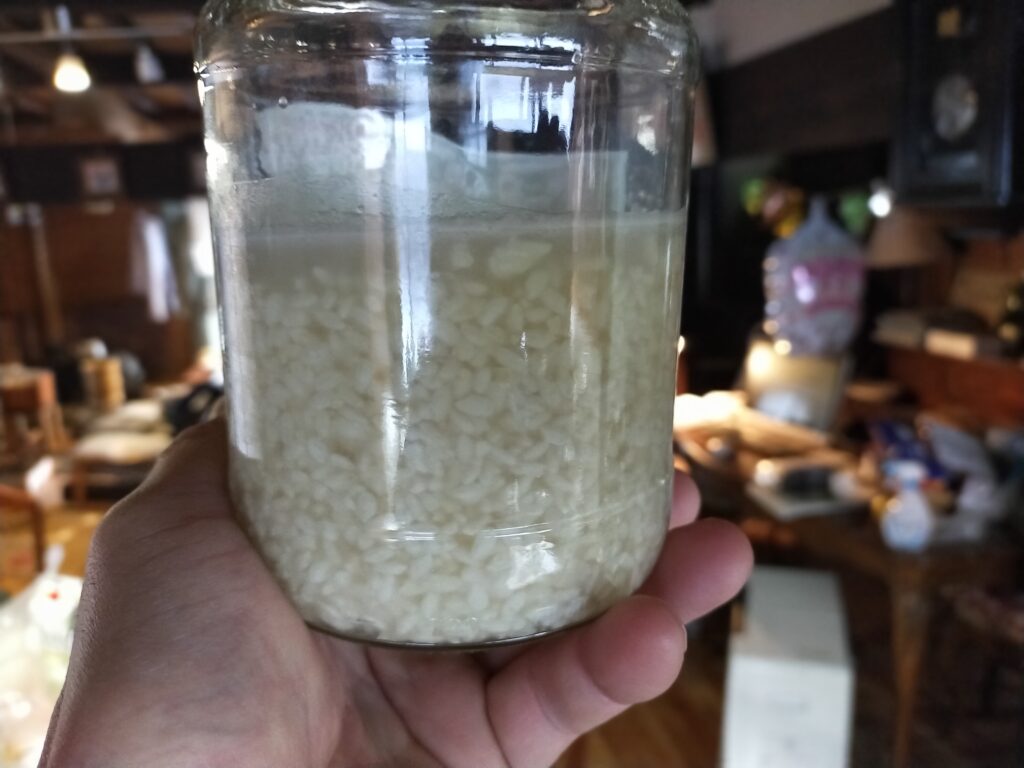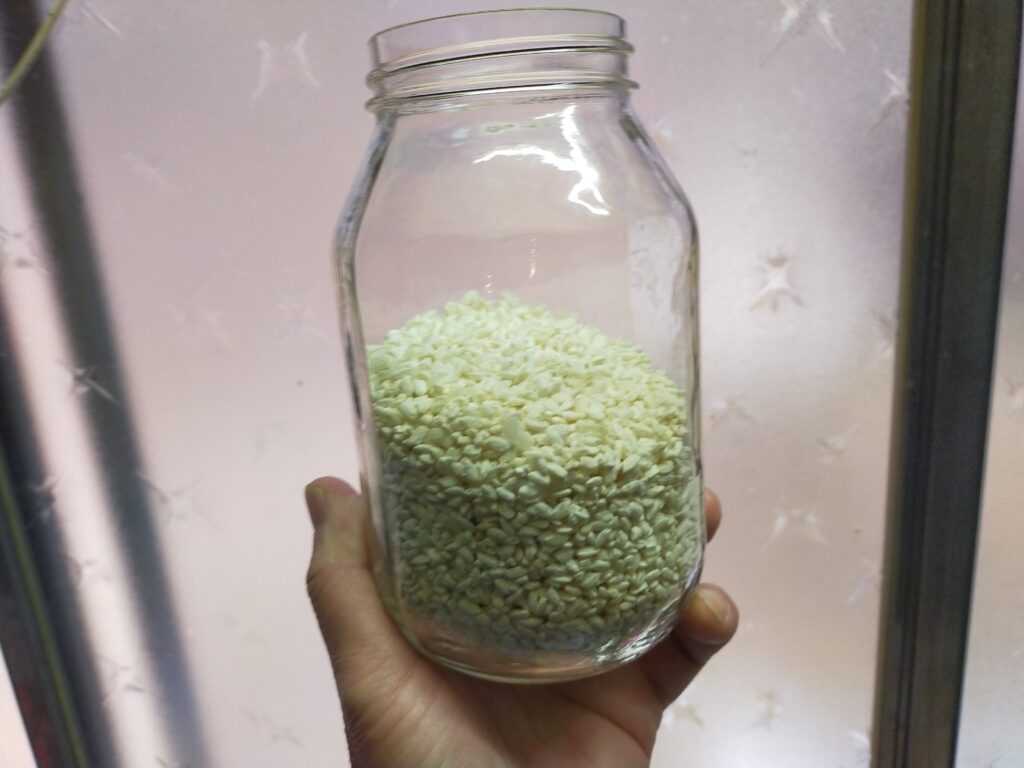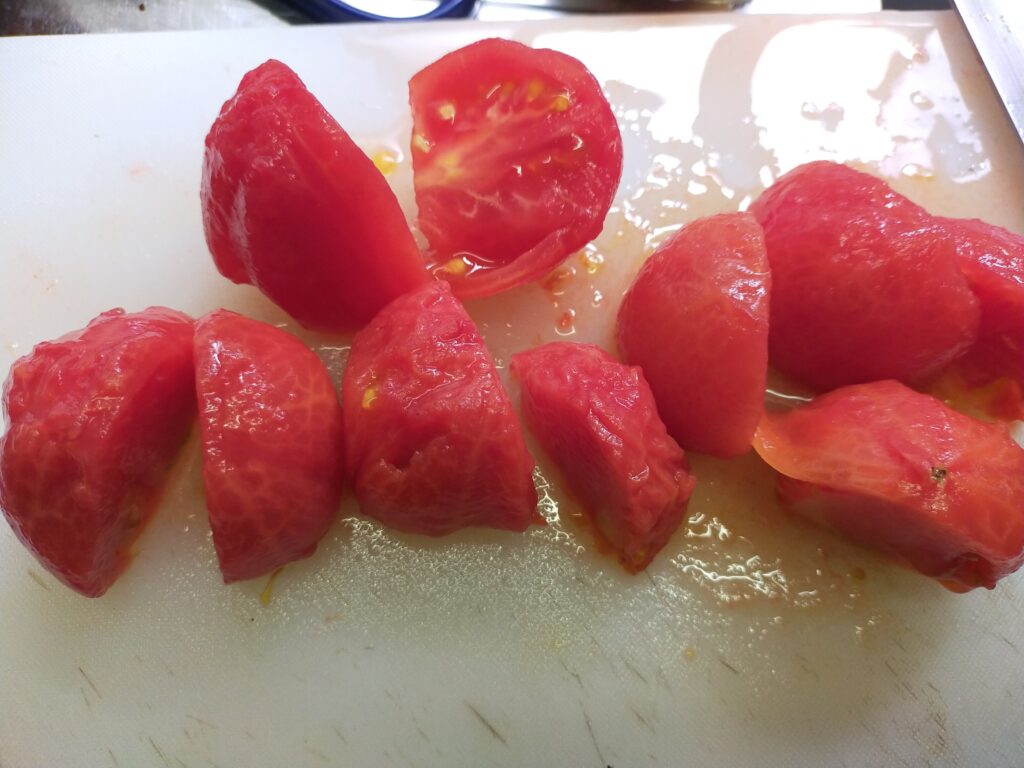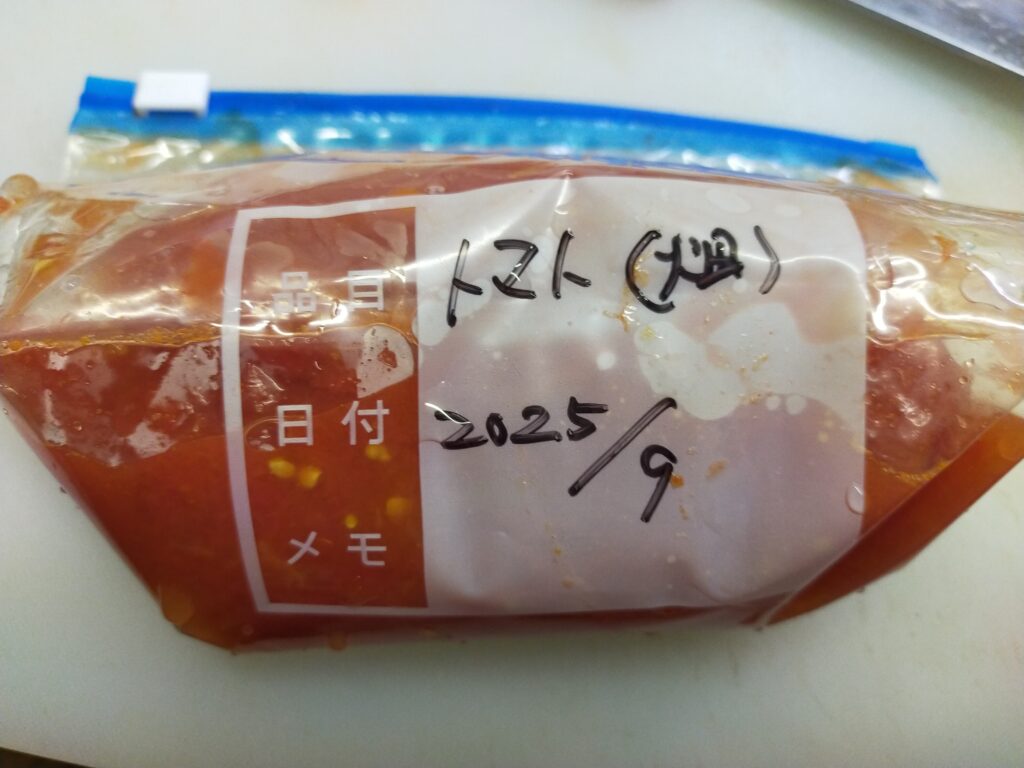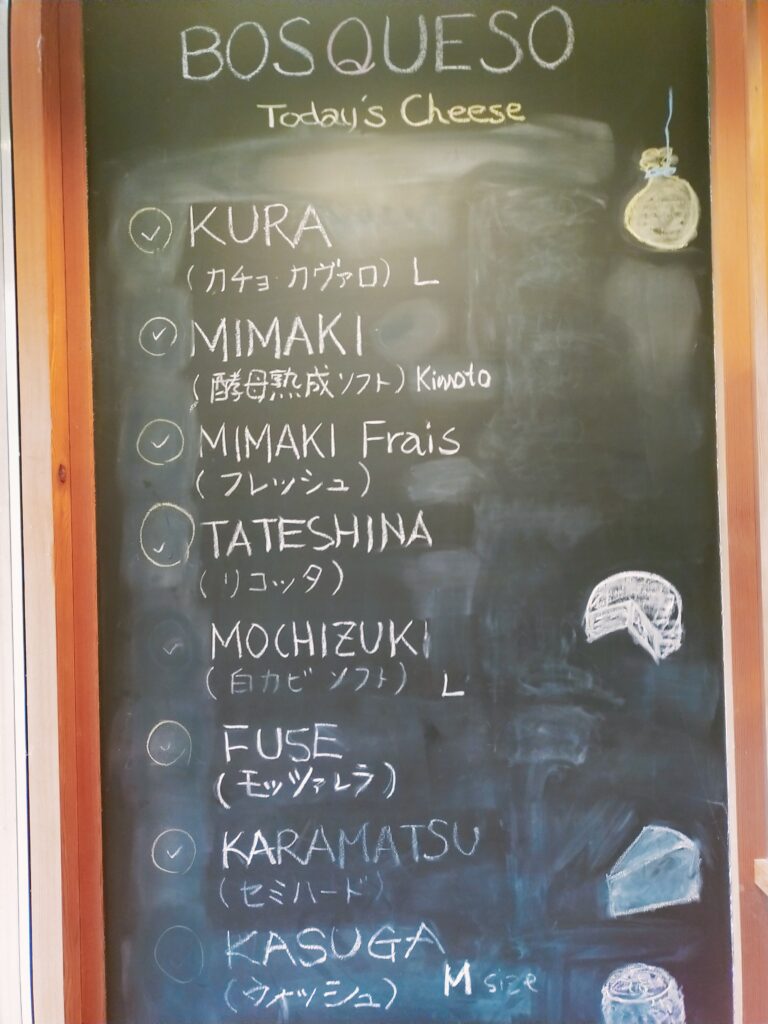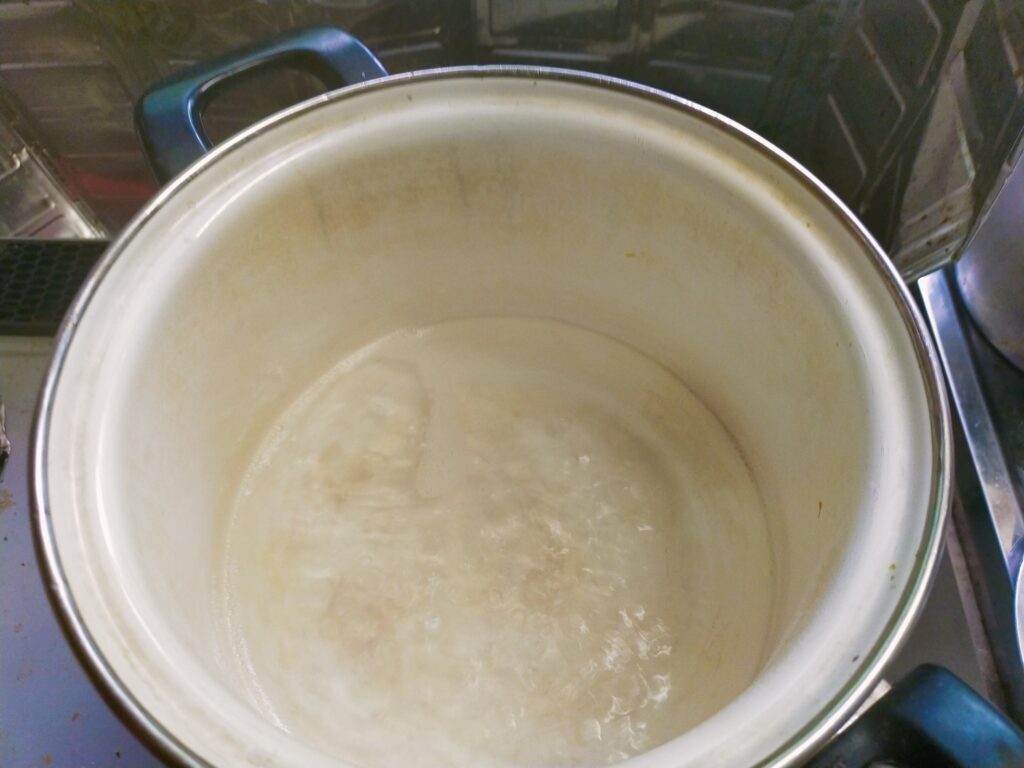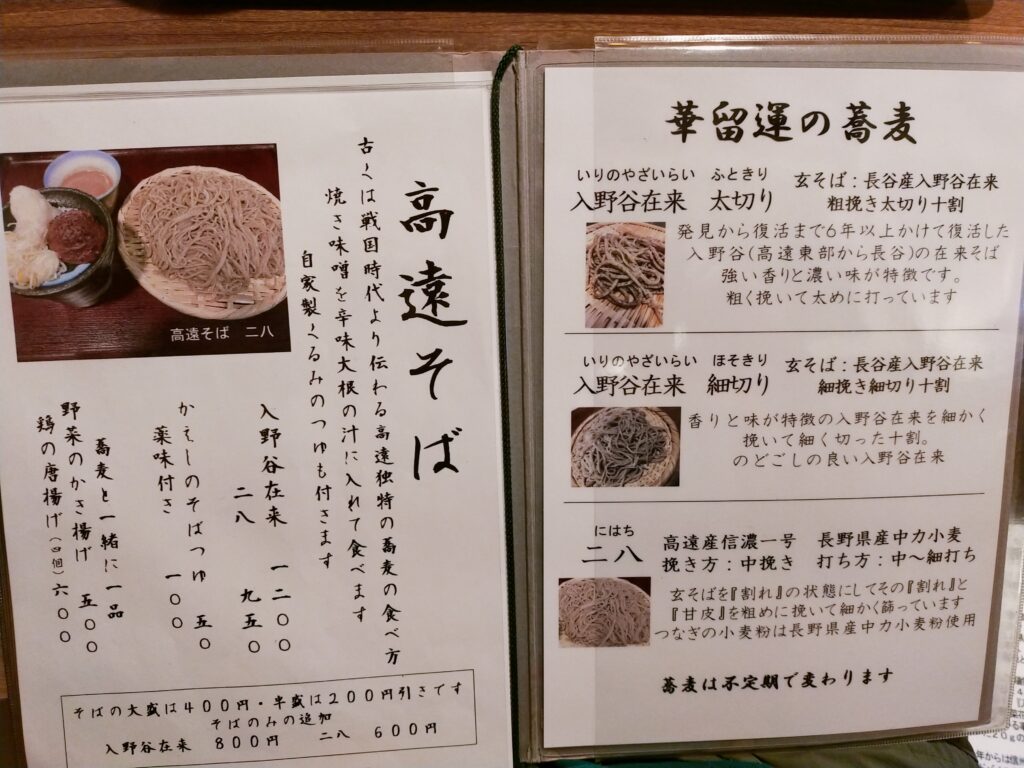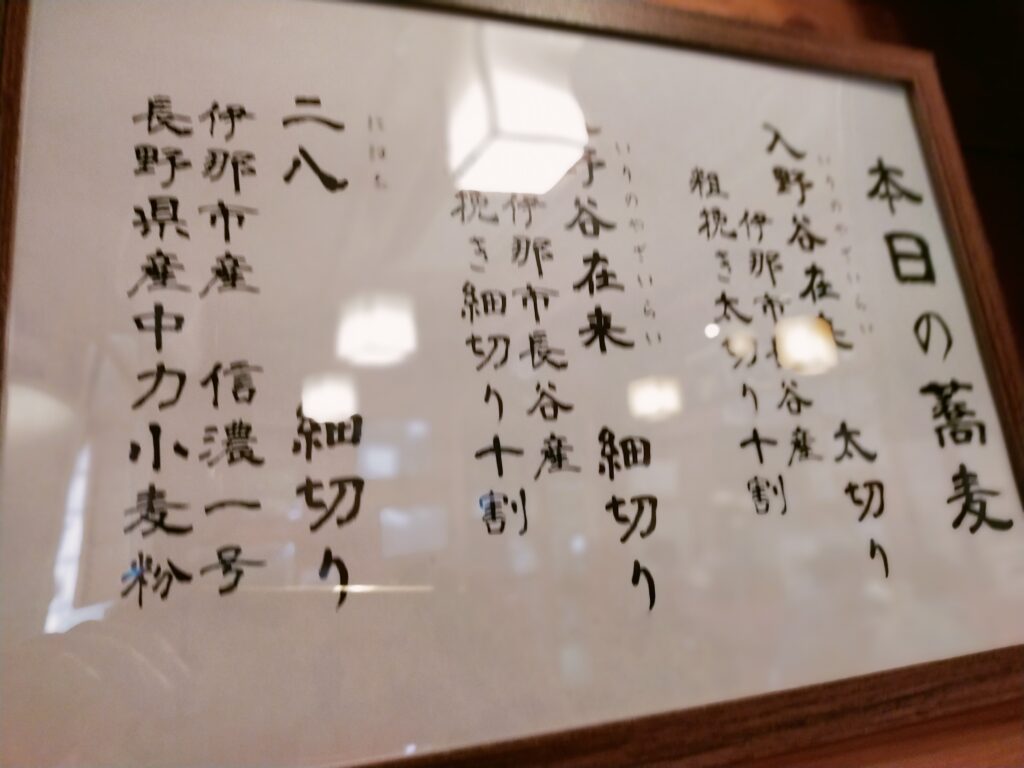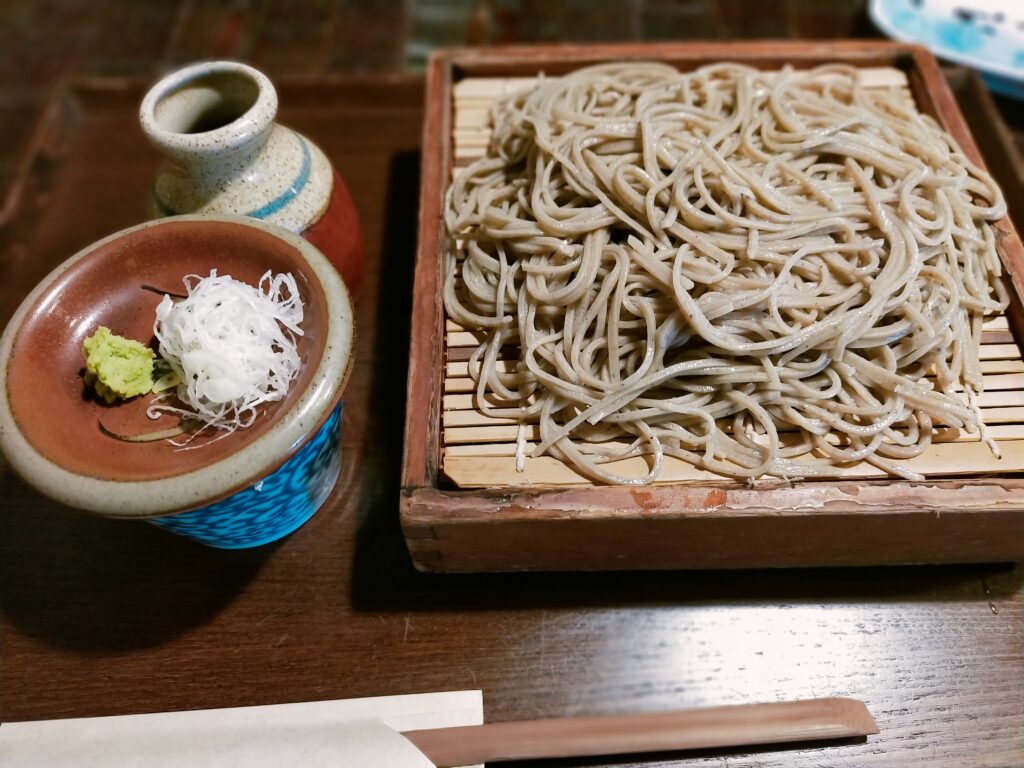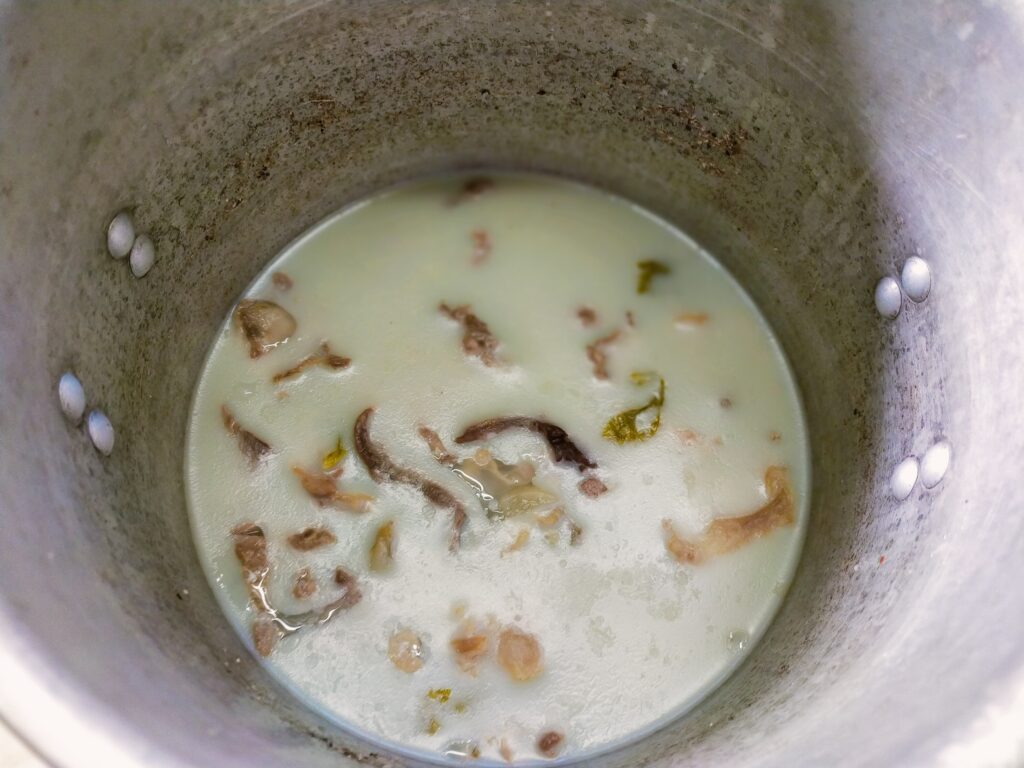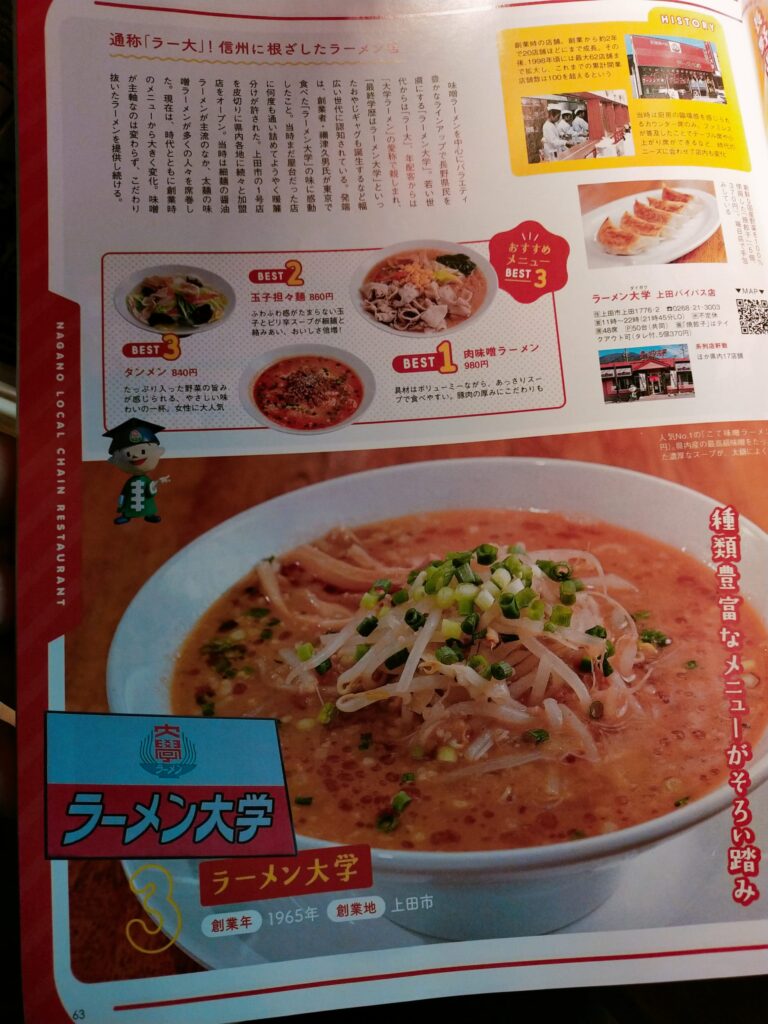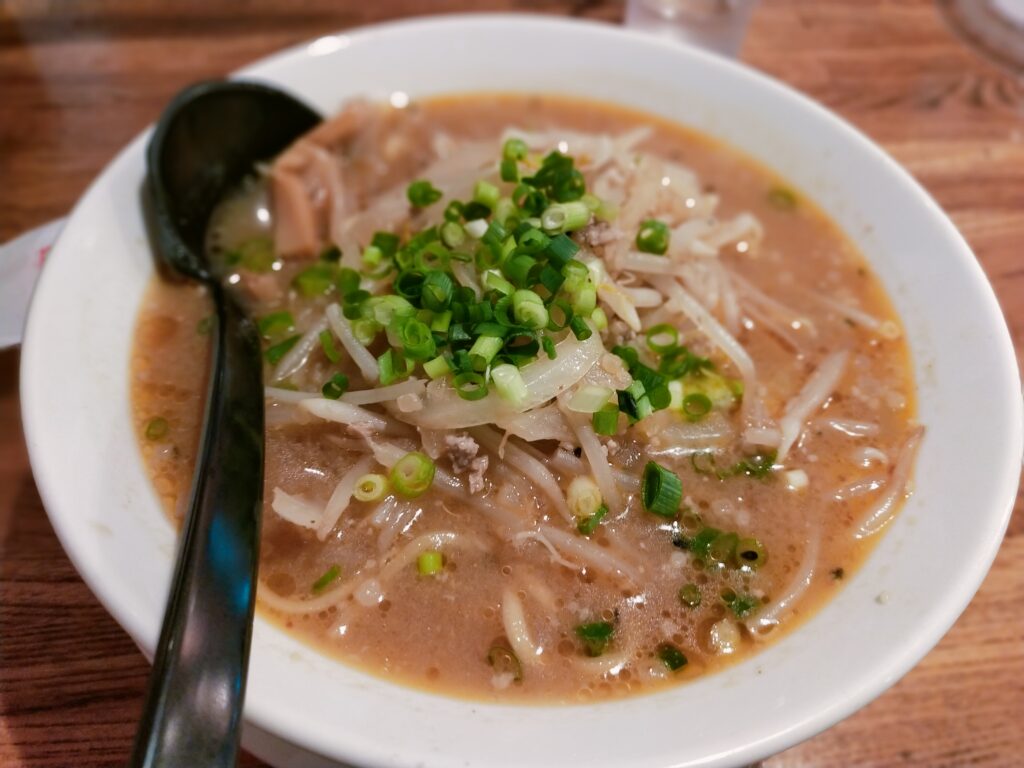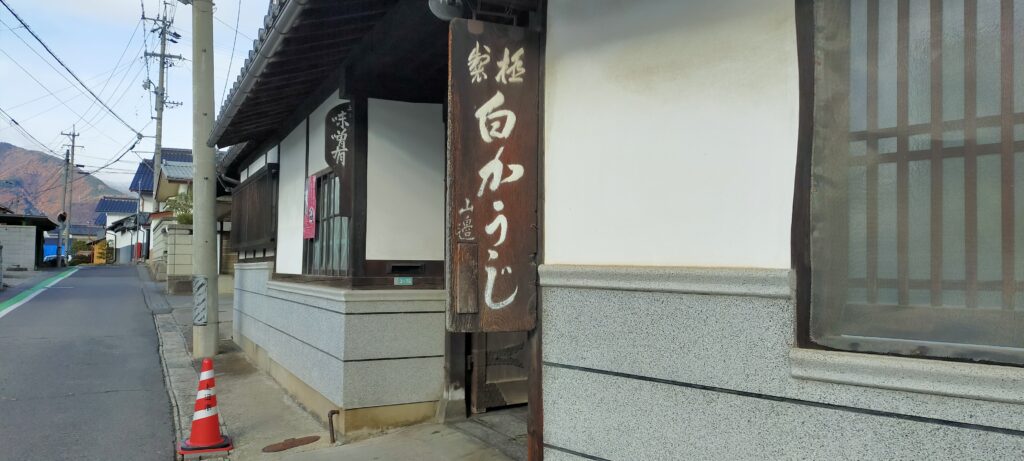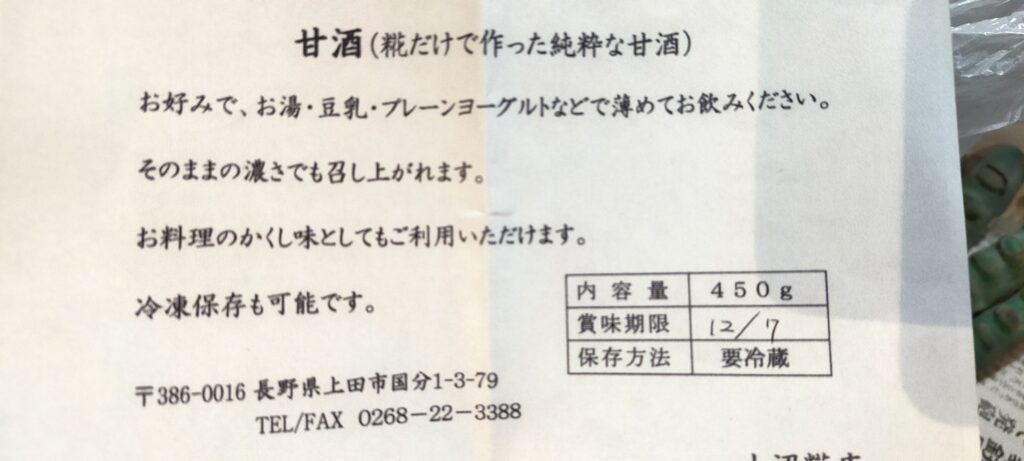柿酢を仕込みました。
材料は、熟した柿。
甘がき渋柿を問いません。
ぐじゅぐじゅの柿を潰して瓶か甕に入れて保存するだけです。
時々かき混ぜながら発酵させ、頃合いを見て漉して更に保存します。
マイルドな何ともいえない酢が出来上がります、うまくいけば。
熟した柿は案外手に入りずらいのです。
柿の樹でも持っていれば何のことはないのですが。
ということで地元系のスーパーで熟し柿の箱売りを見掛けて即ゲット。
柿酢作りに挑戦します。

柿酢作りはこれまでに2、3度挑戦しました。
1度だけうまくできました。
まろやかな酢ができて、素人づくりとは思えないほど実用的でした。
その後のトライは材料の柿の熟し方が足りなく、発酵する前にカビが出て失敗しました。
保存瓶を消毒し、柿をざっと洗い、ヘタを取って四つに割ります。
そのままどんどん保存瓶に放り込み、麺棒で潰してゆきます。
瓶の口は新聞紙で覆い、通気を良くします。
後は柿自前の菌による発酵を待ちます。
潰した柿の量が瓶の半分くらいだったので、雑菌の繁殖を防ぐためにももうひと箱熟し柿を追加しました。
瓶の中の空気は少ない方がいいと思ったからです。


ある日、瓶を見てびっくり。
口にかけたの新聞紙が盛り上がり、液体が盛大にこぼれています。
慌てて瓶を取り出しました。



無事発酵しているのはいいのですが、柿の分量が多く、発酵して新聞紙を盛り上げているのでした。
新聞紙を外し、盛り上がった柿を捨て、量を調節します。
水分が下にたまり、柿の固形物が浮き上がったところを攪拌します。
瓶の外側を拭いて新しい新聞紙で蓋をして再保存です。
吹きこぼれたのは失敗でしたが、発酵は順調に進んでいるようです。