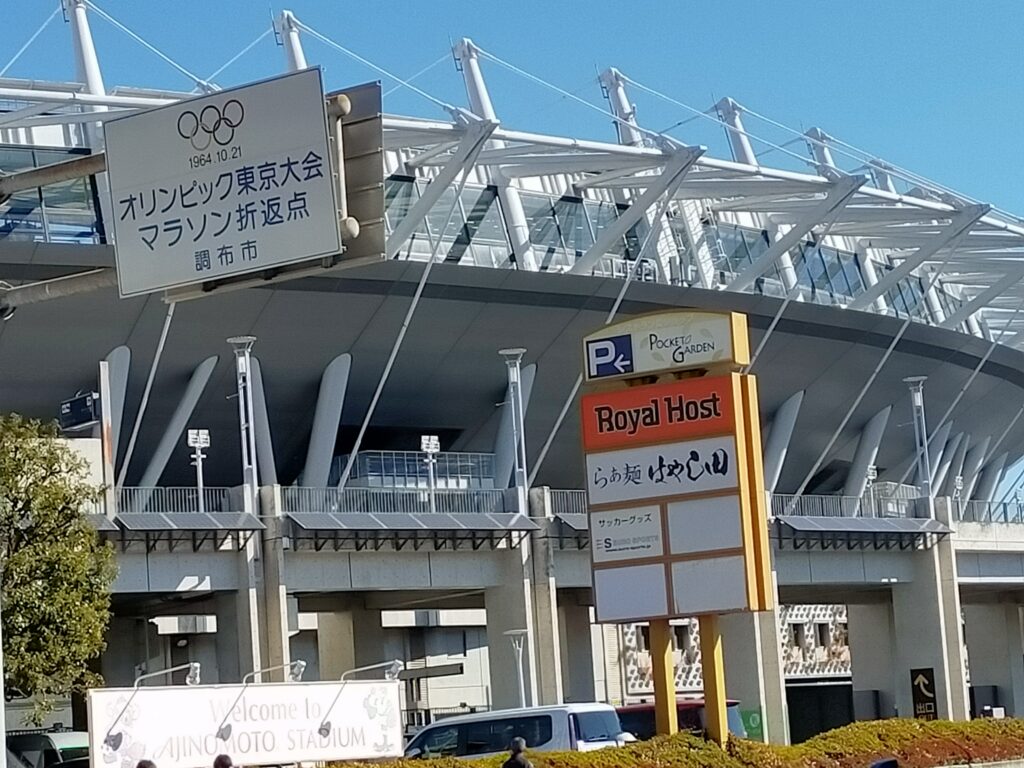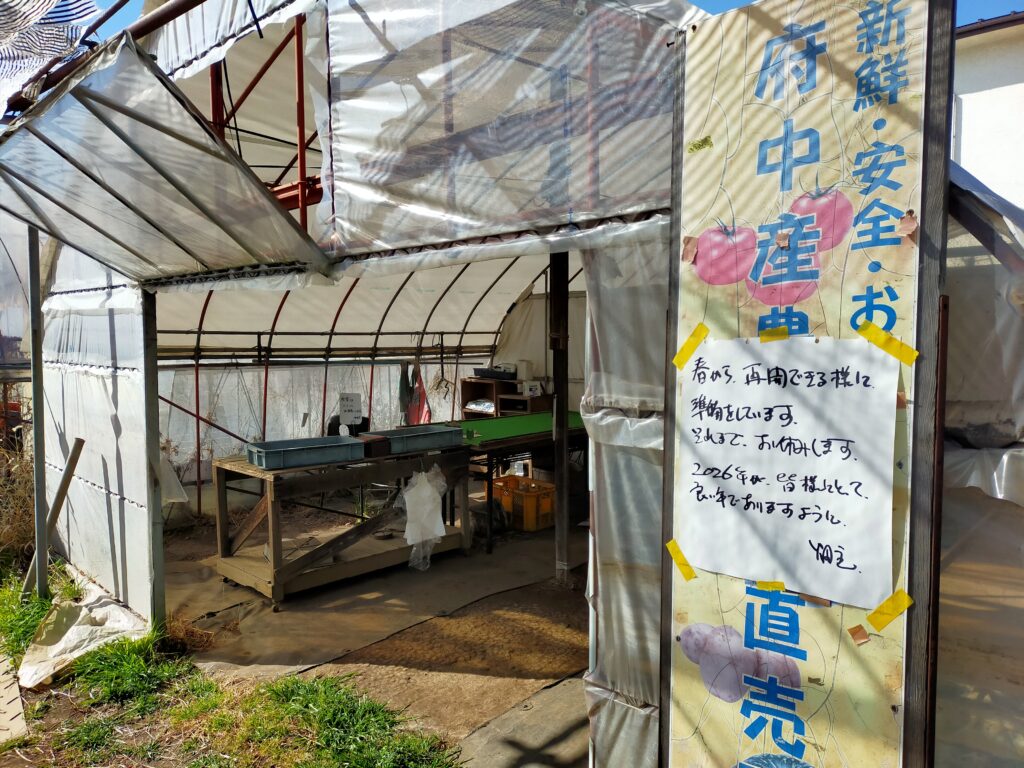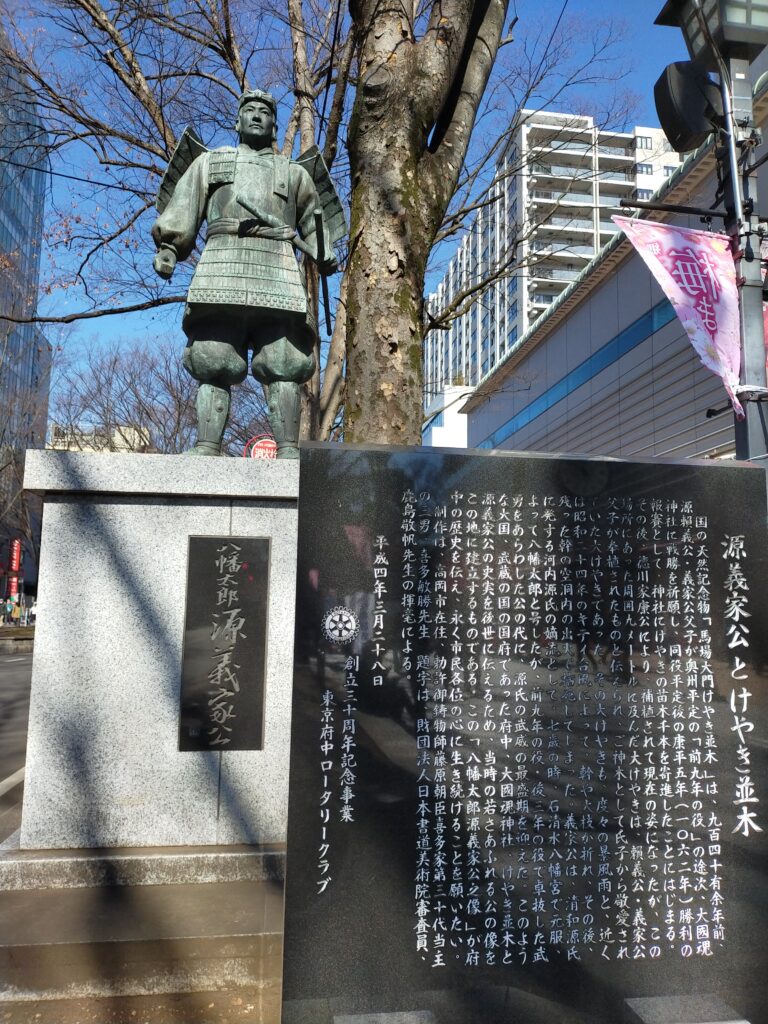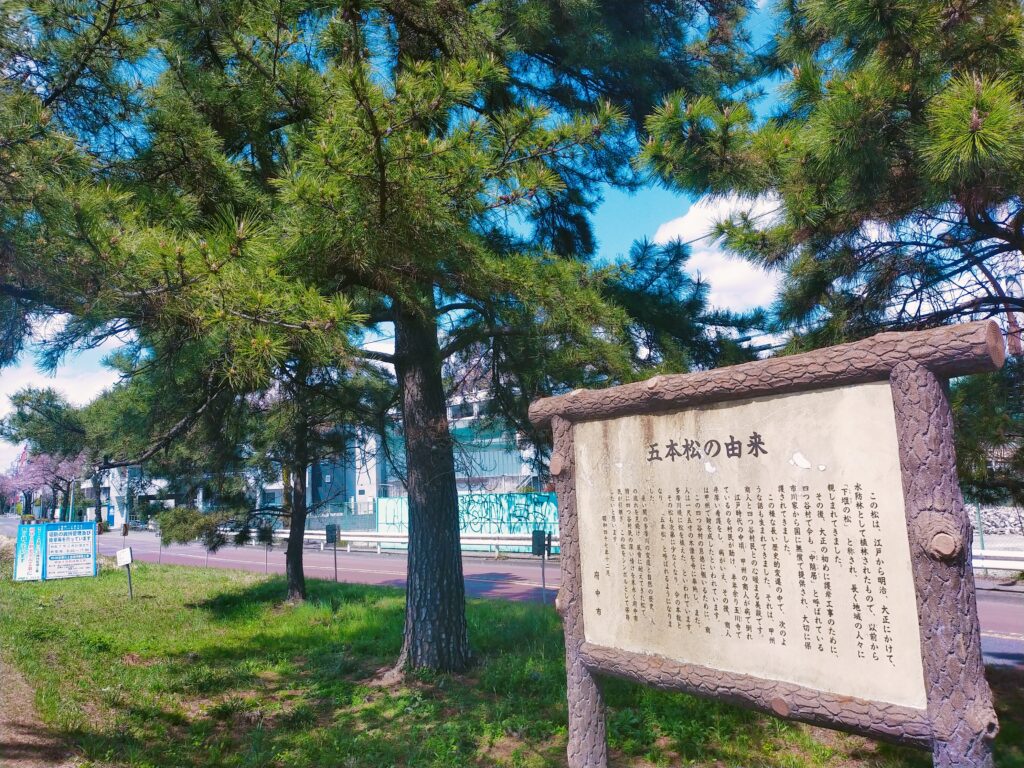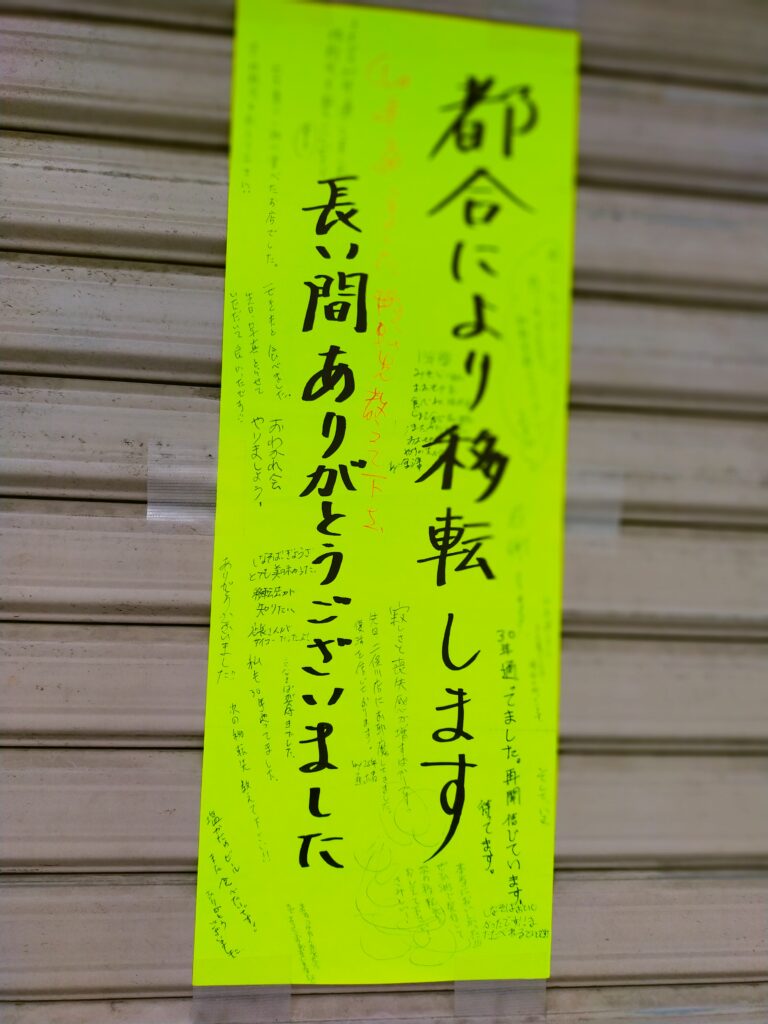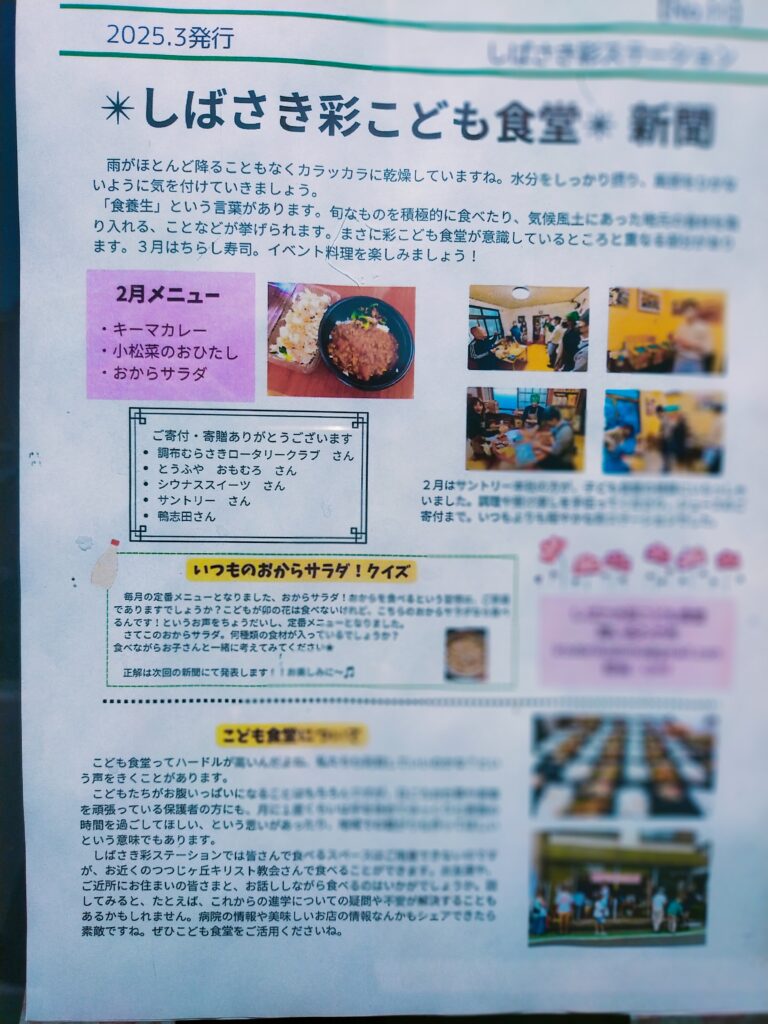山小舎おばさんが夏ミカンをもらってきました。
付き合いのある農家から数十個ももらったそうです。
その農家も処分に困ったのでしょう。
食べると、酸っぱいですがフレッシュな夏ミカン。
柑橘類が冬採れるのも関東ならではの恵みなのですが。

そこで夏ミカンをマーマレードに加工してみました。
使ったのは5個です。
ネットで作り方を調べたり、経験者にコツを聞いてみると、『苦みを抑えるために、皮の内側の白いワタを丁寧に取る』といわれました。
その前に皮のあく抜きを十分に行う必要もありそうです。

手間がかかりそうですが加工開始です。
先ずは夏ミカンの皮をむいてゆきます。
内側のワタはついたまま、皮を茹でて行きます。
30分くらい煮て柔らかくなった皮の内側をスプーンでそいで、ワタを取り去ります。
皮は千切りにしてグラニュー糖をまぶします。

実は袋から出して、種を取り、皮とともに鍋に入れて火にかけます。
アクを取りながらしばらく煮込み、とろみが出てきたら完成です。


若干の苦みと柑橘類の香り、何より採れたばかりのフレッシュさが香る手作りマーマレードができました。
ジャムの代わりに、また肉料理の味付けに使おうと思います。
スペアリブのつけダレにマーマレードを使うと絶品です。
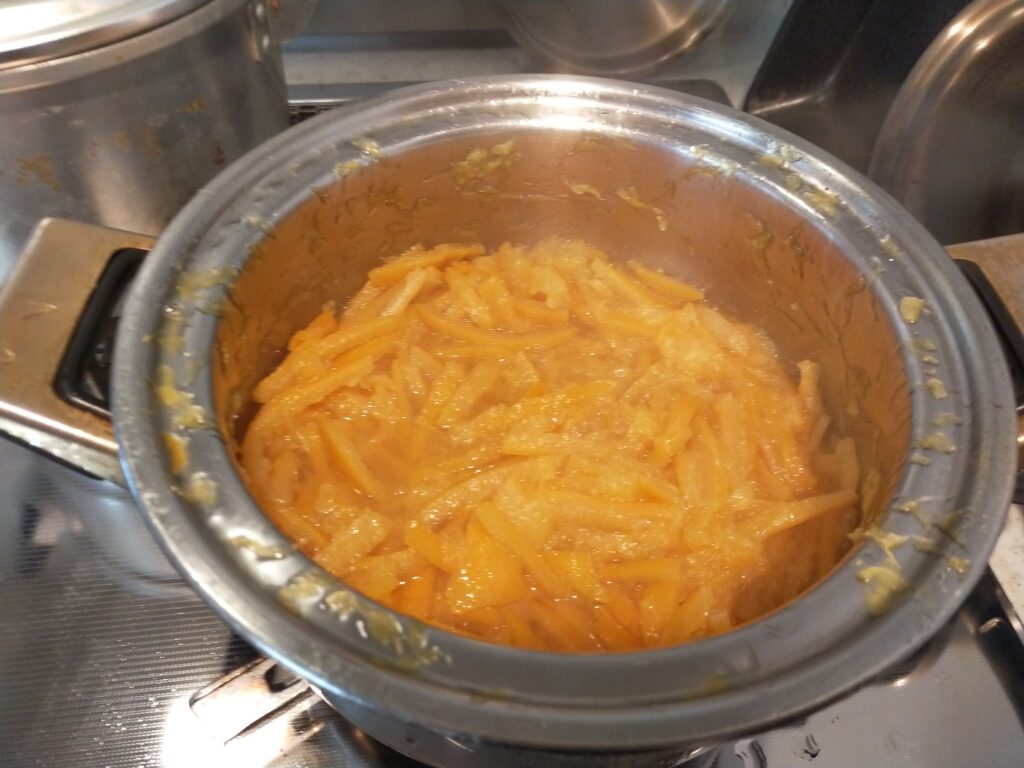
まだまだ夏ミカンは残っています・・・。