ラピュタ阿佐ヶ谷という名画座で、「豊田四郎と文学の心」という、特集上映が行われている。
都合のつく日に行ってみた。
阿佐ヶ谷には自転車で行くことが多い。
運動にもなるし、交通費もかからない。
阿佐ヶ谷は、適度に庶民的で居心地のいい街だ。
今はやりの巨大な駅ビルや、タウンモール的なショッピングセンター、タワーマンションがない。
戦後というか昭和が残っている街だ。

駅北口周辺には小さな飲食店が軒を連ねる。
戦後のどさくさで、細切れの居住権、商権が発生した名残りなのだろうか。
再開発の波にも飲み込まれず、かといって寂れてもいない。

駅から徒歩2~3分、ラピュタ阿佐ヶ谷のホール。
特集上映に合わせて豊田監督作品のポスターが並ぶ。
映画関係の書籍やブロマイドが置いてあるのもうれしい。
窓際にはテーブル席もあり、持って行った弁当を広げられるのもいい。



係のお兄さんから時節柄のこまごまとした注意(携帯の設定、飲食の禁止、私語の禁止、脱帽、録音撮影の禁止、マスクの着用・・・)を喚起されたのち、いよいよ「小島の春」の上映だ。
フィルムセンター所蔵作品のタイトル。
配給は東宝。
制作は東京発生映画製作所。
後に東宝に吸収されることになる制作会社とのこと。
監督、豊田四郎、当時34歳。
脚本、八木保二郎。
主演は夏川静江31歳、脇に菅井一郎、杉村春子など。
原作はハンセン病患者救済につくした小川正子という女医の手記。

瀬戸内に浮かぶ帆掛け船、という今ではCGでしか再現できないであろう「日本の原風景」のロケーションで始まるこの作品。
ポンポン船、渡し場の造り、漁村風景、宿の部屋の造り、など戦前の日本の景色が見られる。
主演の夏川静江は、無声映画時代に子役から娘役として第一線で活躍してきた女優。
戦後、母親役などで控えめながらしっかりとした演技を残したが、31歳の時の「小島の春」でも、そのイメージを彷彿とさせ、まさに適役。
媚びなく、凛とした、シンの強い人物像を再現している。
演技もうまく、娘役として漫然とやってきた感じではない。
女優は歳を取ると崩れたり、化けたり、怖くなったりすることが多いなか、戦後になっても、シンを残したまま怖くならずに歳を重ねた女優さんだった。

脇役に、菅井一郎と杉村春子を配している。
壮年時代の菅井、若さの残る杉村をスクリーンで観ることができるのもこの年代の作品ならではだが、若くてもさすがは両俳優、家族から離されて療養所へ向かうハンセン病患者の苦悩を演じきっている。
豊田四郎監督は、代表作が「夫婦善哉」(1955年)と「雪国」(1957年)で、ほかにも「猫と庄造と二人のをんな」(1956年)、「駅前旅館」(1958年)、「墨東奇譚」(1960年)など、名作が多い。
映画の造りもがっちりしているし、有名俳優を使う。
どの作品も観て損はない監督だが、今にして思うと、名優たちの演技が過剰な作品が多いような気もする。
森繁など、豊田作品で好きなように暴れているように見えて、いいところは監督がすべて持って行った、ように思ってしまうのはヒネクレた見かたか。
もっとも映画監督とはそんなものか。
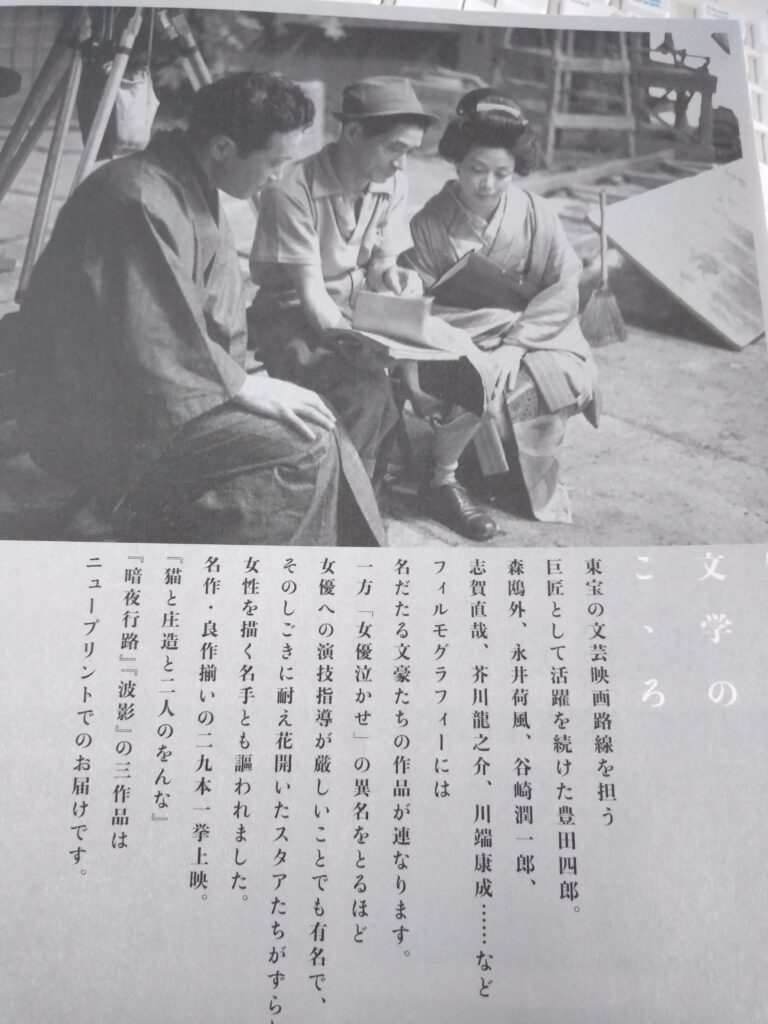
戦後の作品では、重厚で役者の演技をとことん引き出す豊田監督の作風にあって、戦前の「小島の春」には、緊張感はあるものの、さらさら流れるような演技と、社会的良心に満ち満ちたストーリーのみがある。
これも主演の夏川静江の個性がなせる業なのだろうか。
まじめな女の先生(教師)が被災後の現地を巡るというシチュエーションでは「原爆の子」(1952年 新藤兼人監督)という作品がある。
また、瀬戸内海を舞台にした女教師の物語には「二十四の瞳」(1954年 木下恵介監督)があった。
前者の乙羽信子、後者の高峰秀子のどちらも若くてきれいだったが、一番先生らしいのが「小島の春」の夏川静江だった。
1999年文芸春秋社刊の「キネマの美女」という大型本に、夏川静江のインタビューがが7ページにわたって掲載されている。
それを読むと、「小島の春」への出演は、結婚を機に一旦引退した後の特別出演だったとある。
自身が選ぶ代表作に「小島の春」が入っていることも。

山小舎おじさんが印象に残る夏川静江の出演作は、まず前述の「二十四の瞳」(1954年 木下恵介監督)、ついで「蟻の街のマリア」(1958年 五所平之助監督)。
前者では大石先生こと高峰秀子の母親役。
娘の学校での愚痴を聞いてやり、先生を訪ねてきた子供たちに大わらわでうどんをふるまってやり、娘の亭主に赤紙が来てはしゃぐ息子(孫)を叱る娘(亭主の妻)を制して「お義母さん一本つけてください」と場を取りなす義理の息子にこたえて支度し始める、お母さん(おばあさん)役。
亭主の戦死広報には「お父さん死んだよ」と息子に告げるだけだった高峰秀子も、母親の夏川静江が静かに死んでいったときには「お母さん、お母さん」と取り乱していた。
「蟻の街のマリア」では、バタ屋部落にボランテイアで住み込むキリスト者の娘を心配し、リヤカーを引く娘に遭遇した際には、走って追いかけるも途中で走れなくなり、同行の若い女中に後を頼んで息をつく姿が印象に残っている。

「小島の春」で島のハンセン病患者やその家族を診て回り、宿に落ち着くシーンがあった。
畳の部屋には火鉢のほか何もない。
火鉢と宿のおかみと、手に持つお茶だけが相手のすえっぱなしのワンショットワンシークエンス。
夏川静江の動きにに見入った。
無駄なく、隙もなく、媚もなく、見苦しくもない立ち居振い。
見入ってしまった理由が、夏川静江の演技力のせいなのか、当時の堅気の日本女性が身にまとっていた歴史、文化のたまものなのか。
どちらのせいでもあるのだろうと思った。
「小島の春」はそういう映画だった。
