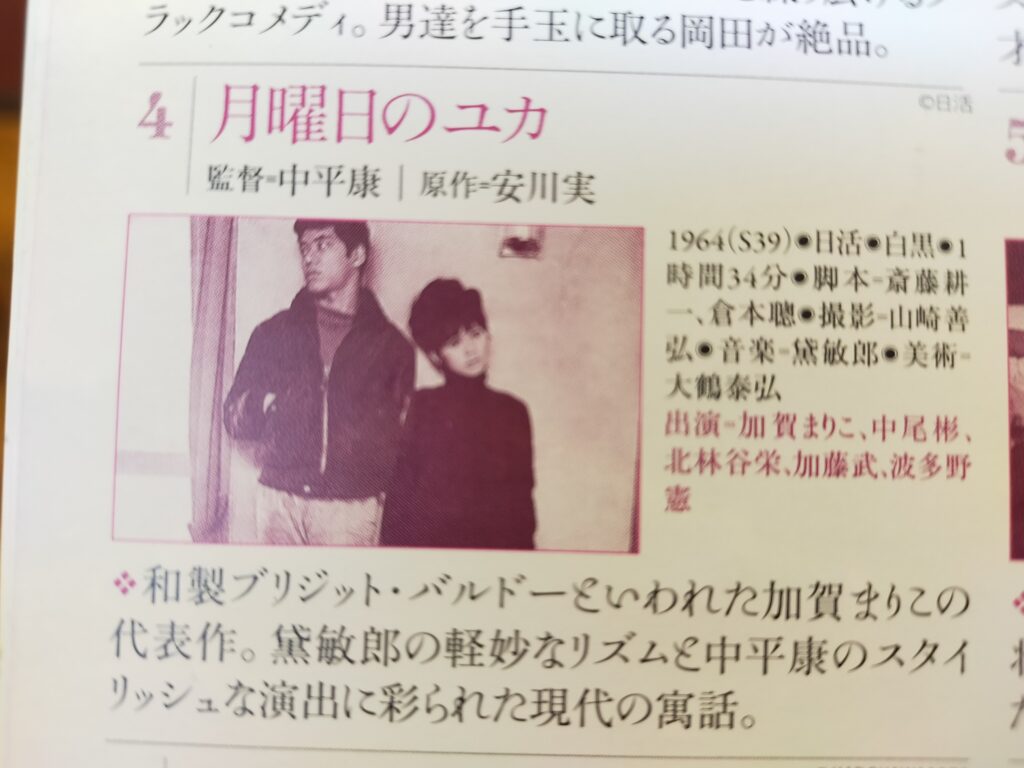観たかった「月曜日のユカ」(1964年 中平康監督 日活)の上映に駆け付けた。
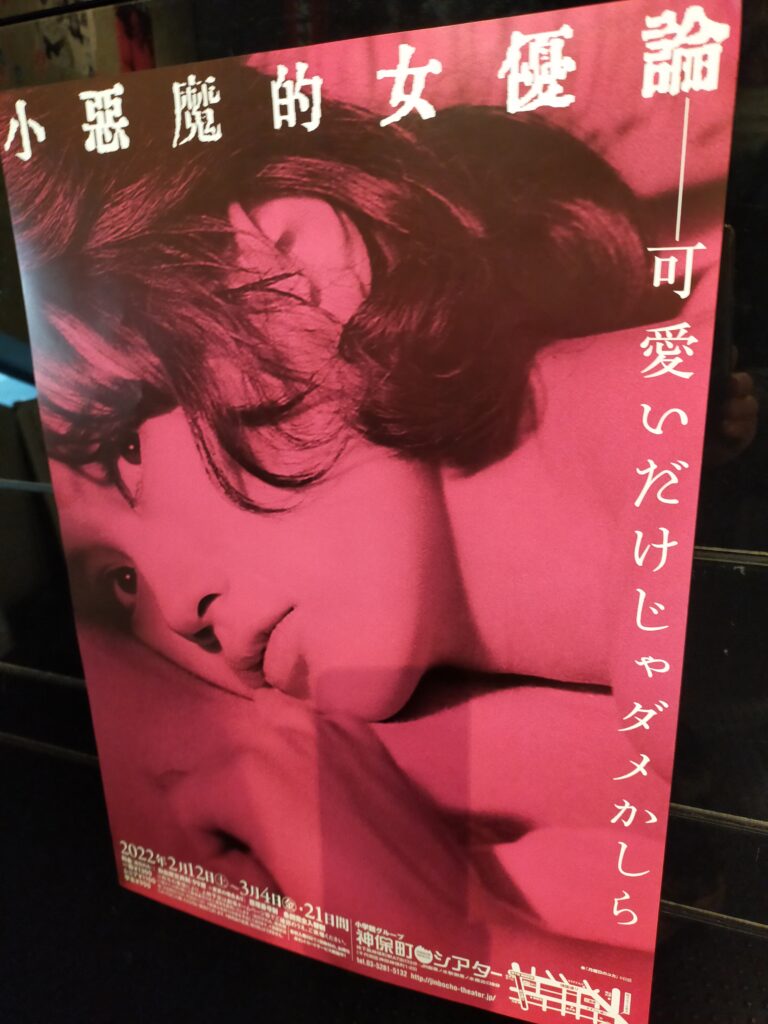
期待通りのしゃれた演出。
期待通りの加賀まりこ。
中平演出は、望遠レンズで加賀まりこの自然な表情を捉えたり、ストップモーションで余計な抒情を廃したり、駒落としや工夫した構図でおしゃれな画面を作り出す。
何を考えているかわからないが魅力のある加賀まりこの存在に、とことん付きまとう〈距離感〉がいい。

新聞にたばこの火が穴をあけ、空いた穴からカメラが抜け出て場面転換するような演出が続き、観客は目が離せない。
加賀まりこ演じるユカは、18歳で横浜のクラブの売れっ子。
外国船に物品を収めている社長のパパ(加藤武)がいて、半端者のボーイフレンド(中尾彬)もいる。
打算的で刹那的に見えるが、実は聖女と思えるくらい純粋で無垢な存在である。
〈ユカ〉は「道」(1954年 フェデリコ・フェリーニ監督)のジュリエッタ・マシーナ演じる〈ジェルソミーナ〉や、「㊙色情メス市場」(1974年 田中登監督)の芹明香演じる〈トメ〉の、加賀まりこ版である。

ユカの母親は、黒人兵のオンリー上がりで、横浜の下町の長屋に住んでいる。
ユカの良き相談相手だ。
母親を演じるのが北林谷栄。
これ以上ない配役。
これ以上ない演技が見られる。
オンリー上がりの母親と、愛人暮らしの娘。
悲惨な境遇だが、映画が描くのは彼女らの神性。
淡々とナレーションを読むような母親の口調。
パパと喧嘩した後の仲直りの仕方、を娘に相談された母親は、自分の経験を話す。
オンリーと喧嘩した後、ハウスへ一抱えもある花びらを持って行ってまき散らしたことを。
パパがユカを大事な話があると呼び出した時、ユカは母親を連れて待ち合わせのホテルへ向かう。
場違いな母の登場に、怒るパパ、冷ややかなホテルの視線。
その時の北林谷栄の困ったような、寂しげな、すべてを受け入れて淡々としたような表情。
その表情は常に社会の底辺にあって、自らも苦労しながらも社会の下支えを強いられ、事が済むと何事もなかったように忘れ去られる存在、の悲しみを物語っている。
こうした演技ができるのは北林谷栄のほかにはいないのかもしれない。
さすがは、「ビルマの竪琴」のリメーク(1985年)においても、第1作(1656年)同様にキャステイングされ、30年越しに、唯一無二のビルマ人のおばさん役を演じた人、だけのことはある。

この作品、原案はミッキー安川だが、もともとは横浜に伝わってきた実話だという。
戦後の横浜をオンリーや愛人として生き抜いてきた親子が実在したのだ。
底辺に生きながらも聖なる無垢な存在。
加賀まりこは天性の輝きで、ユカを演じた。
生涯のベストの演技の一つだろう。
その母役の北林谷栄。
底辺の無垢な女性の、そのまたわき役として忘れられない存在だった。