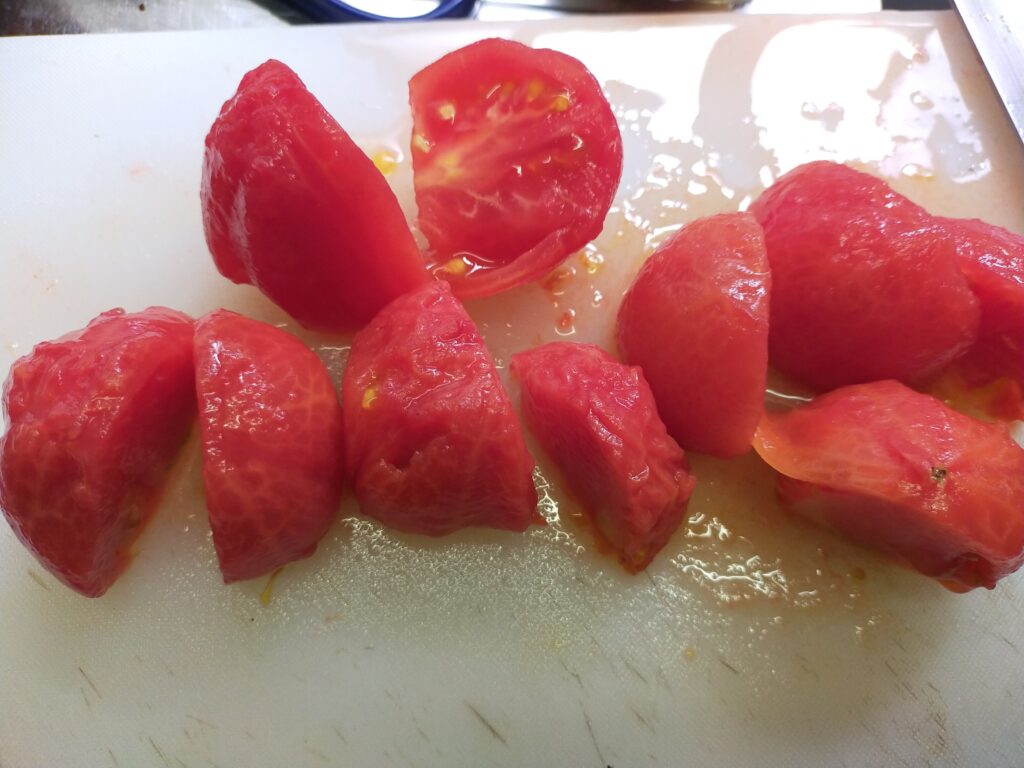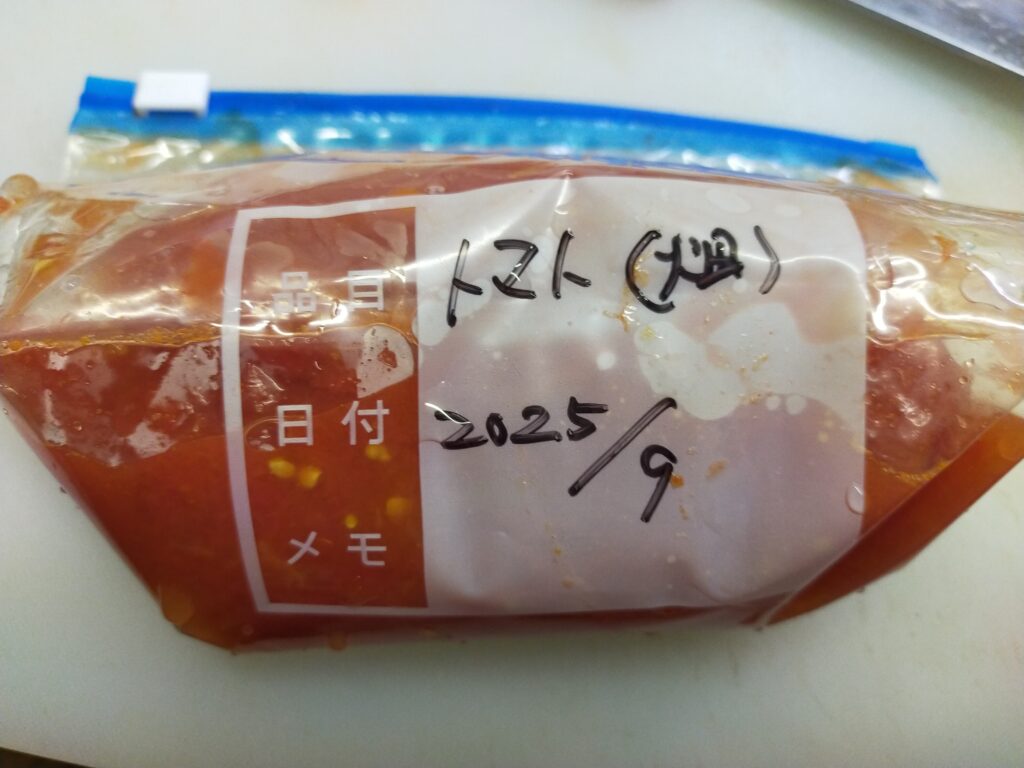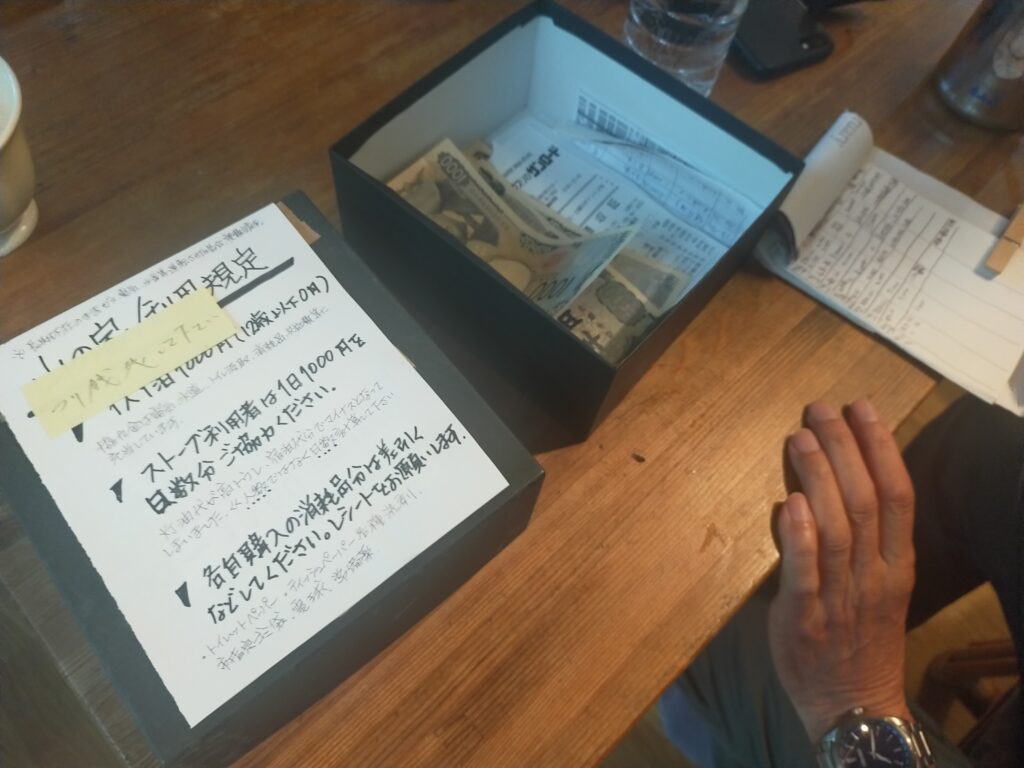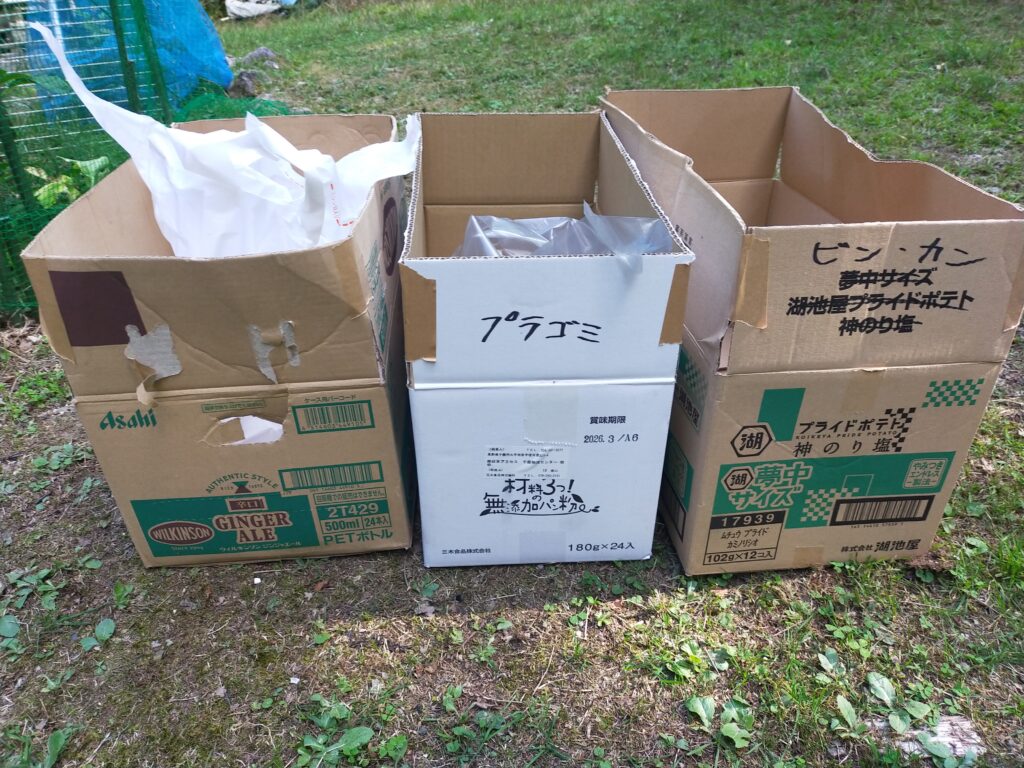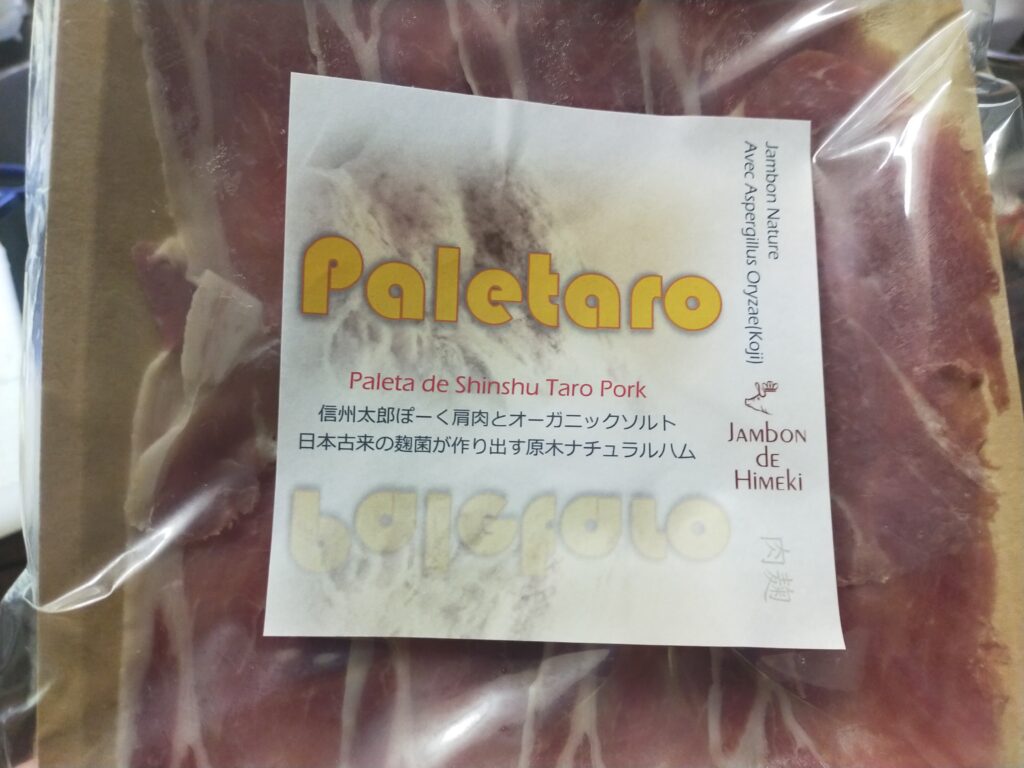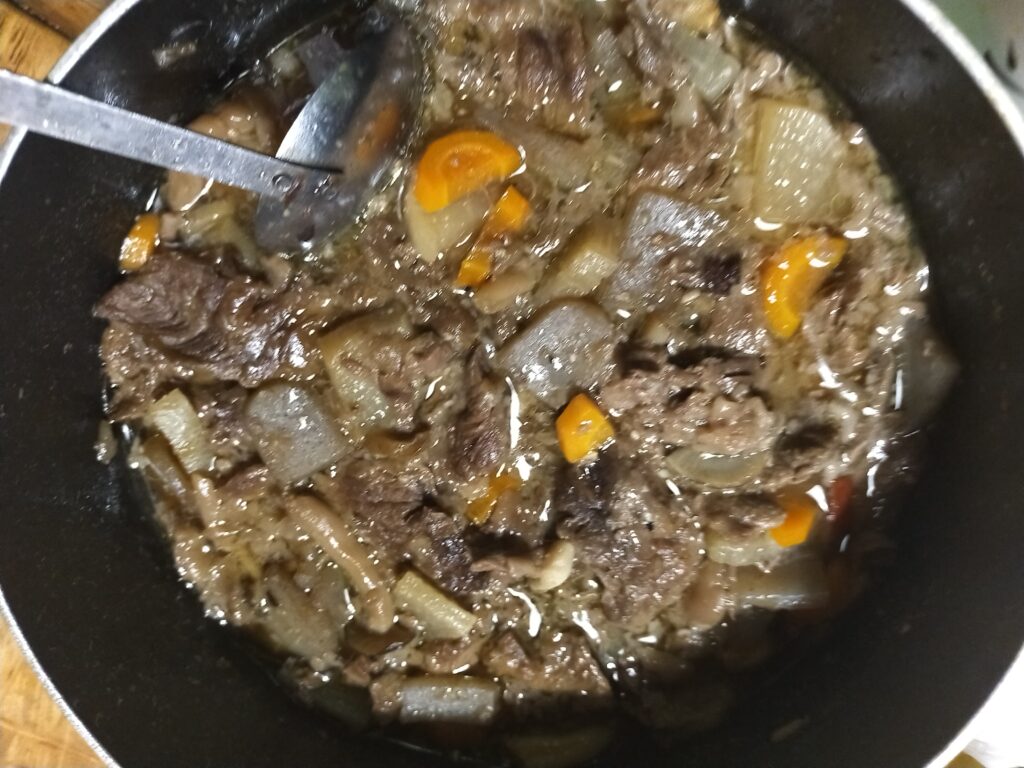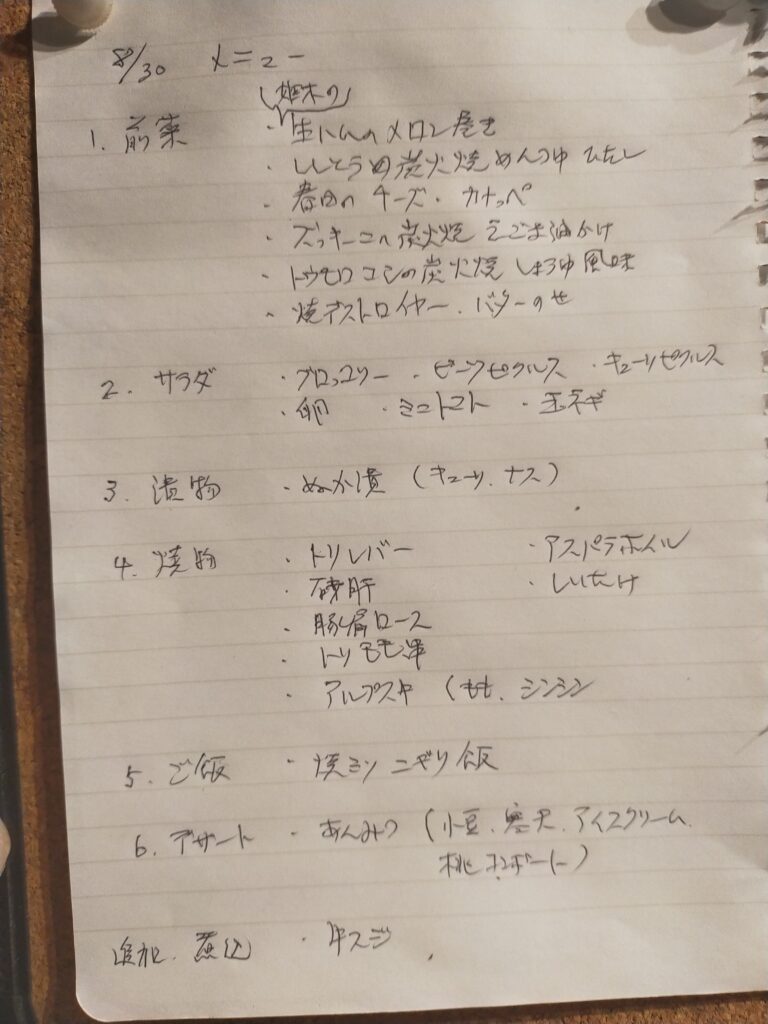山小舎に投宿した学友一行。
彼等の地元の地酒や、貴重な漬物類など、高価なお土産を頂きました。
また、山小舎の食材、アルコールなどは割り勘となり、年金生活の山小舎おじさんには助かりました。
さらに来年の浄化槽設置の寄付金までいただきました!
寄付金は、彩ステーション、娘一家に次いで3例目、延べ7人となりました。
勝手な申し入れながら、ご対応ありがとうございます。
一夜明けた山小舎。
6時半に二日酔いの目を開けて下へ降りると、すでにほぼ全員が起きています。
外に散歩に出ている人もいます。
パン、コーヒーに目玉焼き、野菜スープ、昨日のサラダ、ヨーグルト(ジャムとブルーベリー乗せ)、桃、プルーンなど、夏の山小舎の朝食メニューです。
その前に野草茶を煮だして試飲してもらいました。
すでに活動意欲満々のメンバーですが、麓の町は暑いので標高の高い近辺で、午前中はゆっくりすることになりました。
白樺湖から女神湖、車山を回る一団と、姫木周辺を散策する人、山小舎で待機、と3つのグループに分かれて午前中を過ごしました。
昼食は昨日の残りのおにぎりと、焼き鳥、ほかに焼きそばを2玉作りました。
皆食欲があります。
午後は下諏訪温泉の児湯に入ってから、富士見の別荘へ向かいました。
富士見高原リゾートには、参加メンバーのお父さんが建てた別荘があるのです。
ここで一行を見送る予定だった山小舎おじさんも、学生時代のノリよろしくお邪魔して参加ました。
一行は2台で出発。
山小舎おじさんの乗った車は、温泉の後、下諏訪から20号線で小淵沢まで行き、小淵沢インター近くのドラッグストアでビールなどを買いながら、長野側の富士見高原リゾート内の別荘地へ向かいました。
もう一台は夕食の食材を調達して別荘で合流です。
原生林に点在する富士見高原の別荘地は、国産材で別荘を建てることが条件だったそうです。
まずは堂々とした外観。
中へ入ると、居間は吹き抜け構造で、暖気がいきわたるように配置された3部屋が二階にあります。
広さもあり、普段手入れもされている様子がうかがえます。
皆は、勝手知ったるとばかり雨戸をあけ、網戸にして換気、布団なども用意しています。
 富士見高原リゾート内の別荘へ
富士見高原リゾート内の別荘へ
 部屋の中から外を見る
部屋の中から外を見る
 テーブルでくつろぐ
テーブルでくつろぐ
今は、メンバーのお兄さんが管理しているという別荘。
親族やその友人のみの利用とはいえ、別荘利用の注意やルールが細かく張り紙され、使用料一人1000円を徴収とのこと。
使用料を入れるボックスには、使用者の日付などを記録する台紙もありました。
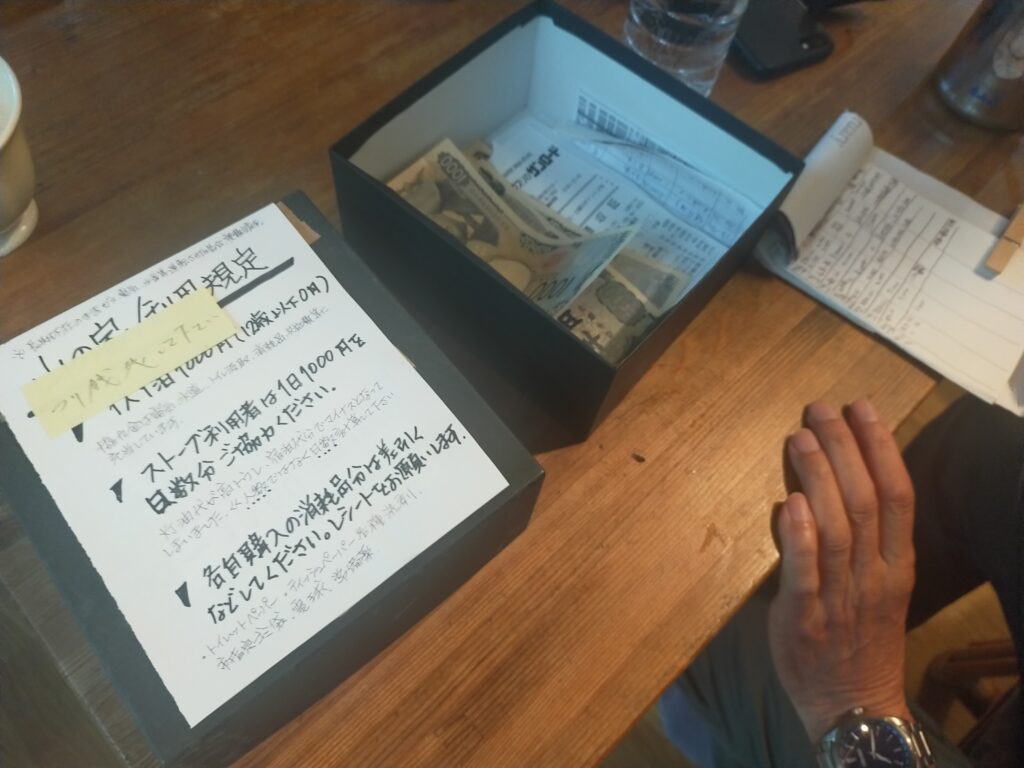 「利用規定」は別荘所有者にとって参考になる
「利用規定」は別荘所有者にとって参考になる
これらの管理方法は山小舎にとっても非常に参考となりました。
富士見の夜はキムチ鍋と昨日食べられなかったアルプス牛のソテーなどで過ぎてゆきました。
ガスコンロや土鍋、炭や七輪まで完備している別荘は居住性十分でした。
翌日は朝食の後、出発の9時まで希望者で別荘地から山道をハイキング。
鹿の道と呼ばれるハイキングコースを歩きました。
網笠山と呼ばれる八ヶ岳最南端のピークが眺望できる地点まで登り、戻ってきました。
南側には富士見パノラマリゾートと入笠山が見えます。
 鹿の道を上る
鹿の道を上る

 霧に包まれた網網笠山
霧に包まれた網網笠山
 パノラマリゾート方面を遠望
パノラマリゾート方面を遠望
この日、一行のうち2人が帰り、残る3人は上田方面へ向かって信州の3日目を過ごしていました。
真田の時代の櫓が残る上田城は、博物館ともども見ごたえがあったとのこと。
来年も皆健康で再会できることを祈ってお別れしました。