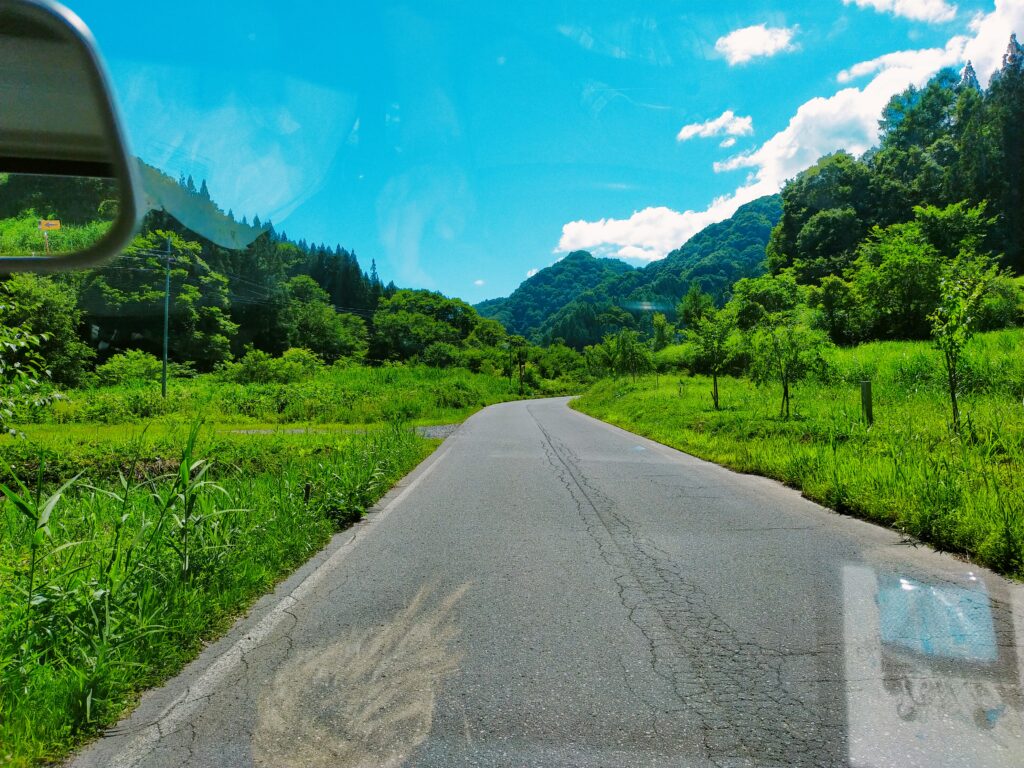鬼無里の中心部にやってきました。
人気はありませんが、長野市の支所の建物やカフェなどがあります。
右手に古そうなお寺がありました。
鬼女紅葉の墓所があるという松厳寺です。
広々とした駐車場に唯一軽トラを止め境内を巡ってみます。

歌舞伎などの演目にもなったという鬼女紅葉の伝説は、956年に都からこの地に流された紅葉という美人が、都恋しさに生まれた息子ともども軍勢を立ち上げ、鬼となって戦ったが征伐されたというものです。
その紅葉の居所跡と墓所が鬼無里にあるのです。

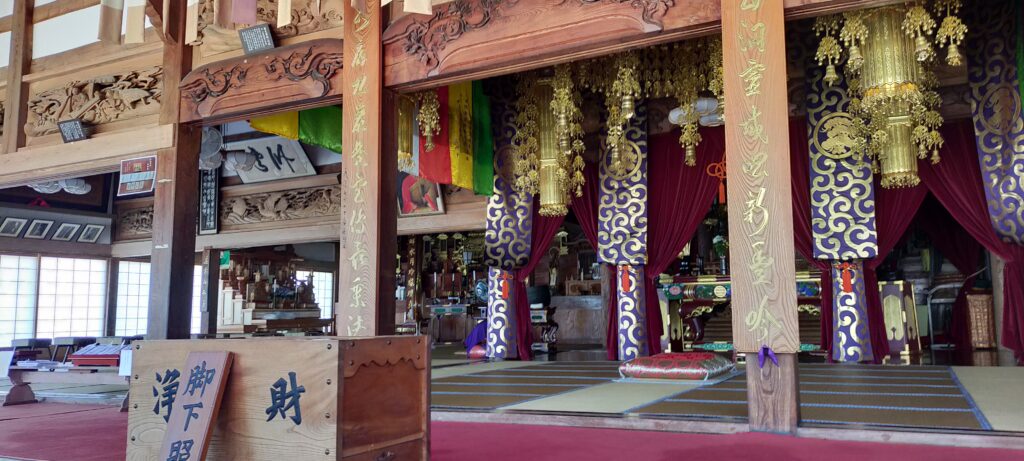
松巌寺の立派な本堂を拝みます。
自動ドアで本堂の扉が開くようになっています。
遠慮なく中に入り、お参りさせてもらいます。
広くて立派な本堂には往時の鬼無里の興隆が偲ばれます。
山門の近く、数体のお地蔵さんに守られるように紅葉の墓所がありました。


軽トラを進め、旅の駅鬼無里に入ります。
直売所と食堂が併設された道の駅のような施設です。
直売所に入ると、イチョウ、クワ、カキ、クマササなどの乾燥させた葉が一袋200円で売っていました。
他の直売所の半値で、種類も豊富です。
一袋400円で備長炭も売られています。
買い!です。



少し早めですが食堂で昼飯です。
名物の蕎麦を頂きます。
ピーマンの天ぷらが食べ放題です。
蕎麦は二八蕎麦。
有名蕎麦店に比べると、蕎麦そのものの打ち方、ダシの手作り感が今一ですが、鬼無里で食べることの意義あり!です。


旅の駅の向いに、ふるさと資料館があります。
県外ナンバーの車で賑わう旅の駅と比べ、来館者が誰もいませんでした。
松代藩時代から麻の栽培で栄え、年貢は麻を売った現金で収めたという鬼無里。
物資の流通でも栄え、近代では善光寺平より早く映画館などができたという。
戦後、GHQにより麻の栽培が禁止されてからは、たばこ、養蚕などを振興したという。
また、和算の天才学者などが生まれ育った地域だという。
それらの歴史、文化が展示された広い資料館を存分に堪能。
色々歴史を解説してくれた学芸員のおばさんも頼もしかった。
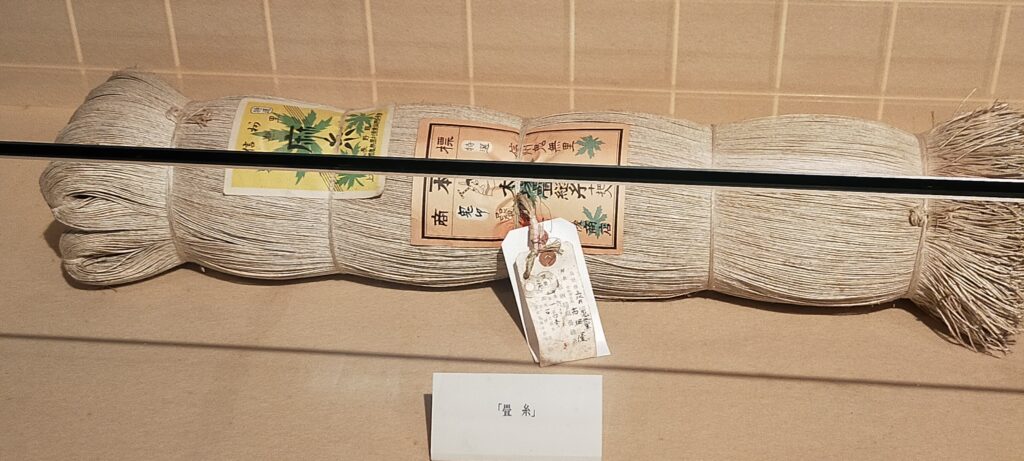

おやきで有名だといういろは堂に寄ってみる。
県外からの客でいっぱいのお店でおやきを買って帰る。
具がたっぷりでおいしかった。

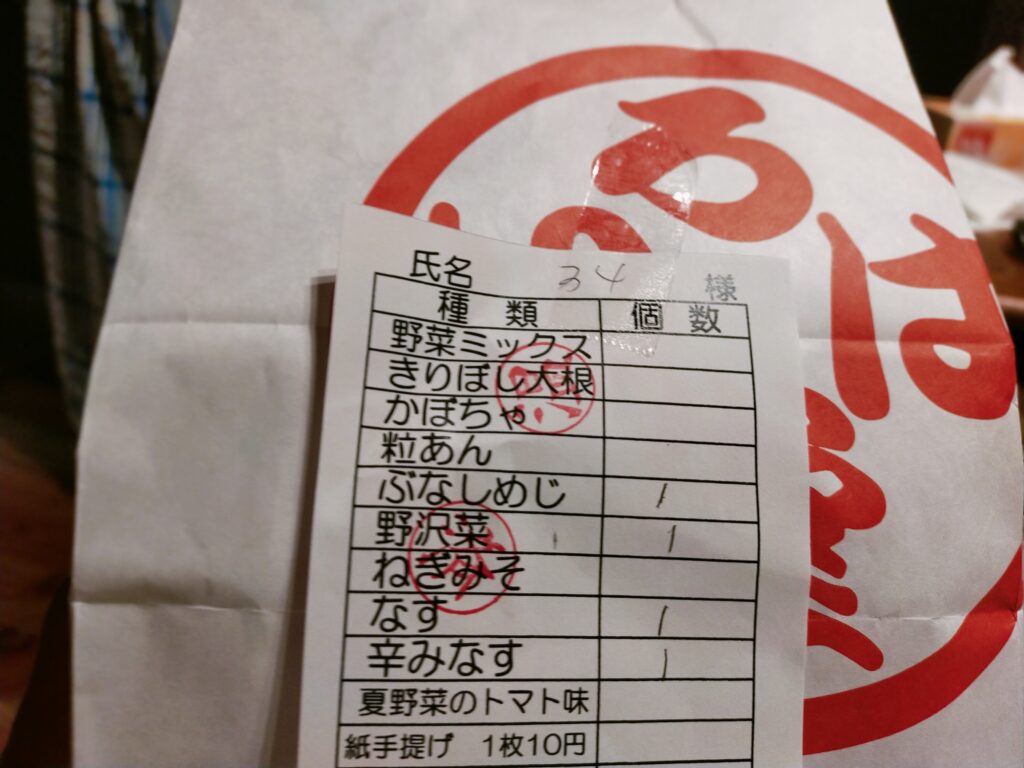
鬼無里街道を進み、鬼女紅葉の居住地だったという、内裏屋敷跡へ行ってみる。
草蒸した高台にその場所はあった。
この地域には東京、西京、二条、三条などの地名が残る。
都からの流れ人が住んだ歴史が確かにあるのだろう。

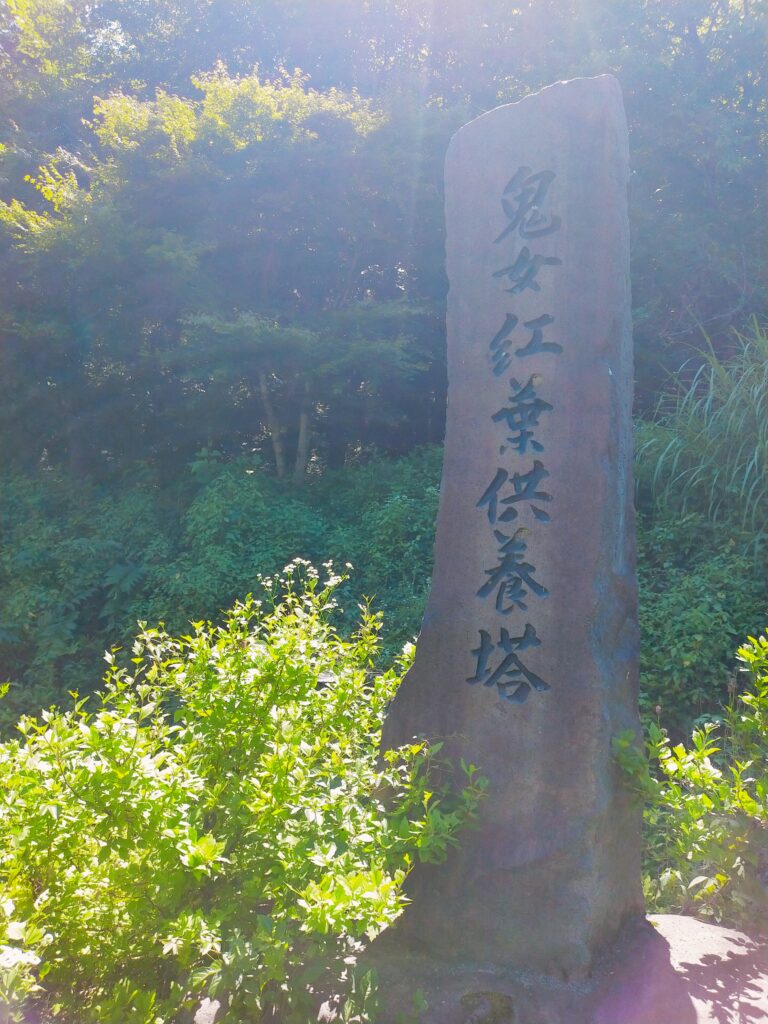

内裏屋敷の後は、鬼無里の湯で立寄り湯。
鉱泉の沸かし湯だというが質感のあるお湯が楽しめました。

ずいぶん遠くまで来ました。
暑い中、帰るのも大変でしたが、充実した流れ旅でした。