今年の山小舎は来客も多く、室内外のリフレッシュの年です。
しばらく行わなかった「大掃除」「廃棄」「手入れ」を行っています。
使わない布団・毛布・シーツ類は思い切って捨て、食器棚もほぼ10年ぶりに中味を取り出し不要な食器類を捨てました。
年1回のルーテイーンとしての、カーテン洗い、本の整理、食糧庫の整理なども行いました。
3年ぶりのルーテイーン復活となったのが、障子紙の張替えです。
玄関への引き戸として障子戸が使われている山小舎では、障子がポイントの一つです。
使う頻度も高く、枠はともかく障子紙の劣化は進みます。日本家屋には障子や襖が似合います。
今年は思い切って障子紙を張り替えました。

晴れた日に障子戸を外に出してホースで水をぶっかけました。
木製の調度品に水をかけるのはご法度なのでしょうが、この際、作業の省力化です。
ついでに枠そのものをきれいにできます。

水をかけた障子戸から障子紙を剥がし、枠の汚れをたわしで洗い流します。
洗ったそばから真夏の日差しで乾いてゆきます。


乾かした障子戸を室内に持ち込んで紙貼りです。
この作業が大変なのです。
ノリの濃さ、枠への糊付け加減、紙の貼り方、とすべての行程で技能的、能率的な作業が求められます。
昭和の家庭では大掃除の一環として毎年行われていました。
昔の日本人の能力の高さを思い知らされます。
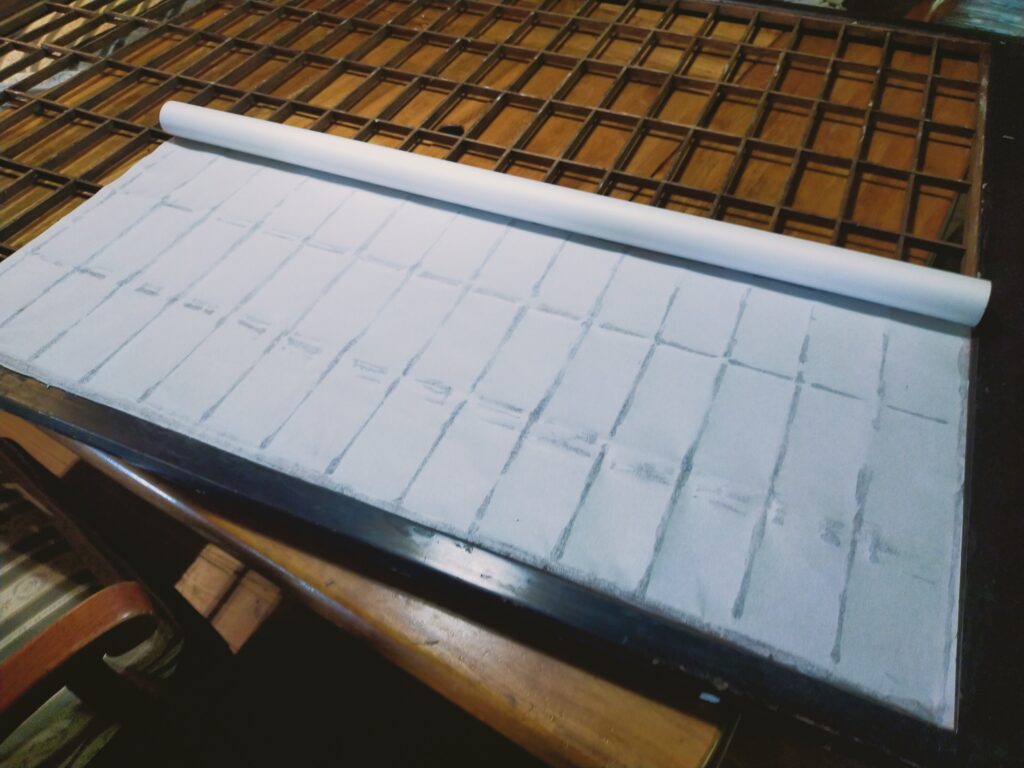
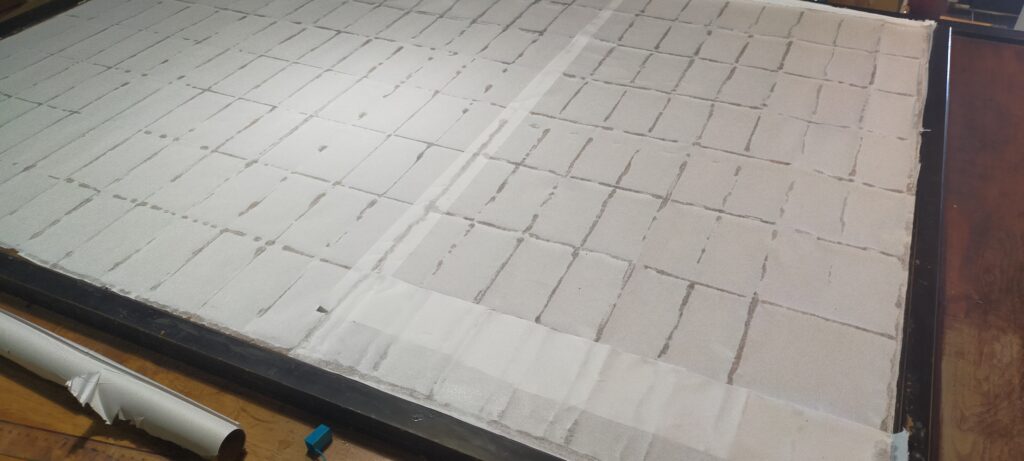
体力、気力、集中力が必要な障子紙貼り作業。
3枚の障子戸に貼り終わるまで、体感時間は半日、気力は1日分使います。
雑ながらなんとか貼り終わりました。
障子がきれいになるのは何とも言えません。
住居に手が入っていて、室内の生気がよみがえる気がします。
3年目の課題がクリアーできました。
家族、来客が来た時の話題にもなります。
ただし水をかけまくった木枠が膨張したのか、引き戸自体の滑りが悪くなったのが難点です。


